岩崎千明
スイングジャーナル 3月号(1975年2月発行)
「ベスト・バイ・コンポーネントとステレオ・システム紹介」より
アルテックのシステムは、本来、シアター・サウンドとしての名声があまりに大きいため、その家庭用システムの多数の傑作も名品も、どうも業務用にくらべると影がうすい。それは決してキャリアとしても他社に僅かたりともひけをとるどころではないのに。つまり、それだけ業務用音響システムのメーカーとしての「アルテック」の名が偉大なせいだろう。
だから、アルテックの名を知り、その製品に対して憧れを持つマニアの多くは、アルテックの大型システムを揃えることをもって、アルテック・ファンになることが多い。そうなればなるほど、ますますアルテックは若いファンにとって、雲の上の存在とならざるを得なかった。
「ディグ」の日本市場でのデビューと、その価値は、実はこの点にある。
「ディグ」のデビューによって、初めて日本のアルテック・ファンは、すくなくとも若い層は、自分の手近にアルテックを意識できるようになったといってもいい過ぎでない。
「ディグは」小さいにもかかわらず、安いのにかかわらず、まぎれもなく、アルテックの真髄を、そのままもっとも純粋な形で秘めている。アルテックの良さを凝縮した形で実現化したといった方が、よりはっきりする。
「アルテックの良さ」というのは、一体何なのであろうか。アルテックにあって、他にないもの、それは何か。
アルテックは、良いにつけ、悪いにつけ、シアター・サウンドのアルテックといわれる。シアター・サウンドというのは何か。映画産業に密着した米国ハイファイ再生のあり方は、どこに特点があるのだろうか。
もっとも端的にいえば、映画の主体は「会話」なのだ。映画にとって、音楽は欠くことができないし、実況音も、リアル感が大切だ。しかし、より以上に重要なのは、人の声をいかに生々しく、すべての聴衆に伝えるか、という点にかかっている、といえるのではなかろうか。
だから、アルテックのシステムは、すべて人の声、つまり中声域が他のあらゆるシステムよりも重要視され、大切にされる。それらは絶対的な要求なのだ。だからこそアルテックのシステムが、音楽において、中音域、メロディーライン、ソロ、つまりあらゆる音楽のジャンルにおいて、共通的にもっとも大切な中心的主成分の再生にこの上なく、威力を発揮するのだ。
音楽を作るのも、聴くのも、また人間であるから……。
「ディグ」の良さは、アルテックの真価を、この価格の中に収めた、という点にある。きわめて高能率なのは、アルテックのすべての劇場内システムと何等変らないし、そのサウンドの暖か味ある素直さ、しかも、ここぞというときの力強さ、迫力はこのクラスのスピーカー・システム中、随一といっても良かろう。
その上、システムとしての「ディグ」は、マークIIになってますます豪華さと貫禄とを大きくプラスした。
「ディグ」の使いやすさの大きな支えは、高能率にある。平均的ブックシェルフが谷くらべて3dB以上は楽に高い高能率特性は、逆にいえば、アンプの出力は半分でも、同じ迫力を得られることになる。システム全体として考えれば、総価格で50%も低くても、同じサウンドを得られるという点で、良さは2乗的に効いてくる。
つまり割安な上、質的な良さも要求したい、この頃の若い欲張りファンにとって、「ディグ」こそ、まさしくうってつけのシステムなのだ。
アンプのグレード・アップを考えるファンにとっても、「ディグ」はスピーカーにもう一度、視線をうながすことを教えてくれよう。パワーをより大きくすることよりも、システムをもうひとそろえ加えて、2重に楽しみながら、世界の一流ブランド「アルテック・オーナー」への望みもかなえてくれる夢。これは「ディグ」だけの魅力だ。
内容外観ともにガッツあるシステム
キミのシステムに偉大な道を拓く点、グレード・アップにおける「ディグ」の価値は大きいが、ここでは「ディグ」を中心とした組合せを考えてみよう。
アンプはコスト・パーフォーマンスの点で、今や、ナンバー・ワンといわれるパイオニアの新型SA8800だ。ハイ・パワーとはいわないが、まず家庭用としてこれ以上の必要のないパワーの威力、それをスッキリと素直なサウンドにまとめた傑作が8800だ。
パネルの豪華さという点でも、8800は文句ない。やや大型の、いや味なく、品の良ささえただようフロント・ルック。ズッシリと重量感あるたたずまい。
「ディグ」とも一脈相通ずる良さがSA8800に感じられるのは誰しも同じではなかろうか。
チューナーには、これもハイ・コスト・パーフォーマンスのかたまりのようなTX8800。
もし、キミにゆとりがあればSA8800の代りにひとランク上の、最新型8900もいい。チューナーは同クラスのTX8900でも、8800でも外観は大差ない。
プレイヤーとしては、同じパイオニアからおなじみ、PL1200もあることだが、今回はビクターの新型JL−B31を使ってみよう。ハウリングに強いのもいい。
カートリッジもこのプレイヤーにはひとまず優良品と
いえるものがついている。
デザイン的にも、また使用感も一段と向上したアームは、仲々の出来だ。このアームをより生かすカートリッジとして、スタントンを加えるのも楽しさをぐんと拡大してくれる。600EEあたりは価格・品質は抜群だ。
出ッとしてマニアライクなオープン・リールの新型、ソニーTC4660を推めようか。







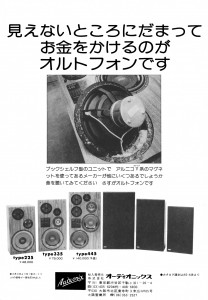

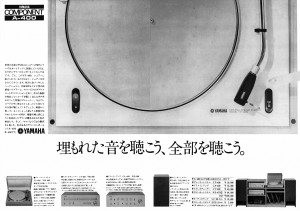




最近のコメント