グレースのカートリッジF8E、F9E、トーンアームG714の広告
(オーディオアクセサリー 1号掲載)
Category Archives: 国内ブランド - Page 118
グレース F-8E, F-9E, G-714
SAEC WE-308NEW, WE-308L
ヤマハ YP-311
ビクター Z-1, Z-1E
ソニー PS-3750, PS4300
オーディオテクニカ AT-15E/G
デンオン DP-1000
ヤマハ NS-690(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
ヤマハのスピーカーの名声を決定的にしたのがこのNS690だ。あとからのNS1000Mが比類ないクォリティで登場してきたので、この690、やや影が薄れたかの感がなきにしもだが、やや耳あたりのソフトな感じがこのシステム特長となって、それなりの存在価値となっていよう。30cm口径の特有の大型ウーファーは、品の良さと超低域の見事さで数多い市販品の中にあって、最も品位の高いサウンドの大きな底力となっている。ドームの中音、高音の指向性の卓越せる再生ぶりは、クラシックにおいて理想的システムのひとつといえる。このヤマハのシステムの手綱をぐっと引きしめたサウンドの特長が大へん明確で組合せるべきアンプでも、こうした良さを秘めたものが好ましいようだ。
ヤマハのアンプが最もよく合うというのはこうした利点をよく知れば当然の結論といえ、CA1000IIはこうした点から、至極まっとうなひとつの正解となるが、あまりにもまとも過ぎるといえる。その場合、ヤマハのレシーバーがもうひとつの面からの、つまり張りつめた期待感と逆に気楽に音楽と接せられる、ラフな再現をやってのける。
スピーカーシステム:ヤマハ NS-690 ¥60,000×2
プリメインアンプ:ヤマハ CA-1000II ¥125,000
チューナー:ヤマハ CT-800 ¥75,000
プレーヤーシステム:ヤマハ YP-800 ¥98,000
カートリッジ:(プレーヤー付属)
計¥418,000
サンスイ SP-4000(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
春以来LMシリーズがヒットしてサンスイのブックシェルフのイメージが盛り上ってきたこの秋、力のこもった強力な新シリーズが鮮烈に加わった。SP4000とSP6000だ。このシリーズの特長ともいえる高音ユニットのホーン構造からも判るとおりユニット各部に対し、質の高さを追求しことがポイントで、LMとは違って音質の面、ひとつぶひとつぶの音のパターンの明確さという点で俄然確かさが感じられる。その質感は、あるいはJBLのそれとも相通ずるものだ。つまり強力なマグネットを源にしてパワフルなエネルギーがあっての成果だろう。この場合、実は組合せにおいてはかえってむずかしくなるもので、例えばJBLのシステムがその用いるアンプのくせを直接的に表出してしまうのとよく似ている。
つまり音がむき出しになりやすいので、この辺をいかにまとめるかが、一般の音楽ファンの好む音へのコツといえる。サンスイのFETアンプBA1000は、この場合最も容易に結論へ導いてくれることを期待してよかろう。ややソフトな中域の再生ぶりがSP4000の引きしまった良さととけ合うのは見事だ。
スピーカーシステム:サンスイ SP-4000 ¥49,800×2
コントロールアンプ:サンスイ CA-3000 ¥160,000
パワーアンプ:サンスイ BA-1000 ¥89,800
チューナー:サンスイ TU-9900 ¥89,800
プレーヤーシステム:サンスイ SR-525 ¥44,500
カートリッジ:エンパイア 2000E/II ¥16,500
計¥500,200
ビクター JS-55(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
ビクターのグレート・ヒットFB5はこのメーカーのそれ以来の路線に少なからず影響を与えたようだ。JS55はFB5のユニットの特長をそのまま拡大したようなサウンドとクォリティとで、そのパワフルな再生ぶりはとうていブックシェルフ型のそれではない。つまり音響エネルギーの最大限度が異例に高いためであろうか、力強さは抜群だ。
このずば抜けた量感あふれるエネルギーは中域から低域全体を支配して音楽のポイントを拡大して聴かせてくれるのだ。ややきらびやかな高域も現代の再生音楽のはなやかさにとっては必要なファクターといえよう。
このスピーカーを引き立たせるには、たとえばセパレートアンプも考えられるが、より力強さを発揮する新型JA−S91に白羽の矢をたてた。ここでは音の鮮度を重視して、暖かな響きを二の次にしたからだ。つまり、あくまで生々しく間近にある楽器のソロのサウンドを捉えようとしたのだ。FB5のエネルギッシュな音にくらべてやや控え目ながらここぞというときに輝かしいサウンドがJS55からは存分に味わえるに違いない。JA−S91はこのとき本領を発揮する。
スピーカーシステム:ビクター JA-55 ¥46,500×2
プリメインアンプ:ビクター JA-S91 ¥130,000
チューナー:ビクター JT-V71 ¥59,800
プレーヤーシステム:ビクター JL-F35M ¥37,500
カートリッジ:(プレーヤー付属)
計¥320,300
ソニックス AS-366(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
ソニックスは海外でよりその名を知られた最もポピュラーなスピーカー専門メーカーで、その作るブックシェルフ型は価格対品質、あるいは実質的投資という点で他社に先がけてきた。クォリティ一辺倒というよりもその価格帯でのユニット構成という点でも優れる。大型システムにも匹敵するスケールの大きなサウンド、やや華麗な中域の充実感などが全体的な特長だ。
その中の中級品種ともいうべきAS366は最も重点的な主力製品だけに一段と充実した内容で、用途の一般的な広さからも誰にも奨められる。
そこでこのシステムをもっとも高いレベルでの再生を考えるとアンプにはやはり相当の品質のものを組み合わせるべきだ。トリオのKA7300は全体にKA7500を格段に上まわるすばらしい質とエネルギーとを、ステレオアンプとして最も理想的なモノーラル2台にわけたといえるほどのセパレーションで実現している。中音から低音の定位の抜群な良さを示す。このアンプのもつ可能性は同じスピーカーでもひとけた違ったグレードにまでも高めてくれるのには目を瞠る。マイクロの超低域までの安定したサウンドと共に、全体の完成度はきわめて高い。
スピーカーシステム:ソニックス AS-366 ¥41,800×2
プリメインアンプ:トリオ KA-7300 ¥65,000
チューナー:トリオ KT-7500 ¥48,000
プレーヤーシステム:マイクロ DD-7 ¥74,800
カートリッジ:エレクトロ・アクースティック STS155-17 ¥8,700
計¥280,100
パイオニア CS-T5(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
パイオニアのブックシェルフ型の新たな流れがこのCS−T5、T3だ。今までにない積極的な前に出る音をはっきりと狙い見事な形で聴く者に迫るサウンドがこの新シリーズの大きな特長で、今までのパイオニアのスピーカーになかったサウンドでもあるのだ。
このスピーカーが加わることの音楽へのアプローチの拡大ははかり知れぬ。
もし、このスピーカーをジャズ向きだなどと評するものがいるとしたら、それは音楽の真の聴き方を知らないといわれそうだ。つまりあらゆる音楽が、それを知れば知るほど身近に欲しくなるものだ。そうした欲望はなにもジャズに限ったことでは決してない。
つまり、オーディオマニアが音楽ファンになったときに欲しくなる音をCS−T5は提供してくれる。
その鳴らし方はそれこそ聴き手の求め方次第だが、最もオーソドックスな形としてSA8900またはSA9800というこの一年間ベストセラーを続けた製品を指定しておこう。パワーのゆとりがあればトーンコントロールで望む音へのアプローチは大きく拡大されるし、しかもこの入手しやすいスピーカーの価格を考えると、好ましい価格のアンプだから。
スピーカーシステム:パイオニア CS-T5 ¥29,800×2
プリメインアンプ:パイオニア SA-8900 ¥78,000
チューナー:パイオニア TX-8900 ¥65,000
プレーヤーシステム:パイオニア PL-1250 ¥45,000
カートリッジ:ADC Q32 ¥9,000
計¥256,000
ヤマハ NS-1000M(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
ベリリウムを素材としてダイアフラムに採用し、理論と技術との両面から達成したまれにみるデバイスは日本のスピーカーの世界に対する誇りでもあろう。クリアーで鮮麗な響きがこの高いレベルの再生を物語り、アタックのまざまざとした実感は、ちょっと比べものがないくらいだ。品の良さに力強さが融合したヤマハの新たなる魅力だろう。
大型のブックシェルフともいうべきこの1000Mは、ウーファーの量感もあって、豊かさを感じさせる見事な再生ぶりがひとつの極限とさえいえる。ただこのためには、アンプは高出力かつハイクォリティを条件とすることになるが、この点で、ヤマハの誇るFET採用アンプBIは、まさに1000Mの女房役として切っても切れない存在といえよう。
プリアンプにはあらゆる点で、オーソドックスな良さを持つCI、またはより高い鮮度と純粋さを音に感じるC2が適切。好みからいえばC2といいたいのだがマニアの多様性、一般性からはより高級で、壮麗なサウンドのCIというところだろう。プレーヤーは使い勝手とデザインの両面から考えてB&Oを選ぼう。
スピーカーシステム:ヤマハ NS-1000M ¥108,000×2
コントロールアンプ:ヤマハ C-I ¥400,000
パワーアンプ:ヤマハ B-I ¥335,000
プレーヤーシステム:B&O Beogram 3400 ¥140,000
カートリッジ:B&O SP12 ¥19,000
計¥1,110,000
ダイヤトーン DS-50C(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
ダイヤトーンのフロア型というだけでスタジオユースのモニターシステムのイメージが濃いが、その外形といいサウンドといい、期待を越えてマニアにとって新たなる魅力を秘めた新型といえるスピーカーだ。
30cmのウーファーながらゆとりとスケール感はもっと大型のシステムに一歩もひけをとるところがない。しかも中音域の充実感、バランスの良い再生帯域のエネルギースペクトラム。広帯域という意識は感じさせないにしろ、モニターたり得るだけのハイエンドの延びは今日の再生と音楽の条件を十分に満足させよう。能率の高さからパワーアンプの出力はあまり大きい必要はないにしろ音離れのよい響きに迫力をも求めれば高出力ほどよいのは当然。マランツMODEL1150はその規格出力以上のパワー感をもち、こうしたときに最も適応できよう。価格を考えても国産メーカーの中でこの質に達した製品は決して多くないはずだ。中域の充実感はダイヤトーンスピーカーの持つ最大の美点だが、マランツのアンプはこれに一層みがきをかけるであろう。
EMTのカートリッジがその質をさらに高めてくれる。
スピーカーシステム:ダイヤトーン DS-50C ¥88,000×2
プリメインアンプ:マランツ Model 1150 ¥125,000
チューナー:マランツ Model 125 ¥84,900
ターンテーブル:マイクロ DDX-1000 ¥138,000
トーンアーム:マイクロ MA-505 ¥35,000
カートリッジ:EMT XSD15 ¥65,000
計¥623,900
クライスラー Lab-1000(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
糸づりダンパーというグッドマン・アキシオム80と同じ技術を採用した30cmウーファー、同じくフリーエッジの中音用の強力なドライバー、さらに平板ダイアフラムという独特なる技術を具えたユニットを組合せて3ウェイ構成のブックシェルフ型に相当すべき大型フロア型システム。マルチセルラーホーンを中音、高音に用い、その高音ユニットを内側に向けるという奇抜なアイデアながら、かつモニターユースにもなり得るクォリティを確保した高水準の安定度をサウンドに感じさせるのはロングセラーのキャリアからか。
いかにも音ばなれのよい響きの豊かさが、このラボシリーズの大いなる特徴といえるが、それをなるべくシンプルな純度の高い形で発揮させることがカギであろう。
国産の高級アンプの中で、ひときわその純粋さを形、内容ともに感じさせるのがテクニクスの最新セパレートアンプだ。この音と価格は、ちょっと比類ない魅力としてマニアの多くが関心をもつに違いあるまい。クライスラーの高い可能性を発揮するのに、もっとも適切なベストのひとつであると思う。ダイナベクターのMC型高出力カートリッジも見落せぬ魅力だ。
スピーカーシステム:クライスラー Lab-1000 ¥139,000×2
コントロールアンプ:テクニクス SU-9070 ¥70,000
パワーアンプ:テクニクス SE-9060 ¥85,000
プレーヤーシステム:テクニクス SL-1500 ¥49,800
カートリッジ:ダイナベクター OMC-3815A ¥18,000
計¥500,800
Lo-D HS-400(組合せ)
岩崎千明
コンポーネントステレオの世界(ステレオサウンド別冊・1976年1月発行)
「スピーカーシステム中心の特選コンポーネント集〈131選〉」より
ハイファイ・スピーカーのもっともむずかしい面はクォリティの管理にあるといえるが、日本の電気メーカーとして、常にオリジナル技術で先頭を切ってきたLo−D技術陣は、HS500を通して得たこの至難の問題点を真正面から取り組んで「信頼性」「寿命」さらに「生産性」をも一挙に解決すべく、メタル・サンドウィッチのスチロール系のコーンを開発した。
大型のHS500がこの開発の土台となったが、HS400はこの新デバイスを量産製品に実現したという点で、世界に誇るまさに画期的製品だ。特有の音響的なピークを電気的共振型で除くという点を危ぶむ声もないわけではないが、実質的に特性上なんらの支障もないということで成果は製品を聴く限り表面化していないのも確かである。たいへん活々として再生ぶりが前作HS500との相違点で、広帯域に亘る極めて低歪再生ぶりはまさにそのものといえよう。組合せるべきアンプによって生命感溢れるサウンドは躍動しすぎになりかねないので無理な再生を狙うとき、ほどほどに押えが必要かとも思われる。日立のアンプV−FETを採用したHA500Fはこうしたときにうってつけ。
スピーカーシステム:Lo-D HS-400 ¥47,800×2
プリメインアンプ:Lo-D HA-500F ¥89,800
プレーヤーシステム:ソニー PS-3750 ¥47,800
カートリッジ:(プレーヤー付属)
計¥275,600
ダイヤトーン DS-50C
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
DS38Bとおそらく同じユニットをフロアタイプにまとめた製品だと思うが、念のため、38Bと一緒に比較試聴してみた。まず大づかみにいえば同じ範疇の音である。そのことをまず言っておいてこまかな比較をすると、38Bではことに重く鈍く感じた低音域に、開放感ともいえる軽さ、(といってもあくまても同じ兄弟という枠の中での話だが)が出てくる。また全音域を通じて、38Bよりも音が空間に浮かび漂う感じが出てくる。それらの差はわずかとはいっても、総体には38Bより聴き疲れしにくい。あるいは38Bほど自己主張が強くないといおうか、ランクが上がった音質といえる。なお、この製品にかぎらず、フロアタイプであっても概して台の上に乗せた音が、音のもやつきがなくなる傾向があるが、50Cの場合も、ブロック1~2個分上にあげた方がよい。カートリッジについては38Bのところで書いたと同じことがいえる。これだけの音の密度にさわやかさが加わったら、もっと好ましい音になるのにと思う。
採点:85点
Lo-D HS-400
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
低音から高音にかけて音域上の欠落感はほとんどなく、たとえばHS500で中低域にやや音の薄い部分があったのにくらべると確実に改善されている。国産でたとえばテクニクスやトリオの音の輪郭に毛羽立ったような、またはどこか粉っぽいような感じのつきまとうのにくらべると、HS400の音はきわめてクリアーという感じがする。ところがこのクリアーさは、私にはとても独特で奇異な音に思える。というのは、たとえば弦楽器の合奏の際に、いわばざわめきのような、楽器の周囲に漂うような雰囲気が生じ、それはレコードにもたしかに録音され、たいていのスピーカーではそれが再現されると私は思うが、HS400からはそういう音がまったくといっていいほど聴こえてこない。もうひとつ、すべての音に独特の色がつく感じで、いわば音楽を淡い黄色の半透明ガラスを通して眺めるような、あるいはゼリーで練り固めたような、土産物によくあるプラスチックで鋳固めた置き物のように音楽が聴こえる。奇妙な体験だった。
採点:65点
テクニクス SB-6000
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
左右に思い切り広げて設置して、適度に壁から離し、ブロック1~2個程度の頑丈な台に乗せる。そして、両スピーカーから等距離の正しい聴取位置で聴くと、眼前に、幕を一枚取り除いたような空間の広がりと奥行きが展開する。こういうエフェクトを楽しく聴かせるのが、今回のSB5000と7000を含むテクニクスの新シリーズの共通の特徴だ。この感じは、最近のヨーロッパ系の優秀なスピーカーシステムが聴かせてくれるエフェクトと同質だがSB6000の場合、この価格、ということを考えに置くと、音質の方に2~3注文をつけたくなる。第一二、SB5000のところでも書いたが音を隈どる輪郭の質感に、なんとなくザラつく感じ、この価格としてはもうひとつ磨きが不足しているような感じが残ること。もうひとつ、小音量のときは良いがパワーを上げると、弦や声で中域に多少きつい感じが出てくることだ。むろん、それらは水準以上のスピーカーシステムであることを認めた上での注文だが。
採点:88点
ダイヤトーン DS-38B
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
DS28B(36号237ページ)やDS261で、ダイヤトーンのスピーカーにしては中域をおさえてよりナチュラルな方向に近づいていることを書いたが、38Bになると、再び中域に密度を持たせてがっしりと構築した特徴のある音色が出てきている。楽器の音ひとつひとつが、ほかのスピーカーよりも重く聴こえる。眼前に奥行きをともなって爽やかに展開する傾向のレコードをかけても、厚手の緞帳を通して鳴ってくるような、鈍い錆色のような音に聴こえがちだ。ジャズのコンボでは中域の密度の高さが一種力強い迫力を聴かせるが、低域がそれにくらべて重く、高域ももっと爽やかに延ばしたくなる。総じてハードなタイプのポピュラー系が最も無難で、それもオルトフォンVMS20EやB&O・MMC4000のようなカートリッジだと音がベタついて鈍くなるので、シュアーV15/IIIのようなアクの強いカートリッジで強引にドライブする方が合うと感じた。台はあまり高くない方(20~30センチ)がよかった。
採点:79点
サンスイ SP-6000
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
SP4000と並べて切り替えながら比較試聴したが、当然のことながらまったく同じシリーズとして、よく似た音質につくられていることがわかる。その上でこまかな比較をするなら、エンクロージュアやウーファーがひとまわり大きくなったために音にゆとりが生じている。たとえばピアノの音が、SP4000よりもピアノという楽器の大きさにいっそう近づいている。低音域での音のスケール感が改善されることによって、中~高音のユニットはほとんど同じものらしいにもかかわらず聴感上では、たとえばシンバルのような楽器の場合にも4000よりも楽器の大きさがよりよく再現され、迫真感あるいは現実感が(その差はわずかであるが)確実に増している。しかしその反面、たとえばバルバラの唱うシャンソンなどで彼女の声がいくらか重くあるいは太くなる傾向があって、比較上は4000の方が線が細いが演奏されている場の空気感のような要素がいくらか優れていることがわかる。他の点は4000の項を参照して頂きたい。
採点:82点
ビクター SX-5II
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
どちらかといえばスタティックで控えめな、彫りの深さや音の艶に不足を感じる柔らかな音色だが、ことにクラシック系のオーケストラを鳴らしたときの、弦の自然な響きには、国産の攻撃的な音の多い中で改めて評価をし直した。細かいことをいうと、弦のオーヴァートーンにややケバ立つところがあったり、そのせいか倍音だけがやや離れるというか、または基音と倍音との間に僅かな不連続があるともいえるが、クラシックのコンサートプレゼンスとでもいうべき自然な柔らかい響きは、国産スピーカーの多くについて最も不満な部分であるだけに、多少の弱点はあっても価格とのかねあいその他で、良いスピーカーのひとつに数えてよいと思った。ピアノや打楽器のアタックには少し弱い。また、スピーカー自体の音は平面的な傾向なので、カートリッジやアンプの方に、表象の豊かさ、彫りの深さ、音の艶など生かす製品をうまく組み合わせて弱点を補う方がいい。高い目の台、左右にひろげて、背面は壁面から離した方がいい。
採点:91点
オンキョー M-6
瀬川冬樹
ステレオサウンド 37号(1975年12月発行)
特集・「スピーカーシステムのすべて(下)最新40機種のテスト」より
オンキョーのスピーカーが、また変身を試みた。まず感心したのは低音のよさだ。楽器の動きが実に軽やかで自在。箱鳴り的なブーミングがほとんど感じられず、ベースやピアノの低域の実体感をニュアンスをこめてよく再現する。ただし以上のような低音を聴くには、ブロック1~2個分の(低めの)台に乗せて背面を壁に近づける方がいい。高い台で壁から離すと低音が不足する。2ウェイにもかかわらず、中音域の抜けた感じが全くないという点、低音・高音両スピーカーの中音のコントロールがうまくいっているのだろう。ただ、手放しで感心してもいられないのは、中~高域以上の音色に、硬い頑固な表情がつきまとう点で、ことに弦やヴォーカルを不自然に聴かせる。反面、コンボジャズ等のスネアやシンバルの音が、腰くだけにならず実感豊かに輝くあたり、ふっと聴き惚れさせる良さがある。ただしこの製品も試作の段階で、市販までに中~高域はもう少し改善されるそうだから、期待のもてるスピーカーのひとつといってよいだろう。
採点:88点

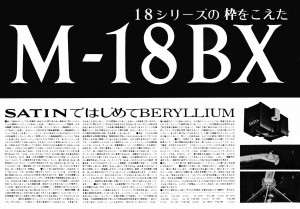
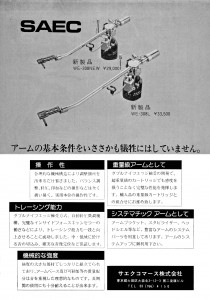
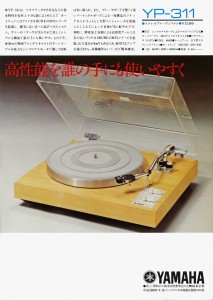




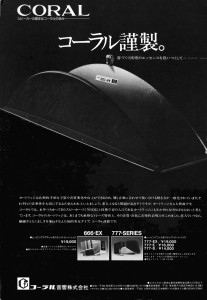
最近のコメント