岩崎千明
スイングジャーナル 4月号(1974年3月発行)
「AUDIO IN ACTION SP-505J、707Jのシステム・アップ」より
SJ試聴室に、山水JBLのシステムSP707J、505Jそれに新しいJBLのシステムL88プラスがずらりと勢揃いする。その様はまさにJBL艦隊ともいうべきか、戦艦707J、巡洋艦505J、駆逐艦L88プラスと威風堂々と他の居並ぶシステムを圧倒し去る。この山水JBLのシステムが高音ユニットを加えることによって、どれほどグレード・アップするかを確かめ試聴する目的で一堂に会したわけだ。
これらのシステムSP505J、707Jは、発売された状態では、それぞれ30cmと38cmのフルレンジが箱に収まった形だが、トゥイーターを加えることにより数段高いグレードに向上し、名実ともに世界最高のシステムと成長し得る。
こうした大いなる可能性こそ、これらのシステムの大きな魅力と源となっているのだが、そのためこのシステムの愛用者や購入予定を願う多くのファンから、いかなる道が最もよいのかという質問がSJ編集部へ発売以来あとをたたずに来ている。そこで今月は、これを読者に代って試みよう。
まず、SP505J、価格88、000円。JBL・D123、30cmフルレンジが中型のフロアータイプのチューンド・ダクト型エンクロージュアに収められている。
D123はJBLサウンドの発足以来ごく初期から戦列にあり帯域の広いことでは定評のあるフルレンジだ。低い低音限界周波数とアルミ・ダイアフラムから輻射される鮮麗な高音域はJBL特有の高能率のもとに迫力にみちたスムースな再生を可能にする。
SP505Jは、高音用ユニットとしてLE20、075、175DLHの3つの中から選べるが、組み合わせるべきネットワークはそれぞれちがってLE20はLX2、075はN2400、175DLHはLX10と組み合わせることが考えられる。
価格は、それぞれの組合せで大きく違いLE20(20、100円)+LX2(14、000円)、075(38、200円)+N2400(15、600円)、175DLH(82、000円)+LX10(10、200)となるからどれを選ぶかフトコロと相談をして可能性の近いものをねらうことになるが音の方もかなりの違いを見せ、結論からいうと刺激的な音をさけるのなら、LE20、ハードなジャズ・サウンドをねらうなら無理をしてでもLE175DLHをねらうべきだろう。つまり、本誌の読者なら少々がまんをしてでも将来175DLHを加えることを、ぜひ薦める。
●LE20とLX2を組み合わせる場合
JBLの山雨度は実に不思議で使うものの好みの音を「自由」に出してくれる。LE20との組合せの場合、ソフトな品のよい迫力が、その特徴だ。繊細感に満ちたクリアーな再生ぶりはまさに万能なシステムというべきで、クラシックのチェンバロのタッチからコーラスのウォームなハーモニーまでニュアンス豊かに再現する。しかも、ジャズの力強いソロにも際立った鮮麗さでみごとにこなしてくれる。ロリンズ・オン・インパルスのシンバルが少々薄い感じとなるが、タッチの鮮かさはやはりJBL以外の何ものでもない。全体にバランスよく、完成された2ウェイ・システムが得られる。
●075とN2400を組み合わせる場合
これは075の高能率な高音が、ちょっとD123のサウンドと遊離してしまう感じがあって、鮮烈なタッチのシンバルだけが浮いてしまう。D123のバスレフレックスの組合せから得られる深々とした低音がLE20の場合みごとに引き立て合うのに、075では、その特徴が075のよさを相殺してしまう感じなのだ。ピアノの高音のタッチがキラキラしすぎるし、ミッキー・ロッカーのシンバルワークだけが、ややきつくなる感じ。075はかなりレベルをおさえて用いるべきだが、そうなるとLE20とかわりばえがしなくなる。
●175DLHとLX10を組み合わせる場合
なにしろ、ロリンズのテナーの音までが力強くなって、輝き方が違ってくる感じだ。本田のタッチのすさまじさも175DLHとの組み合わせで俄然、迫力を加えてくるし、何とベースのタッチの立ち上りまで変ってしまう。
まあ結論として、やっぱり175DLHを加えないとジャズ・サウンドの迫力は完全ではないのだ。拡がりと余韻の豊かさが加わるのは、175DLHの指向性のよいためか。
175DLHの場合、高音用とはいってもクロスオーバーが1200hz付近だから、中音まで変ってくるのは、あたり前だが、それにしてもテナーやピアノなど中音はおろかベースからタムタムなど低音のアタックまでがすっかり変わり、D123が見ちがえるように迫力を加えてくる。やはり、ハードなジャズ・ファンだった175DLHをねらうべきだろう。
SP707JはおなじみD130の38cmフルレンジでJBL精神むき出しの強力型ユニットを、これまたJBLならではの大型バック・ロードホーンのエンクロージュアに収めたシステム。元来、C40ハークネスとしてJBLオリジナル製品があったが、72年度よりC40はカタログから姿を消してしまったので、SP707Jの存在意義は大きい。C40のシステムとしてはD130単体と、D130+075の2ウェイ、D130A+175DLHの2ウェイの3通りが選べたが、日本のファンの間では後者がよく知られている。価格176、000円は決して安くはないがJBLオリジナル製品から比べれば安いものだ。
組み合わせるべき高音用ユニットとしては、075、LE175DLH、LE85ユニット・プラスHL91ホーン・レンズの3通りがある。さらに、それぞれユニットをダブらせて用い、クロスオーバーをかえて3ウェイにすることをメーカーでは言っているが、まずその必要はないと結論してもよかろう。つまり、JBLはよほどの音響エネルギーを必要とする場合でない限り、ホールや劇場などを除いては3ウェイの必要性はないと言ってよかろう。
さて、それぞれのユニットの試聴結果は、投ずる費用に応じてハッキリとグレードの高さを知らされ、どれもがD130単体の場合に比べて、格段と向上する。一段とではなく、格段とだ、つまり、SP707Jはこのままの状態ではなく、上記の3種のユニットのどれかを選んだ2ウェイとして初めて完全なシステムとなると言いきってもよい。それも世界最高級のシステムに。フトコロと相談して、075との2ウェイにするのもよい。ゆとりがあれば是非ともLE85+HL91をねらうべきであるのは当然だ。
075とN7000が38、200円+16、700円。LE175DLH+N1200は82、000円+26、800円。LE85+HL91とLえっ苦5は83、000円+23、200円+41、500と価格は段階的に大きくステップ・アップするが、その差が音の上にもハッキリと表われてくるのだから言うべきところがない。
●075とN7000を組み合わせた場合
これが意外にいい。SP505Jでは何かどぎつくさえ感じられた075が、707Jとの組合せでは俄然生き返ったように鮮明な再生をかってくれる。さわやかささえ感じる。のびっきった高音はアウト・バックのエルビンのシンバルのさえたタッチを、軽やかに鳴らす。707Jの音の深さが一段と加わり、力強い低音がアタックでとぎすまされてくる。特に音場感の音の拡がりが部屋の大きさをふたまわりも拡げてしまうのには驚かされる。
JBLの怖じナル003システムはD130と同じ075をN2400と組み合わせされているが、この組合せを試みたところ、中域の厚さが確かに増し、ロリンズのテナーは豪快さを加えるが、シンバルの澄んだ感じがやや失われるのを知った。どちらをとるかは聴き手の好みによるが、オリジナルの003システムの場合のN2400ではなく、7000HzのクロスオーバーのN7000を指定したメーカー側の配慮も、また充分うなずけるものであるのは興味深い事実だ。
175DLHこそ、D130とならぶJBLの最高傑作であると20年前から信じ続けているのを、ここでもやはり裏付けされたようだ。175DLHはD130の中音から低音まですっかりと生き返らせ、現代的なパーカッシブなジャズ・サウンドにみなぎらせ、鮮烈華麗にして品位の高い迫力をもってあらゆる楽器を再生してくれる。
アウト・バックのエアート・モレイラのたたき出す複雑なパーカッションは大きなスケールで試聴室の空気をふるわせる。特に、バスター・ウイリアムスのベースのプレゼンスある響きは、大型の楽器を目前にほうふつさせ、エルビンのドラムスとの織りなすサウンドをみごとに展開してくれる。
●LE85+HL91をLX5と組み合わせた場合
175DLHの場合に比べて音の密度が格段と濃くなり、音のひとつひとつの粒立ちがくっきりと増してくるのはさすが。175DLHに比べ、価格のうえで50%アップになるが、その差は歴然とサウンドに出る。
もし、ゆとりさえあればLE85といいたいが、175DLHとして世界最高のシステムとなり得るのだからLE85は音のぜいたく三昧というところだ。なお、LE85の場合はホーンとデュフューザーが大きく、バックロード・ホーン型エンクロージュアのうえにのせるかたちになる。この場合、ぜひ注意したいのはHL91のホーン・レンズの後方には、、必ず厚板で音が後に逃げるのをふさがなければ完全とはいえない。つまり、ホーンを板につけ、板の前にデュフューザーをつけるべきで、板の大きさはデュフューザーよりひとまわり大きいのが望ましい。メーカーでこの板を作ってくれることを望むところだ。
最後に、JBLオリジナル・システムL88プラスについて、ちょっとふれておこう。好評のL88のグリルを変えた新型であるL88プラスは、M12と呼ばれるキット34、300円を買いたして、3ウェイに改造出来得る。このキットの内容はLE5相当の12cm中音用ユニットと、ネットワークのコンビである。接続はコネクターひとつだけで、88プラスの箱のアダプターをはずしてつけることにより誰にでも出来るが、このエクスパンダー・キットを加えると、音域はまさに拡張された感じで中音のスムースさを加え、バランスが格段と向上して豊麗さをプラスしてくれる。
JBLというブランドのシステムに対する、ジャズ・ファンの期待と信頼は、他のオーディオ・システムに例がないほどである。それを製品の上で、はっきりとこたえたのが、D130であり、D123である。D130のみでアンプの高音を強めた用い方により、D130のシステムは、ジャズ・サウンドのもつ醍醐味を満喫するのにいささかも不満を感じさせない。ましてD123のシステムにおいておやである。アンプの高音を3ステップ上げた状態で、我が家においてただ1本のD130と見破った者は、メーカーのエンジニアを含めまだひとりたりもいない。
それを、さらにオリジナルJBLのサウンドに向上させるのが、この2ウェイ化だ。ひとつ気になるとすれば、D130をベースとしたオリジナル・システムは003と名付けた075を加えたものだけである。
あくまで、オリジナルJBLに忠実ならんとする者にとってはD130うウーファーに使うことを将来ためらう向きもあるかも知れない。あえてというなら、130Aを買い換えなければなるまいが、ジャズの楽器の再現を主力にするならば、D130によりリアルなプレゼンスを認めることは容易であろう。



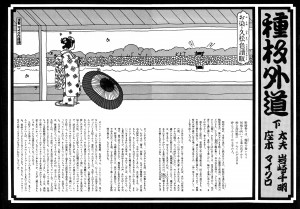


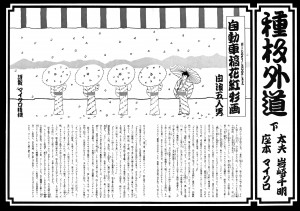





最近のコメント