ラックスのプリメインアンプSQ505、SQ606の広告
(スイングジャーナル 1968年11月号掲載)
Daily Archives: 1968年10月20日
ラックス SQ505, SQ606
サテン M-11/E
ナショナル SA-54
トリオ MT-45
ビクター SSL-96TS
ナショナル FRONTIER760
ナショナル RS-796U
ソニー PS-1200
パイオニア IS-6032
シュアー M44-5
コーラル BETA-8, BETA-10
アルテック A7
サンスイ AU-555
岩崎千明
スイングジャーナル 11月号(1968年10月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
山水が、67年度ハイ・ファイ市場のベスト・セラー・アンプである傑作AU777を曹及型化したAU555を発表したのは、今春であった。そして、ちょうど同じ時期に、米国ハイ・ファイ市場で長期的なベスト・セラーを約束されたARのアンプが日本市場に入ってきた。
この2つアンプはいろいろな意味で、それぞれの国民性をはっきりと表わしている点で、同じ普及型アンプながら対照的といえる。
もっともARのアンプは、米国市場でこそあのあまりに著名なスピーカーAR3とともに、250ドルという普及品価格である、その点にこそ大きな価値があるのである。つまりコスト・パーフォーマンスの点でずばぬけているのであるが、日本市場では、ともに10万をかるくオーバーする高価格な高級品としてみなされており、その本来の価値がどこにあるのか見うしなわれてしまっている。しかし、本国では平均的月収の1/2〜1/4程度のあくまで普及品なのである
さて、ARのアンプであるが、ARの創始者であり今春の組織変えまでの中心であり社長であったエドカー・ヴィルチャーの完全な合理主義にのっとった厳しい技術の集成である。そこには、スピーカーにみられると同じの、不要な所は徹底的に省略し、必要な所はとことんまで追求して費用も惜しみなくつぎこむという、いかにもきっすいの技術者根性がむき出しにみられる。そして、そのパネル・デザインは無雑作で、かざりひとつないみがきパネル、そこに5つのつまみが、デサインもなしにといいたいほど無造作に並ぶ。しかし、このつまみの間かく、大きさまで使いやすさを計算したものに違いないことは扱ってみて納得できる。もっともニクイ点は、スピーカー・システムAR3とつないだときに最大のパワー60/60ワットをとりだすことができる点であろう。
しかし、ここであえて断言しよう。暴言と思われるかも知れないが。もしARのアンプの日本価格が半分になったとしても日本市場では、ARのアンプは売れることはないだろう。歪なく、おとなしい、優れた特性だけでは日本のマニアは承知しないのである。ARのスピーカーが圧倒的に高い信頼性を得ている日本においてもである。
その解答が、AU555にある。AU555をみると国こそ違うが、それぞれの市場においてほぼ同じ地位にある2つのアンプのあり方の違いが、そのままその国のマニアの体質の違いとか好みを表わしていることを発見する。
AU555には、ARアンプのような大出力はない。ほぼ半分の25/25ワットである。しかし、その範囲でなら0・5%という低いひずみは実用上ARアンプにも劣るものではなかろう。
しかも、ARと違って入力トランスのない、つまり位相特性のすぐれた回路構成とフル・アクセサリー回路がマニアの好みと市場性をよく知ったメーカーらしく、AU777の爆発的な売れ行きのポイントが、この3万円台のアンプにも集約されているのをみる。
25/25ワットの出力も日本の家屋を考え、サンスイのスピーカーの高能率を考慮すると、ゆとり十分といえよう。加えて、プリ・アンプとパワー部が独立使用できる点も、マルチアンプ化の著しい日本のマニア層の将来をよく見きわめたものといえよう。そのひとつがダンピング・ファクター切換にもみられる。2組のスピーカー切換と6組の入力切換はマニアにとって、グレード・アップのステップを容易にしよう。最近、さらにこのAU555と組み合せるべきチューナーTU555が出たが、共に今後当分の間、中級マニアにとってもまた初歩者にとっても嬉しいアンプであるに違いなかろう。
コーラル BETA-10
菅野沖彦
スイングジャーナル 11月号(1968年10月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
コーラル音響といえば日本のオーディオ界では名門である。昔は福洋音響といって、スピーカー専門メーカーとしての信頼度は高かった。数々の名器はちょっと古いアマチュアならば記憶されているだろう。私自身、当時はずい分そのスピーカーのお世話になった。型番はもううろ覚えだが、たしかD650という61/2インチのスピーカーは大いに愛用した。810という8インチもあった。当時はインチでしか呼ばなかったが今でいう16センチ、20センチの全帯域スピーカーであった。トゥイーターもH1いうベスト・セラーがあった。福洋音響は当時のハイ・ファイ界のリーダーとして大いに気を吐いたメーカーだ。そして最近コーラル音響という社名に変更し住友系の強力な資本をバックに大きく雄飛しようという意気込みをもってステレオ綜合メーカーとしての姿勢を打ちだしてきている。
ところで、そのコーラル音響から新しく発売されたユニークなスピーカーがBETA10である。BETAシリーズとして8と10の2機種があるが、主力は10だ。まずユニットを一目見てその強烈なアマチュアイズムに溢れた容姿に目を見はる。白色のコーン紙。輝くデュフィーザー。レンガ色のフレーム。強力なマグネットは透明なプラスチック・カヴァーで被われている。これはマニアの気を惹かずにはおかないスタイリングで、キャラクターこそちがえ、例のグッドマンのAXIOM80のあのカッコよさに一脈通じるものを感じたのは私だけではあるまい。オーディオ製品のような人間の感覚の対象となるものについては、形も音のうちというものであり、この心理はマニアなら必らずといってよいほど持ち合わせている。形はどうでも音がよければという人もいるが、同時に、まったくその反対の人さえいる。コーラルがマニアの気質をよく心得て、細部にまで気をつかって、いかにも手にしたくなるようなスピーカーをつくったことは、今後のこの社の積極的な姿勢を感じさせるに充分で、事実、その後、かなり意欲的なデザインによるアンプも発売されている。
さて、BETA10の音はどうか。それを書く前に、スピーカーというもののあるべき姿にについて述べておかなければなるまい。音響機器中、スピーカーはもっとも定量的に動作状態をチェックしにくい変換器である。つまり、直接空気中に音を放射するものだけに、使われる空間の音響条件は決定的に影響をもたらす。装置半分、部屋半分ということがいわれるが、たしかに部屋が音におよぼす影響はきわめて大きい。これは録音の時のホールとマイクロフォンの関係に似ていて、電気工学と音響工学の接点であるだけにさまざまなファクターを内在しているわけだ。理論的な問題は別として、ある音源に対して最適なマイクロフォンを無数のマイクロフォンの中から選択して使っているというのが現状だが、これは、いかに問題が複雑で、理論や計算通りにいかないかを物語っているものであろう。マイクロフォンは使う人の感覚によって選ばれる。それに似たことがスピーカーにもいえる。スピーカーほど感覚的に選ばれる要素の強いものはない。それだけに選びそこなったら大変で、正しいバランスを逸脱することになる。BETA10こそは、まさにそうした危険性と大きな可能性を秘めたスピーカーであり、たとえてみれば暴れ馬である。その質はきわめて高く大きな可能性を秘めている。しかし、うっかり使うとたちまち蹴飛ばされる。使いこなしたらこれは大変魅力的なスピーカーだ。その点でも、これは完全に高級マニア向の製品で、これを使うには豊富な経験と知識、そしてよくなれた耳がいる。我と思わん方は挑戦する価値がある。こんなに生命感の強く漲ったタッチの鮮やかな音はそうざらにない。
フィデリティ・リサーチ FR-1MK2
菅野沖彦
スイングジャーナル 11月号(1968年10月発行)
「ベスト・セラー診断」より
フィデリティ・リサーチ、略してFRというイニシアルは、マニア間で高く評価されているカートリッジ、トーン・アームの専門メーカーである。FRは社長が技術者で、会社というよりは研究所といったほうがよいような性格のため、広く大衆的な商品はつくっていない。この社の代表製品はFR1と呼ばれるムービング・コイル型のカートリッジで、昨年MKIIという改良型を発表して現在に至っている。この欄でもカートリッジを何回かとりあげ、そのたびに、再生装置の音の入口を受持つ変換器としての重要性については詳細に解説されている。そして、現状では理想的なカートリッジというものの存在が理論的には成立しても、実際の商品となると困難だというのが偽らざる実状のようである。つまり、物理特性をみても、あらゆるカートリッジがあらゆるパターンを示し、皆それぞれ専門家によって慎重に開発され製作されているのに……と不思議になるくらいである。ましてやその音質、音色となるとまったく千差万別で、どれが本当の音かは判定不可能といってもよい。一般にはレコードの音がどうであるべきかという基準がない(そのレコードを作った人でさえ本当のそのレコードの音を知ることはむずかしい)から音質や音色を感覚的に受けとって嗜好性をもって優劣を判断することにならざるを得ないわけだ。
話は少々ややこしくなってしまったが、そういう具合で良いカートリッジというものを、いずれも水準以上の最高級品の中から見出すことはむずかしいのである。FR1MKIIは、そうした高級品の中でも、一段と明確に識別のできる良さをもっている。それは高音がよくでるとかどぎついとか、低音が豊かだとかいった、いわば外面的な特質ではなく強いて表現すれば透明な質といった本質的な音のクォリティにおいてである。FR1の時代には、かなり外面的な特長もそなえていて、音の色づけ、いわゆるカラリゼイションを感じさせるものがあった。それにもかかわらず質的なクォリティの良さを高く評価されていたのだが、MKIIとなってからは、そうしたカラリゼイションも一掃され本当に素直な本来のクォリティが現れてきた。そしてつけ加えておかなければならないことは、FRT3というトランスの存在についてである。ムービング・コイル型は出力インピーダンスが低く、一般のアンプのフォノ入力回路にはトランスかヘッド・アンプを介して接続しなければならない(例外もある)。これがMC型のハンディで、そのヘッド・アンプやトランスの性能が大きく問題とされた。せっかく、本来優れた変換器であるMC型が、その後のインピーダンス・マッチングや昇圧の段階で歪を増加させたのでは何にもならないからである。同社が最近発売したFRT3というトランスはコアーとコイルの巻き方に特別な設計と工夫のされた恐しく手のこんだもので、その歪の少なさは抜群である。FR1MKIIはFRT3のコンビをもってまったく清澄な音を聴かせてくれるようになった。FRT3は他のMC型カートリッジに使っても、はっきりその差のわかる歪の少ないもので、少々高価ではあるけれど、マニアならその価値は十分認められるであろう。
FR1MKIIの音は恐らくジャズ・ファンの中には物足りないと感じられる人もいるかもしれない。しかし、そう感じられる人は、きっと歪の多い、F特の暴れた装置の音で耳ができた人だと断言してもよいと思うのである。私が優秀だと思うカートリッジはすべて、そういう傾向をもっているが、それは決して何かが足りないのではなく、何も余計なものがないのである。そして、そうしたカートリッジから再生される音はやかましくはないけれど、迫力がないということは絶対にない。これはぜひ認識していただきたいことだ。

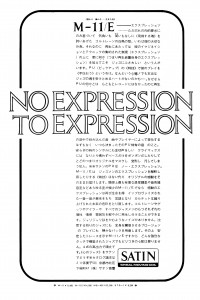
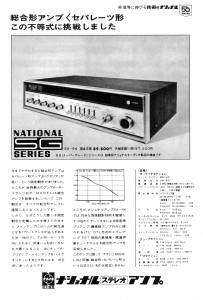










最近のコメント