井上卓也
ステレオサウンド別冊「世界のオーディオブランド172」(1996年11月発行)より
TA−ER1プリアンプは、独立電源部をもつバランス優先設計の超広帯域・超高SN比が特徴の、現代最先端のプリアンプだ。バランス入力端子と高平衡度バランスアンプを直結し、入力信号を直ちに差動合成する考え方は、ノイズ打ち消し効果が高く、通常120dBの信号伝送系SN比を170dBに高めているという。また、信号ロスを低減するため、入力インピーダンスは4MΩと異例に高い。加えて、不平衡入力の平衡アンプによる増幅、ホット/シールド切替を同時に行なうパラレルスイッチ機能、リモコン可能な真鍮削出し筐体収納のコンダクティヴプラスチック・アッテネーターの採用などが特徴。出力段はMOSダイレクトSEPP方式で、駆動能力の安定化と強化が特徴だ。
MM/MC対応フォノEQは、MC用に昇圧トランスを搭載。リモコンボリュウムは超音波セラミックモーター駆動で、停止時には制御系的にもメカニズム的にもすべて解除状態となる。
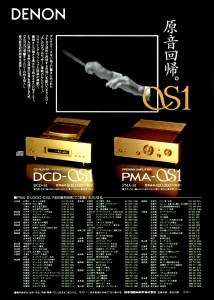




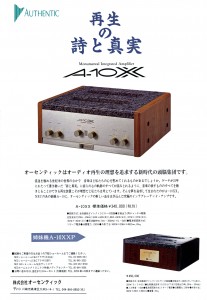

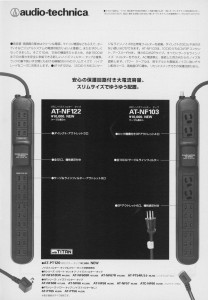

最近のコメント