SAECのトーンアームWE317の広告
(オーディオアクセサリー 27号掲載)
SAEC WE-317
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
オーレックス XR-Z90
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
RGR Model Four, Model Five, ニッティ・グリッティ Nitty Gritty I, Nitty Gritty III
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
シュアー V15 TypeV
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ソニー XL-MC1
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
デンオン SC-A3
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ヤマハ A-500, T-500, MC-4
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
コーラル X-III
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
サンスイ XR-Q5
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
クライン SK-2
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ディスクウォッシャー D4
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
エクセル PRO81MC, ES-10
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
テクニクス SL-P10
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ナガオカ SOUND PIERCE
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ドルビー DOLBY STEREO
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
BOSE 901SS
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ビクター Zero-100
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
BOSE 101MM
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
まるまた陶器 IGA
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
ヤマハ NS-200M, MUSIC GX
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
Lo-D DAD-1000
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
サンスイ SP-V70
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
フィリップス GP400III, GP401III, GP406III, GP412III, GP420III
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
JBL 4344, 4345
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
日立電線 OFC AUDIO CABLES
Posted by audio sharing
on 1982年11月21日
No comments
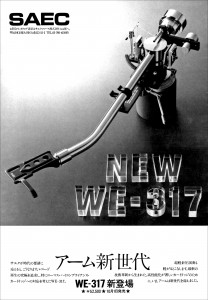



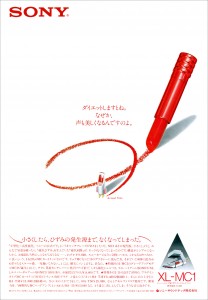
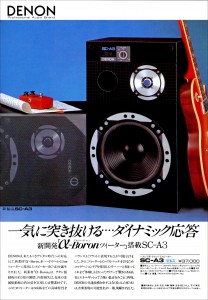

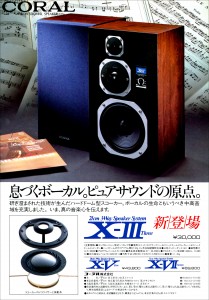

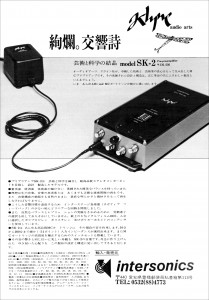

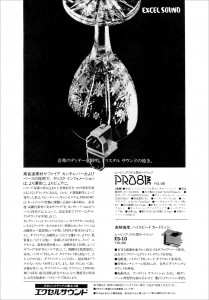

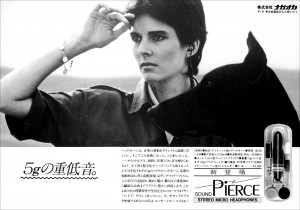



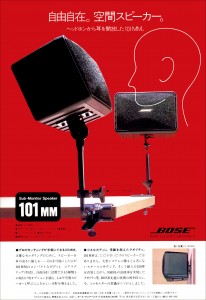

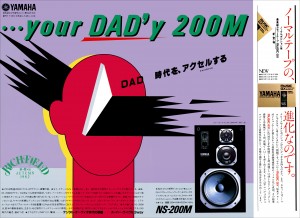



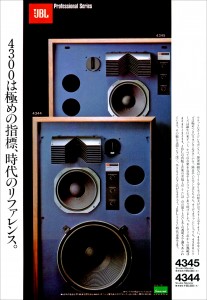

最近のコメント