オーレックスのスピーカーシステムSS220W、プリメインアンプSB220、チューナーST220、アナログプレーヤーSR220の広告
(オーディオ専科 1975年4月号掲載)
アルテック DIG MKII
サウンド STC-11, STO-140
マクセル UD-XL
アルテック DIG MKII
岩崎千明
スイングジャーナル 3月号(1975年2月発行)
「ベスト・バイ・コンポーネントとステレオ・システム紹介」より
アルテックのシステムは、本来、シアター・サウンドとしての名声があまりに大きいため、その家庭用システムの多数の傑作も名品も、どうも業務用にくらべると影がうすい。それは決してキャリアとしても他社に僅かたりともひけをとるどころではないのに。つまり、それだけ業務用音響システムのメーカーとしての「アルテック」の名が偉大なせいだろう。
だから、アルテックの名を知り、その製品に対して憧れを持つマニアの多くは、アルテックの大型システムを揃えることをもって、アルテック・ファンになることが多い。そうなればなるほど、ますますアルテックは若いファンにとって、雲の上の存在とならざるを得なかった。
「ディグ」の日本市場でのデビューと、その価値は、実はこの点にある。
「ディグ」のデビューによって、初めて日本のアルテック・ファンは、すくなくとも若い層は、自分の手近にアルテックを意識できるようになったといってもいい過ぎでない。
「ディグは」小さいにもかかわらず、安いのにかかわらず、まぎれもなく、アルテックの真髄を、そのままもっとも純粋な形で秘めている。アルテックの良さを凝縮した形で実現化したといった方が、よりはっきりする。
「アルテックの良さ」というのは、一体何なのであろうか。アルテックにあって、他にないもの、それは何か。
アルテックは、良いにつけ、悪いにつけ、シアター・サウンドのアルテックといわれる。シアター・サウンドというのは何か。映画産業に密着した米国ハイファイ再生のあり方は、どこに特点があるのだろうか。
もっとも端的にいえば、映画の主体は「会話」なのだ。映画にとって、音楽は欠くことができないし、実況音も、リアル感が大切だ。しかし、より以上に重要なのは、人の声をいかに生々しく、すべての聴衆に伝えるか、という点にかかっている、といえるのではなかろうか。
だから、アルテックのシステムは、すべて人の声、つまり中声域が他のあらゆるシステムよりも重要視され、大切にされる。それらは絶対的な要求なのだ。だからこそアルテックのシステムが、音楽において、中音域、メロディーライン、ソロ、つまりあらゆる音楽のジャンルにおいて、共通的にもっとも大切な中心的主成分の再生にこの上なく、威力を発揮するのだ。
音楽を作るのも、聴くのも、また人間であるから……。
「ディグ」の良さは、アルテックの真価を、この価格の中に収めた、という点にある。きわめて高能率なのは、アルテックのすべての劇場内システムと何等変らないし、そのサウンドの暖か味ある素直さ、しかも、ここぞというときの力強さ、迫力はこのクラスのスピーカー・システム中、随一といっても良かろう。
その上、システムとしての「ディグ」は、マークIIになってますます豪華さと貫禄とを大きくプラスした。
「ディグ」の使いやすさの大きな支えは、高能率にある。平均的ブックシェルフが谷くらべて3dB以上は楽に高い高能率特性は、逆にいえば、アンプの出力は半分でも、同じ迫力を得られることになる。システム全体として考えれば、総価格で50%も低くても、同じサウンドを得られるという点で、良さは2乗的に効いてくる。
つまり割安な上、質的な良さも要求したい、この頃の若い欲張りファンにとって、「ディグ」こそ、まさしくうってつけのシステムなのだ。
アンプのグレード・アップを考えるファンにとっても、「ディグ」はスピーカーにもう一度、視線をうながすことを教えてくれよう。パワーをより大きくすることよりも、システムをもうひとそろえ加えて、2重に楽しみながら、世界の一流ブランド「アルテック・オーナー」への望みもかなえてくれる夢。これは「ディグ」だけの魅力だ。
内容外観ともにガッツあるシステム
キミのシステムに偉大な道を拓く点、グレード・アップにおける「ディグ」の価値は大きいが、ここでは「ディグ」を中心とした組合せを考えてみよう。
アンプはコスト・パーフォーマンスの点で、今や、ナンバー・ワンといわれるパイオニアの新型SA8800だ。ハイ・パワーとはいわないが、まず家庭用としてこれ以上の必要のないパワーの威力、それをスッキリと素直なサウンドにまとめた傑作が8800だ。
パネルの豪華さという点でも、8800は文句ない。やや大型の、いや味なく、品の良ささえただようフロント・ルック。ズッシリと重量感あるたたずまい。
「ディグ」とも一脈相通ずる良さがSA8800に感じられるのは誰しも同じではなかろうか。
チューナーには、これもハイ・コスト・パーフォーマンスのかたまりのようなTX8800。
もし、キミにゆとりがあればSA8800の代りにひとランク上の、最新型8900もいい。チューナーは同クラスのTX8900でも、8800でも外観は大差ない。
プレイヤーとしては、同じパイオニアからおなじみ、PL1200もあることだが、今回はビクターの新型JL−B31を使ってみよう。ハウリングに強いのもいい。
カートリッジもこのプレイヤーにはひとまず優良品と
いえるものがついている。
デザイン的にも、また使用感も一段と向上したアームは、仲々の出来だ。このアームをより生かすカートリッジとして、スタントンを加えるのも楽しさをぐんと拡大してくれる。600EEあたりは価格・品質は抜群だ。
出ッとしてマニアライクなオープン・リールの新型、ソニーTC4660を推めようか。
オーディオテクニカ AT-15E
菅野沖彦
スイングジャーナル 3月号(1975年2月発行)
「ベスト・バイ・コンポーネントとステレオ・システム紹介」より
AT15Eはオーディオ・テクニカが同社のオリジナルであるVM型の発電機構を持ったカートリッジとして何回か改良を経て完成した最新製品である。この後に普及版の、AT14シリーズを発売しているが、同じ設計思想にもとずくものだ。AT15Eのよさは、VM型の同社のカートリッジに共通のきわめて明解な音像再現に加えて、豊かな陰影やニュアンスの再現力が得られたところにあると思う。VM型の振動発電系というのは.45/45方式の現在の2チャンネル・ステレオ・ディスクの溝の構造と同系のもので、互いに45度ずつ傾いた左右の壁の振動を、ちょうど、その振動を刻み込んだカッティング・ヘッドの左右のドライビング・コイルのポジションのようにV字型に2つ独立したマグネットが設けられて変換するというものだ。その構造が、いかに音質に結びついているかを明確に断言する自信はないが、今まで聴いてきた同社のVM型に共通した音質傾向が、先に述べたように、明解な音像再現とクリアーなセパレーションにあったといえる。曖昧さのないソリッドな音の再現は、時にドライで鋭角な印象を与えられ、音楽のニュアンスによっては不満を感じる場合があった。AT15Eでは、それが大きく変化して、適度な味わいと音のタッチの快さを感じるものになったのである。カートリッジは変換器として、ディスクの溝に刻まれた信号を忠実にとり出すことが、その大きな役目であるから、こういう音のカートリッジ……というような存在や、表現は本来おかしいというのは正論である。カートリッジが音を持つことは間違いだという理屈は正しいと思う。しかし、それはあくまで理屈の上であって.現実は大きく違う。全てのカートリッジは固有の音をもっている。カートリッジだけではない。全ての機械系をもつ変換器は固有の音を持っているのが現実である。そして、そこに楽しさや、喜びを感じることは間違いだといってみてもはじまらない。いい音、快い音は、まきに好ましいのであって、感覚に正邪はないのである。私はよく自分の部屋でカートリッジをテストするが、自分の作ったレコードでは、よくそのマスター・テープと聴きくらべることがある。変換器として、マスター・テープに近い音を良しとするのは当然だが、そういう比較は遠い昔にやめてしまった。つまり、近いといえば全てのカートリッジはマスター・テープに近いし.遠いといえば全て遠いのである。そして、その差の部分は千差万別で、そこにカートリッジの音として固有の音楽的魅力の有無が存在することのほうに大きな楽しみを見出してしまっている。
高品性かつ豊かな感性を持つジャズ・サウンドを再現
そんなわけで、このAT15Eに対する私の評価も、かなり柔軟な態度で音楽を聴いた上でのものであり、このところそうした味わいを聞かせてくれるカートリッジが国産でポツポツ出始めてきたことに喜びを感じているのである。ところで.このAT15Eを使って一式コンポーネントを組み合わせろという編集部の注文だが、小さなカートリッジ一個から、システムに発展させるというのは、少々こじつけがましいこともあり、本来、カートリッジは最後に決めて、なお、その上でも、いくつかのものを使い分けるという性格からすれば、この注文は少々無理があろうというものである。そこで、AT15Eの価格や実質性能、感覚的な満足度にバランスした装置を漠然と考えてみると、やはりかなり高級なシステムになるようだ。決して10〜20万の普及システムはイメージ・アップされてこない。AT15Eというのはそういうクラスのカートリッジなのだろうと改めて思った。ここに作ったシステムは、それでも、ギリギリ節約して作ったつもりのものである。プレイヤー・システムとしてはAT15Eのよさを発揮させるにはアームが重要。多くの普及、中級、時には高級システムまでが、トーンアームに問題があって、カートリッジの性能を充分に発揮しきれないのである。ひどい場合はトレース不能、ビリつきを生じて、一般にはカートリッジのせいにされている。
デンオンDP3700Fはこの点で安心して使える。シンプルだが精度のいいアームは高感度でしかも神経質ではない。私の好きなアームの一つだ。モーターはいうまでもなくDDの有名なもの。話が前後するが、AT15Eのシェルはあまりいただけない。形は気取っているし、作りもよいが、音は最高とはいえない。他のシェルに変えて、よりよい結果が得られた経験がある。シェルに対するカートリッジ本体の食いつきもよくないし、ダンピングが不充分だ。
アンプは同じデンオンのPMA700Zを使う。デンオンのプリメイン・アンプとしては既に定評のあったPMA700の改良でMKII的新製品である。音の透明度と実感がより確かな感触になった。よく練られた回路は高度な技術に支えられた音の品位のよさを感じさもる。味わいも豊かで、音楽の生命感がみなぎる。
スピーカーはダイヤトーンの新製品DS28Bだ。去年の暮に発売になったばかりだが、すでにかなりの台数がファンの手許に渡っているという。ダイヤトーンのスピーカー技術が、商品としてまとめの技術とよく結びついた完成度の高いもので、とにかくよく鳴る。AT15E、
ソニー TC-5550-2
菅野沖彦
スイングジャーナル 3月号(1975年2月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
音をとる楽しみは大きい。オーディオの世界は長い間、音を聴く世界であった。専門家だけが音をとることを許され、一般アマチュアは、それを聴く楽しみに限定されていた。レコード、ミュージック・テープ、そしでラジオというように、全て与えられたプログラム・ソースの再生に楽しみの世界があった。無論、そこには大きな趣味の世界があった。一般にいわれるように、必らずしも、聴くことは受身の行動だとはいい切れない。まして、自分で再生装置を構成して、同じプログラム・ソースからありとあらゆるバリエーションをもった音を再生するオーディオの楽しみは、再生とはいいながら、かなり創造性の強い趣味の世界だといえるのである。しかし、自分で録音をするということになると、その性格は一段と明確になってくる。写真の楽しみは撮影にあるし、写真というメカニズムは、素人が撮影するというプライバシーと共に今日のような大きな発展を見た。もし、写真が、オーディオのように、撮影済みのフィルムを再現するという範囲に限られていたら、とても現在のような発展は望めなかったであろう。そして、この音をとるということの楽しさは、録音機をうまく操ったり、S/Nのいい音を録音再生するというメカニックな楽しみと共に、自分の頭の中にイメージとしである音を具現化するところに、その真骨頂があるといってよいのである。実際には自分の外にある音を対象として、これを録音するのに違いないが、ただそこに音があるから録音するというのでは次元が低くすぎるし、楽しさも浅い。自分のイメージに合った対象を求め、それをイメージ通りに録音すること、あるいは思いがけない対象を発見して、それを瞬間的に自分のイメージに火花を散らせ、自分の感じた音として適確に把えること、時には強引に自身のイメージに合わせるべく音をつくり変えてしまうこと、こうした録音の楽しみこそ、まさに創造的な制作としての楽しみであり、その世界は大きく深いといえるであろう。
ところで、そうした目的には世の中の多くのテープレコーダーがあって、それぞれ目的と用途が設計思想の基本となっているが、ここにご紹介するソニーの新製品TC5550−2は、そうした高級な趣味層向けに、ハイ・クォリティ・サウンドで、サウンド・イメージをクリエイトするための道具として作られた高級デンスケである。同社でも、オープン・デンスケ、TypeIと称しているが、この分野での経験の豊富なソニーらしい立派なマシーンが登場して嬉しい。その昔、デンスケの呼称の元となった、ゼンマイ式の重いデンスケをかついで肩をこらせた筆者にとって、あらゆる点で、これは理想のマシーンだと思える程なのである。この種の機械の最も重要なポイントはパワー・サプライだが、これは4電源方式という便利なもので、単一乾電池8個、充電式バッテリー、カー・バッテリー、AC100Vと万全である。まず、どこへ行こうと電源に悩むということはない。メカニズムは少々繁雑だが、それだけ機能は豊富である。筆者としてはもっとシンプルなもののほうが好ましいが、メカニズムの好きな人にはその欲求が充分満たされるであろう。デザイン、仕上げにはマニア好みの格好よさが溢れているのである。トランスポートの要めはがっしりとダイカストで固め、19cm/sec、9・5cm/secの2トラック・2スピードの録音特性は素晴らしい。音楽録音にも全く心配なく使えるほどだから、野外の自然音などは完璧。あまりよいので家庭用のデッキとしても使いたくなるほどでなぜ7号リールがかけられるようにしなかったのだろうなどと、少々見当はずれの欲が出てくるほどなのである。ヘッド構成は3ヘッドの独立式、駆動モーターはDCサーボのワン・モーター、44×94mmのダ円型スピーカーがモニターとしてついている。マイクの入力はロー・インピーダンスで−72dBの感度を持つ本格的なプロ仕様。ラインは勿論、100Ω以上で−22dBである。音質は明解で安定し、バイアス、イコライザー共に3段切換で、テープに対する適応性も広く、高性能テープも使いこなせる。重量は6・8kgと決して軽くはないが、この内容としてはよく押えられている。19cm/secは勿論、9・5cm/secの音質のよさは特に印象的で、基本性能をかっしりと押えたメカニズムとエレクトロニクスのよさを感じた。
JBL LE175DLH
岩崎千明
ステレオ別冊「ステレオのすべて ’75」(1974年冬発行)
「オーディオ製品紹介 1975」より
JBLのオリジナル、もっとも初期からシステムとして構成されたその名も001。2ウェイの高音用として指定されたのが175DLH。ウーファーは130A、4cm径の金属ダイアフラムのユニットと約20cmのホーンはその前面に設けられたパンチングメタルを5枚、すき間をあけて重ねて作られた音響拡散器とによって、開口部における音響反射がおさえられるとともに90度の広角に高音エネルギーを拡散して、家庭用としてこの上なく理想的な高音輻射を実現している。パンチングメタルの間につめられたフェルト状吸音材によりJBLの他の高音用よりやや繊細なサウンドでこれが好みを左右する。
JBL 075
岩崎千明
ステレオ別冊「ステレオのすべて ’75」(1974年冬発行)
「オーディオ製品紹介 1975」より
JBLの初期から高名とどろくホーン型高音用が075。リングラジェーターと称しホーンのスロートでごく狭くした上でドーナツ状にして拡散を図ったが、設計の意図と違ってリング状のホーンの開口は、全体として約10cmのホーン開口と同じことになってしまって、せっかく鮮鋭な高エネルギーながら拡散特性はあまり良いとはいえず、高音用としての大きな利点を損なったともいえる。しかし73年になって、プロ用にこの075の拡散特性を大改良した角型開口の2405が発売され、さらにコンシューマー用としても、まったく同じ構造の077なる名器の075改良型がでることになるJBLブランドにふさわしい製品だ。
アルテック 604E
岩崎千明
ステレオ別冊「ステレオのすべて ’75」(1974年冬発行)
「オーディオ製品紹介 1975」より
アルテックのスピーカーを代表するモニター用15インチ(38cm)2ウェイ型。当時アルテックにいたミスターJ・B・ランシングが1946年に発売したホーン型高音用を大型ウーファーと同軸上に組み合わせた2ウェイ・スピーカーを、具体化して製品としたのがアルテックの600シリーズで、601の12インチ型と603簡易型及び604の15インチがある。38cmウーファーは強力型515と同じ。そのウーファーを貫通して高音用ユニットのマグネットを貫通して高音用ホーンが設けられており、外観から想像できぬほどのホーン有効長を得た本格的な2ウェイ。力に満ちた迫力と、比類ないステレオ定位、音像の確かさは秀逸。
アルテック 605B
岩崎千明
ステレオ別冊「ステレオのすべて ’75」(1974年冬発行)
「オーディオ製品紹介 1975」より
業務用としてスタジオでの監視用モニターにもっとも広く活躍する604Eを基とし、家庭用ハイファイ用にリファインされたのが605B。ウーファーが604Eの515同等に対し416A同等となっている展が最大の相違点で外観上は604Eのやや高域に偏し引締った音に対し、格段に優れてフラットな特性と聴きやすいサウンドを得ており、類まれな高品質の2ウェイとなった。製品としては604と同時期から存在するが604のかげに日本ではその良さを充分に認識されることがなかったのは痛恨事であったが、最近「クレッセンド」が認められつつある。
JBL D130
岩崎千明
ステレオ別冊「ステレオのすべて ’75」(1974年冬発行)
「オーディオ製品紹介 1975」より
JBLスピーカーの優秀性を端的に代表するユニットが38cmフルレンジD130。比類ない高エネルギーと能率の高さが、今日ではおろそかにされがちな音響変換器の本来持たねばならぬ素質の良さを、強烈な形で使う者に知らせてくれる。8000Hz上の高域はかなり低減するが帯域内でのバランスの良さ、特に200ないし80Hzのいわゆる中音域の充実感はこれを知ると手放せなくなろう。このユニットが日本のファンに好評な理由は、まずフルレンジとして高音をやや強めた状態で愛用され、あとから高音用ユニットを追加することにより、JBLオリジナルに近い2ウェイ・システムに高められるという利点にある。
アルテック 419-8B
岩崎千明
ステレオ別冊「ステレオのすべて ’75」(1974年冬発行)
「オーディオ製品紹介 1975」より
JBLの大型フルレンジの38cmがD130なら、アルテックの38cmは420A、30cmが419得非である。JBLのシングルコーンに対してアルテックは2つのコーンをつないだ形の変形ダブルコーンで、倍フレックスと呼ばれる。バイBiは2つの意味。センターのアルミドームが高域ラジエーターとして有効なのはJBLと似ている。再生音域が充分広いとはいえぬがややソフトな耳当りの良い朗々たるサウンド。はっきりして定位の優れたステレオ感。いかなる用い方にも応じ得る素質のよさに裏付けされたハイファイ全般への広範な酔うとに広く推められるべき極上のコストパフォーマンスの優秀ユニットだ。
ダイヤトーン DS-28B
岩崎千明
スイングジャーナル 12月号(1974年11月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
この秋の新製品の中でも文句なしの出来と認められているのが、このダイヤトーンの新型システムDS28Bだ。
ダイヤトーンは、言うまでもなく、初心者にとっては名作といわれる16センチ・フルレンジ型ユニットP610のブランドとして良く知られ、オーディオ・ファンとしてそろそろ判ってくると、これまた日本の名作スピーカーDS251という名のブックシェルフ・スピーカーのブランド名として忘れられない名前となっており、さらにマニア度が昂じてくると、今度はNHKで活躍し本格派にとって目標とされるモニター・スピーカー2S305のメーカー名として脳に叩き込まれる。
つまり、オーディオ・ファンのあらゆる層に対して、ほんの、しかもオーディオという事象が日本で始まった時から、僅かでも絶えることなく、偉大なるウェイトと輝きをもってファンの上に聳え続けてきた。こうした事実は、三菱電機郡山音響部というより、ダイヤトーン・スピーカーの実力の高さを示す以外なにものでもないのだが、メーカーにとってはかえって不幸となるべき要素も胎んでいるのである。3つのピークが永い年月を乗り越えてきたので、あまりにも大きく裾が広く、まさに壮大というほどの輝やかしいものだから、その他の峰はすべて霞んで、いかに光ろうと、目立つことがないからだ。
かつてDS301という画期的な名作ブックシェルフがあった。決して影の薄い商品ではないし、現在でも、そのマイナー・チェンジ版がDS303として確固たる座にあり、海外誌でしばしばこのうえなく誉め讃えられてきた。にもかかわらず、DS301やDS303は果してDS251ほどの人気を持っているかというと、答えるまでもなく、P610と、251と、305の輝きの下で霞んでしまっているとしか形容できないのである。まだある。DS36Bというフロア型ともいえそうな大型ブックシェルフ・スピーカー・システムが、一部のファンの間で熱愛されているが、これまたDS251の前には商品としてすっかり薄れてしまう。つまり余りに3つの印象は大きく強烈なのである。そうした内側の問題ともいえそうな3つのピークは今秋遂に打破られた。そう言っても言い過ぎではなかろう。それは時間が証明するだろう。
かくて、DS251以来の、それ以上の出来をささやかれ、認められつつあるこのDS28Bは、今後のダイヤトーンの最も主力たるスピーカー・システムとなるであろうことは、まず間違いない。というのは、今やコンポーネントの一環としての、市販スピーカーは、ひとつの価格水準として、ほぼ4万前後がオーディオ・ファンの最も多くから認められる最大公約数といえるからである。もっとも、そうした最近の状況をよくわきまえた上で企画されたのがDS28Bであり、その成功を獲得するための、あらゆる条件を究めつくした結果と言うこともできる。
28Bは一見したところ、従来のダイヤトーン・スピーカーとはまったく異って、現代的なセンスに溢れる。まるで海外製品のようだ。更に前面グリルをはずしても、それが言える。
あるいは全世界の製品中、最も秀れた外観的デザインと云われる米国JBLのブックシェルフと間違えるほどに、フィーリングが相似であるのは今までの三菱というメーか−を知るものにとり、その製品の武骨な外観を見てきたものにとって意外なほどだ。その次に音に触れると、それは感嘆に変わるだろう。なんと鮮明な、なんと壮麗で豪華なサウンドであろう。そこにはブックシェルフ型というイメージはまったくない。もっと10倍も大きなシステムからのみ得られる、深々とした重低域の迫力と、歪を極端に抑えた静けきと、生命力の躍動する生き生きとした力とが、まったく見事に融合して湛えられているのを知るのである。音のバランスは確かにDS251と相通ずるものがあるが、その帯域の広さと音のゆとりとの点で一桁も二桁も高い水準にあり、DS251たりといえども28Bとは比べむべくもないほどだ。音像の確かさと広いステレオ感などとやかく言うこともあるまい。必ずや28Bは251を軽く凌ぐ人気と実績をものにするだろうから。
JBL L16 Decade
菅野沖彦
スイングジャーナル 12月号(1974年11月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
JBLがL26ディケイドという普及型のスピーカー・システムを出したのは、そう古い記憶ではない。今は値上りしてしまったが、発売当初は7万円ぐらいで買えたので、大きな人気を呼んだ。たしかこの欄でも私が採I)上げたと思うが、普及型ながら、まぎれもないJBLのクォリティをもった優れたスピーカーであった。アメリカでも好評であったらしく、今度、このディケイド・シリーズを上下に拡大し、L16、L36というニュー・フェイスが登場したのである。このシリーズの開発は、私の知る限りでも、かなり長い時間をかけており、ロスのカシタス・アヴェニューにあるJBL本社の試聴室には、そのプロト・タイプが前から置いてあった。昨年の春、同社を訪れた時にも、それを聴かせてもらって、その発売を楽しみにしていたものである。この1〜2年、小型ブックシェルフ・スピーカー・システムはヨーロッパ・メーカーから続々と優れたものが発売され、世界中で好評を得たというバック・グラウンドが、JBLにも、ディケイド・シリーズの拡大を考えさせる刺戟になったことは疑いない。ヘコー、ブラウンなどの製品が、同社の試聴室にあって、L16のプロト・タイプとの比較試聴に使われていたことからも、こうした事情がわかろうというものだ。
この秋になって、ようやく輸入発売されたL16を試聴してみて、さすがにJBL! という感概を改めてもったほど、この小さな〝ジャイアンツ〟は私を魅了してしまったのである。27×49×26cmという小さなエンクロージャーに収められたこの2ウェイのコーン・スピーカー・システムの音は、とても外観から想像できないスケールの大きさと、本格的なJBLクォリティーを備えているものであって、JBL製品の成功作といってよいと思う。JBLといえども、稀れには失敗作と思える製品を発売してしまうこともあるが、そのほとんどは、最高級のJBLシステムに通じる音の質感をもっていることは見事というほかはない。ほとんどのスピーカー・メーカーからの製品は、同シリーズといえども、全く異質な音を出してみたり、ましてや、発売時期に2〜3年と隔りのあるものや、使用ユニットやエンクロージャーのサイズが違ってしまえば同質のサウンドを聴かせてくれるものはないといってよい。スピーカーというものの赦しさをそのたびに感じさせられるものである。しかし、JBLは、コーンの2ウェイからホーンを使った3ウェイに至る多くのバリエーションが見事に同質のサウンドで貫かれているということは驚異といってよいくらいである。明るく、解像力に富み、屈託のない鳴り方は音楽の生命感や現実感を見事に浮彫りにして聞かせてくれる。濁りのないシャープな音は、時にあまりにも鋭利で使いこなしの難しさに通じるが、使用者が、自分の理想音を得る場合の素材としては、これほど優れた正確なものはないと思えるのが、私のJBL観である。可能性というものをこれほど強く感じさせてくれるスピーカーは他にはない。ほとんどの所で聞くJBLスピーカーの音は、その可能性を発揮していないといってもよいので、一部ではJBLスピーカーが誤解されているようにも思えるのである。
さて、このL16は、20cm口径のウーハーと3・6cm口径のコーン・ツイーターの2ウェイで、ウーハーは新設計のものだが.ツイーターはL26、L36、L100、4311モニターに共通のダイレクト・ラジエーターである。エンクロージャーはバスレフ型だ。JBLのユニット群は同社がスピーカー・ユニット製造の長年の歴史から得た貴重なノーハウと、確固たる信念にもとずいた、磁気回路、振動系の設計製造法によっているため、新しいシステムを出した時にも、全く別物のようなサウンドにならないといってよいだろう。それでもなお、ユニットの組合せ、エンクロージャーの違いによって、そのまとまりに出来、不出来が生じることもあるのだから、スピーカーというものは難しい。L16は、前にも書いたように、きわめて幸運?なまとまりが得られたシステムとなった。許容入力は連続で35W、音庄レベルは75dB(入力1Vで4・57mに置ける測定値)だが、ドライブするアンプは、50W×2ぐらいのパワーは欲しい。こんな小さなシステムでありながら、プリ・アンプやパワー・アンプのクォリティーを完全に識別させるほどの実力をもっているからである。
オンキョー E-212A
岩崎千明
スイングジャーナル 11月号(1974年10月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
「オンキョーの新製品」といわれるまでは、それを知らないものはてっきり米国製新型システムかと思い込むだろう。また、このオンキョーのE212Aを見知っているのがJBL・L16に接すればオンキョー製と間違えるに違いない。それほどまでよく似た外観だが、どちらが先か、 といわれると指折り数えて月日を改めたくなるほどに同時期の新製品なのだから、お互いに真似たわけではないだろうし、おそらく偶然の一致なのだろう。
しかし、オンキョーE212Aは、戦後いち早くスタートした同社のスピーカー専門メーカーとしての永いキャリアにおいて、おそらく始めて海外製品を意識して企画され、作られたスピーカー・システムなのではなかろうか。
この数年、日本のオーデイオ市場における海外製スピーカーの人気はすっかり普及化し定着した。その背景からヒット商品のデビューのあり方も国産品なみで、爆発的な人気と売り上げは、国内のメーカーのライバルとして対象にならないわけがないだろうから、オンキョーのこうした意図は当然かも知れぬ。
しかし似ているのはサウンドと外観だけであって、決して内容や機構ではない。日本製品の一般的あり方を考えると、これは讃えられるべきといえる。ヒット商品が出れば、あらゆる点においてそれに追随する、という製品が多いのだから。
E212Aのフロント・グリルの内側には2本の16センチ・コーン型ユニットと1本の逆ドーム型トゥイーターとが収められ、一見、ヨーロッパ製ブックシェルフによくみられる並列に接がれた2ウーファーを思わせるが、実は単純な並列駆動ではなくて、一本は高音ユニットとクロスオーバーさせて、中音以下を受け持ち、もう1本だけが低音域のみに対して動作するという、つまり、エネルギーの不足になりやすい低域においてのみ、2ウーファーとして動作し、中域では2本ではなく1本のみが動作するように配慮されている。これは2つの振動板から放射される音響エネルギーが、完全なるピストン・モーションの範囲にあれば理論的にもスッキリとした音響エネルギーとして受けとれるが、その振動板が分割振動をし始める周波数以上においては、2つの振動板による相互の影響が幅射エネルギーとしての音源のあり方を決して純粋な形にしておくわけがない。初歩的ファンが、単純に受け入れてしまう多数の小型スピーカーを無定見に並べて、並列接続して分割振動の範囲までも動作させるシステムが持つ位相歪に起因する音他の定位のぼける欠点を、このシステムは知っており、2つのユニットに対してすら留意している、ということになるわけだ。
こうした今までのシステムでは見逃されがちの、弱点に対して細心の注意を注いだ結果が、2つのユニットを用いながら、そのクロスオーバーを変えてトゥイーターに近いひとつは中音域から低域まで、もうひとつの下のユニットは、低音用としているわけで、いうなれば3ユニットの3ウェイ的な変り型2ウェイ、というややこしい動作をしているわけだ。しかもこうした大口径ウーファーによらぬ2ウーファーの大きな特長でもある重苦しさの少しもない軽やかで、迫力ある低音は失われることがないのは無論だ。
実は、このE212Aの発売直後に、すでに好評を得ていて、オンキョーのブックシェルフ中の傑作といわれているE313Aと並べて試聴する機会があった。E313Aの重量感もありながら、さわやかさを失なうことのない中音から低域にかけての迫力に対して、E212Aはなんと少しもひけをとらなかったのには驚きを感じたのである。価格において50%安く、大きさにしてふたまわりは小さいといえるこのE212Aが、ふかぶかとした低音をスッキリと出してくれた。
むろん、16センチの中音は、低音でゆすられるのではないかという心配をよそに、力強く、シャープな立上りと明快なサウンド・クォリティーで、いつもオンキョーのシステムに対して感じられる品の良さの伴った充実ぶりで、心おきなく楽しめるし、音域ののびもまた十分。つまり内外含めてライバル多きこのクラスの中にあって実感度の高いシステムと断言できよう。
トリオ Supreme 700C, Supreme 700M
菅野沖彦
スイングジャーナル 10月号(1974年9月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
トリオが久しぶりに〝サプリーム〟という名のもとに高級アンプを発売した。かつて、マルチ・チャンネル・アンプ・システムが流行した当初、総合マルチ・アンプとでもいえる3チャンネル・アンプを発売した時からこの〝サプリーム〟(本当はシェープリームと発音すべきだが)という名前が生れたと記憶するが、その時点での同社の最高級技術とノー・ハウを集中して作られる製品にだけ使うことになっているようだ。今回の製品はモデル700Cプリ・アンプと700Mパワー・アンプの2機である。最高級アンプを目指すものだけあって、同社のこの製品にかけた努力は並々なものではなかったらしい。実際の製品のデビューが、他社のこのクラスのものより遅れた理由も、慎重な開発のためだろう。
たしかに、現在の日本のオーディオ界は高級アンプに大きな成果をあげつつある。この一年間に各社から発売されたハイ・パワー・アンプ、それにマッチした高級プリ・アンプはそれぞれ自社の持てる力をフルに発揮した力作ばかりといってよかろう。それぞれが優れた物理特性を誇る高水準のもので平均的にいっても外国製の同クラス・アンプを凌駕するといってよい。ただし、デザインのオリジナリティ、音の風格の面ではそうとばかりはいい切れないが、音の純度の高さは最近の国産アンプの大きな特長だと感じている。私の装置は3ウェイのマルチ・アンプだが、その各帯域のパワー・アンプとして優れた性能を発揮してくれるのはむしろ国産の優秀アンプであるが、全帯域として使うと、不思議と外国アンプの魅力が生きてくるという事実を痛感している。魅力とか音楽性というあいまいな表現は、全て物理的にはネガティヴな要因、つまり、歪に起因するものという見方があるが、心のせまい思考である。それが本当に歪の存在であるかどうかも解らぬくせに、技術領域でだけに思考の輪を限り、現実の音のよさを理解もしないで、頭から否定するという貧しさである。そういう考え方の人間に限って全体を把えることなしに、部分だけに気をとられ、そこさえよくなれば全体もよくなったと錯覚する。エレクトロニクスの進歩とオーディオのトータルな世界でのバランスにおいて、未だ混沌とした情勢にある中で、各社のアンプが、それぞれに実際に鳴らしてみると、ちがう音がするという事実はきわめて当り前の結果だという気がするのである。
このトリオの700C、700Mも、こうした現状を反映したアンプであって、特に、700Cプリ・アンプの音の強烈な個性は好き嫌いがはっきり分れる性質のものだと思う。私の手許にいくつかあるプリ・アンプ、マランツ7T、マッキントッシュC28、JBL・SG520、パイオニアC3、ソニーTAE8450、テクニクスSU9600など、一つとして同じ音のするプリ・アンプはない。そして、しかもそれらは、組み合わせるパワー・アンプとスピーカーで、さらに千変万化するという有様である。700Cを私の常用システムに繋いで鳴らした時の魅力はここでは書くまい。何故ならば、それはあまりにも個人的なものだから。ここではあくまで、700Mとの組合せでアルテックのA7をSJ試聴室で鳴らした感想に止める。音は大らかで底抜けに明るく、ウワーと前面に躍り出た。屈託のない表現の大きさは実にユニークで戸惑いを覚える程である。内向的で悪くいえば陰湿な、じめじめしたデリカシーに伏目がちに涙する日本人的気質とは程遠いのである。私自身、味や女性への好みもマルチブルで自分でも自分が解らなくなるほど浮気っぽいから、音の好みも相当多岐にわたる。700Cの持っている充実した明るい大らかな音は大変魅力的だった。細かい特性はカタログを見ていただければわかるから、ここではふれる必要もあるまいが、各種コントロール機能もよく練られ、これぞプリ・アンプといったパネル・デザインもオリジナリティこそ高く評価は出来ないが、仕上げの高さ、感触のよさなど、高級感に溢れている。700Mパワー・アンプは、170W×2の大出力らしい余裕と、中低音の豊潤さは圧倒的だ。低音の量感がするだけではなく、その質が弾力性に富んでいる。平板な量感をもつ低音ではなく、丸いのである。電源の基本特性もぜいたくに設計されている。出力段は3段ダーリントン接続コンプリメンタリー・トリプル・プッシュである。最近の大出力アンプはパワーの余裕と、よくコントロールされた低歪率のために、音質の向上は著しい。しかし、大出力アンプの共通の欠点としての残留ノイズ・レベルの高さがあげられる。高能率のスピーカーで深夜ひっそりとした中での使用は大変気になるものだ。この点、この700Mは、最近、私が接したハイパワー・アンプの中では格段に残留ノイズ・レベルが低いことを特筆しておこう。ロー・レベル再生の透明度にも影響をもたらすものだけに、残留ノイズは、全てのアンプがこの程度に押えられなければ家庭用のハイ・ファイ・アンプとはいえないのである。700C、700Mはトリオらしい強い主張をもった製品であり、手応えのある堂々とした高級機であった。
アドヴェント ADVENT2
岩崎千明
スイングジャーナル 10月号(1974年9月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
白い小さな現代的な姿のシステムが、広いけれど数多いパーツがその空間の多くを占めるSJ試聴室の正面にちょこんと据えられると、ひどくスッキリと目立つ。ただ、左右に2本置かれているだけでたいへんしゃれたたたずまいである。
白いシステムの、後側に嫌み上げられたたくさんのシステムが、やたらに大きく感じられ、ぶっきらぼうなくらいに実用むきだしの体裁にみえる。
アドヴェントIIの四隅をほんの少々丸みを持たせた小さな箱がこの上なくまっ白であるのは、それが塗装ではなくプラスチックのためだ。プラスチックの箱というと、これはまたただプラスチックというだけで価値も見映えもおそまつな感じを受けてしまいがちなものだが、このアドヴェントIIにおいては、プラスチックといわなければそう気がつかないほどに品のある仕上げだ。まっ白なので、塗装でないとすれば素材の色だろうし、その素材としては常識的に塩化ビニール・プラスチックにきまっているのに、そう見えないのは、その表面がきめ細かい艶消し仕上げだからだ。もっともそれだけではなく、板との2重張りの箱は工作上も現代工芸的イメージだ。さらにそれを決定的にするのは、この小さな箱に収められた20cmウーファーとドーム型の2ウェイ・システムのサウンドであろう。
とてもこの大きさが信じられない程の太くゆったりした低音の響き、それとバランスよく釣合って鮮かに輝くような高音のタッチだ。
この快く豊かなエネルギーが、聴き手をつつむとき、それは姿態通りの現代的なセンスに満ちたシステム。単にスマートなデザインというのではなく、しゃれた雰囲気がぴったりの小型システムなのだ。
この一見、いかにも現代ヨーロッパ調のイキなシステムは、かくのごとく、サウンドの上でも、西独製の新進ブランドのスピーカー・システムを思わせるにもかかわらず、なんと米国製のスピーカーなのである。
アドヴェントは、すでにこの4年間米国の新しいブックシェルフ・システムの名として、コンシュマー・レポート誌において絶賛され、BestBuy(最高のお買い物)に選ばれて以来先輩格のARやKLHに並ぶロング・ベストセラーを続けているシステムだ。このアドヴェントはARやKLH同様、米国スピーカーの中にあって、生粋のイースト・コースト派で、いわゆる品がよくて万人向けの優等生的サウンドのシステムだが、その中でもアドヴェントは高音に鮮かさを加えている点と、価格的にもっとも安い点で、いかにも現代的だ。
アドヴェントには「レギュラー・アドヴェント」と「スモーラー・アドヴェント」のただ2機種のみしかなかったが、この新しいシステムが「アドヴェントII(ジュニア)」として登場してからはまだ間もない。つまり、アドヴェント・システム中の新顔なのだ。
この数少ない製品から「品種をやたら増やすことのないメーカーの姿勢」が感じられるが、アドヴェントIIは、それなりの理由があって加えられた新製品だ。
それなりの理由とはなにか。それをこの現代的デザインの白く小さな姿が物語り、コンチネンタル・サウンドを思わすこの響きがそれを示そう。
アドヴェントIIは、明らかに従来のアドヴェントの、今までの米国製スピーカーから突き抜けた企画で創られた「新しいシステム」なのである。
このシステムが、西独でもなければ、英国でもないし、北欧でもなくアメリカから生れた、という点に、大きな意義があるというのである。
アドヴェントはすでに、米国市場において大成功を収めているが、アドヴェントIIのデビューによって、アドヴェントの新たなるファンが大いに増えることは間違いなかろう。アドヴェントが狙うファンは、ヨーロッパ製システムを予定していた、センスフルな若者なのだから。それはちょうど、クルマでいえば、ワーゲンを買おうとしていた若者ともいえるし、ありきたりのアメリカの良識にあき足らない感覚を満たすに違いない。そして、日本市場でもまったく同じ意味でアドヴェントIIは、大いにファンを獲得するに違いない。アメリカと違うのは、このアドヴェントIIによって日本市場で初めてアドヴェントが本格的に腰を据えるだろうという点である。
エレクトロボイス SP8
岩崎千明
ステレオサウンド 32号(1974年9月発行)
「AUDIO MY HANIECRAFT C・Wホーンシステムの制作と試聴記(下)」より
エレクトロボイスのユニットの中でも、もっとも小さな8インチ口径のフルレンジユニットで、価格もJBL♯2110とほぼ匹敵する。
同社の数あるユニットの中でも、非常に使い易いということ、いわゆるエネルギー感の強い、音量の充実感がある、という良さが感じられる。このユニットの場合、いわゆるモノーラル時代の基準にしては非常にレンジの広いものだったのだが、今日それを聴いてみると、ハイエンドにおいてそれほどレンジが広いというわけではない。ただハイエンドにおける僅かな強調だと知らされるのだが、それによって非常にバランスが良い印象だ。
もともとこのユニットは、バスレフ型などのエンクロージュアを使うべきだろうが、現在のブックシェルフシステムと較べると、それはバスレフ型にしろ密閉型にしろかなり大型であるはずである。このユニットのもうひとつの特徴は、エッジにあり、今日におけるフォームラバーを用いたフリーエッジとも違うし、コルゲーション・エッジのひとつだが、それにしてはf0がかなり低くなるべき構造を持っている。それが、このバックロードホーンにより、的確なロードがかかってコーン自体バタつきという心配がなくなったことがあげられる。低音を上げてみても、コーンの動きをみると無理な振動をしていない。つまり、SP8Bの良さは、音量を上げても充分に確認でき得たそうしたことからも高域から低域までレンジも広く、バランスの良さも充分だ。あるいはJBL♯2115よりもかえってSP8美非の方が潤いのある音という感じを受け、一般の音楽ファンにはより多くの良さを認めるのではないだろうか。2115のような、フラットレスポンスというのではなくて、音楽的バランスという点では大変嬉しい。加えてエネルギー感が強く、ユニットの出し得る低音をホーンロードによってさらに強調している。特にJBL♯2110のようにやや中低域に豊かさがあるというわけでなく、しかも2110と同じような、高い音量を期待できる。つまり広い部屋でガンガン鳴らすことができ、その状態でもバランスが非常に良く、低音の力強さとアタックの見事さが得られる。これは、やはりユニット自体の基本条件、たとえば、マグネット中心の駆動系と振動系の関連性、コルゲーション・エッジによって得られたバランスの良い帯域、それぞれがバックロードホーンによって効果を高めているといえよう。
実は、このSP8B自体の良さをバックロードホーンによって僕自身も大いに見直した訳で、このユニットはこんなに良かったかなと改めて知ったのだった。このユニットの場合、クラシック、特にオーケストラものを聴いても豊かさもあり、しかも音の分解能も適当にあり、バロックを聴けばその繊細感もでる。中音のあざやかさもうるおいもたっぷり感じられる。ロックを聴けば、フェンダーベースの持つ力に満ちた低音の響きなども充分出してくれる。つまり万能な、誰にでも奨められるユニットだ。ただここに得られた音をさらに良くしようということは難しい。というのは、このシステムはSP8Bによって完成されてしまったといえ、トゥイーターを加えたからさらに良くなることはまず考えない方がよい。
アルテック 403A
岩崎千明
ステレオサウンド 32号(1974年9月発行)
「AUDIO MY HANIECRAFT C・Wホーンシステムの制作と試聴記(下)」より
アルテックの中でも特に手頃な価格のこのユニットは、ここに集められたユニットの中でも一番安い、ユニットの後にトランスをつけるための台座がついていることからも、本気になってハイファイを志向する人からは敬遠されがちなユニットで、多分、多用途に向けて作られたスピーカーということができる。
アルテックの他のスピーカーにもいえる良さ、大きなメリットとは、やはりうまいバランスにある。このユニットでもそれは充分感じられるのだが、そのうまいバランスをバックロードホーンによってさらに拡大しようと期待すべきかどうか、それに先だって感じさせてしまう。
ただ、ここでつかっているユニットは合計4本、ユニットだけで約二万円を費やしてしまうのだが、アルテックのブランドが持つ信頼感やあこがれう満たすことを考えると、この価格は驚異的に安いわけだ。その意味では、最初にエンクロージュアを作って、なにはともあれという折、手頃なユニットだといえよう。
このユニットの外観と価格からは、そう多くのものを期待する人はおそらく少ないに違いない。ところが実際にエンクロージュアに取付けて聴くと、一瞬うなってしまう。やはりアルテックというのは、音楽を非常によく知り、しかも中音の量感が──量感という言葉からはどうしても低音のイメージを持ってしまうのだが、この場合には中音のそれが──よく出る。これはJBLの♯2110などと相通じる量感ともいえようか。ただ、力という点でアルテックの方に、もう少し力強さが欲しい。力強さとは、たとえば打楽器の立上り、各楽器の分離、コーラスの分離などについて、もう少し力があったらもっと分離が良くなったのではないか。あるいは、コーラスのハーモニーが良く出るが、そのコーラスの一人一人の唄を細かく聴こうとすると、それらがぼやかされる物足りなさを感じてしまう。つまり、音の力強さとは、全体の力を意味するのではなく、音のひとつひとつに対する立上りの良さで発揮される。そういった意味での力強さが欲しい。特に中音域に対して、高域は、このユニット自体が持つ好ましい、いわゆる〝ウェル・バランス〟が2個のユニットを使用したことにより、かなり弱められてしまったようだ。聴感上、8kHzから10kHzぐらいまでやや強めながらダラ下りになる周波数特性をもつこのユニットを2個使ったことで、音のバランスはさらに低い方に移ってしまって、高域が欠如してしまったといったほうがぴったりする。低域においては確実にエネルギーの増強が感じられる。これはユニットをマルチ化した場合での周波数特性、指向特性、出力エネルギー特性といったものが影響したのだろう。
そういった意味から、やはりこのスピーカーはトゥイーターを追加することにより、全体のクォリティをかなり改善することが期待できる。
ただ、アルテックにはパンケーキと呼ばれている20cmフルレンジユニット755Eがあることを思うと、音のクォリティ、周波数帯域のバランスなども、こちらの方がより良い結果が得られるに違いない。
コーラル BETA-8
岩崎千明
ステレオサウンド 32号(1974年9月発行)
「AUDIO MY HANIECRAFT C・Wホーンシステムの制作と試聴記(下)」より
20cmフルレンジユニットとして、国内の中でもおそらく、一番高価な部類に入るであろうこのユニットは、非常に手の込んだコーン紙で、その品質管理などは大変なものだろう。このユニットは高音域において、このユニット自体の出し得る低音のマキシマムに充分マッチし得る高域を持つ。そのためにこのユニットは、普通の使い方では高音がかなり強調されている、と受けとめられており、BETA8の使い方の難しさ、ということばになって伝えられているといえよう。
すでにこのユニットに関しては、メーカー自身の「BL20D」という製品がある。それは今回作った2個付バックロードに対して、に対して、ユニット1個使用という点での相違点はあるにせよ、構造はきわめて似ているので、このシステムでの場合にも当然良い結果が得られるだろうと予測される。
今回の場合、2個のユニットを使用したことで高域のやかましさと一口に言われる音域上のバランスが抑えられたことは事実だ。より好ましい状態に鳴ってくれたといえよう。しかし、それでもなお、今日ここで聴いた中では6kHzから10kHzの高域において非常に鮮かさが目立つ。この鮮かさに対比される低域は、デュアル・バックロードホーンにより非常に豊かな力量感をもち、さらに質的にシャープさをも充分に加え、立上りの良い、切れ味の鋭い、しかも雄大なスケールを再現する低音といったところで、その点ベストだ。
しかし、全体の音のバランスという点からいえばやや高い音の鋭さが気になる。それは「鮮かさ」という点ではプラスであるにしろ、鋭さという形で感じられてしまう。だからユニット前面にパンチングメタルとかフォームラバーの塊による、ディフューザーを付加し、高域のエネルギーを拡散させるのが有効だ。アンプのトーンコントロールを操作するよりも音響的に処理する方が優れたバランスを得られるのではなかろうか。高域の鮮鋭さに対して、中音域での豊かさがちょっと物足りなく感じられ、どうも低音の豊かな冴えた雄大な感じを生かしきれず、もどかしさを感じさせてしまう。いわゆるアンプの中域を上げると、このユニットの持つ中高域の鮮かさを助長させてしまうので、中域を上げるというよりも、中低域を上げるというほうが望ましい。さらに中低域でも低音に類する中低域ではなく、中音に近い中低域、周波数でいうとたとえば300Hzから600Hzまでのオクターブぐらいの音をうまく強められるとすれば、より高いクォリティを望めよう。低音の豊かさが印象的なだけによけいそれを感じさせる。
これは前記のような使い方での改善が期待できるという結論するのが大変なだけに、充分に使いこみ馴らすことが大切であろう。
音のひとつひとつの質的なものが非常に高く、国内のユニットの中では特にバックロードホーンに適しているだけに、バランス的なプラスα(アルファ)が欲しいと感じさせてしまう。それを完成させた結果においては、かのJBLの持っている良さを凌ぐかもしれない。またはエレクトロボイスSP8Bの持っている良さと共通している優秀性ともいえるだろうか。
JBL 2115
岩崎千明
ステレオサウンド 32号(1974年9月発行)
「AUDIO MY HANIECRAFT C・Wホーンシステムの制作と試聴記(下)」より
JBLのLE8T相当プロフェッショナルユニット♯2115は、業務用8インチ・トランスデューサーとしてポータブルモニターなどに使われている広帯域シングルドライバーだ。
音の傾向として、現代のハイファイスピーカーの志向する多くのものをもち、ここで試聴した六機種の中では、もっもとフラットレスポンスを感じさせるユニットだ。リニア・エフシェンシーとJBLでうたっている、音圧に対して非常に動作範囲が広く、さらにハイプレッシャーのユニットには違いないのだが、能率を多少犠牲にしてもリニアに動作する範囲が拡大されている。
そういった意味からは、ホーン型エンクロージュアに必ずしも合っているわけではなく、つまり、他の方式、バスレフ型や密閉型のほうがかえってこのユニットを活かすはずであろうが、しかし、実際にここで使ってみるとバスレフ型や密閉型の大型フロアタイプにしたのとは違った力強さが特に低音の迫力に感じられる。その意味ではもっとも成功度の高かったユニットだ。
ただ、ここで聴きいった他のユニットに較べ、能率がやや低めで、アンプの出力は必要とする。このユニットの特長は、フラットレスポンスなのだが、もうひとつJBLらしさは、やはり人間の声の音域での充実感であろう。この声の漁期に関して、周波数でいうと200Hzからおよそ1200Hzあたりまでの音域に関して、非常に豊かな感じをもっている。それが低音の力強さ、しかも質の良さに支えられ、豊かさを盛り上げている。
このユニットは、フルレンジとして完成度が高いのが何よりも魅力で、あえて高域用ユニットを補うという必要はあまりなく、かえってこのままの状態の方が、このユニットの持ち味を出せる。LE8Tと較べた場合、ぐっと高い方までレンジがのび、エネルギーも強められているので、高域に物足りなさを感じる場合にはトーンコントロールの操作で十分であろう。
ジャズなどを聴いてみると、かなりソロのエネルギーが大きく、ジャズのいわゆる醍醐味も十分。クラシックの弦楽器のファンダメンタルが、ちょうど声の漁期にあたり、実に豊かに出てくれる。いわゆる高い音の繊細な感じというのも充分に秘めながらも、しかも豊かな響きをもつ。
ジャズにしても唄やソロが単に迫ってくるというよりも、むしろ節度を保って前に出てくる。つまり、品の良い音という点でJBLのユニットの中でもはっきりそれを感じられる。
片チャンネルに2本のユニットを使ったことにより、あるいは高域のエネルギーが少々物足りないと感じる場合もあるかもしれないが、アンプのトーンコントロールによってやや高域を上げるだけで、自然なバランスを得られるのはユニットの質の良さによるものだ。ユニットを片側1本での場合はそのままのバランスで充分いける。
この選ばれたいくつかのユニットの中で、周波数レンジの広さもさることながら、音自体のクォリティの高さが特に感じられ、広く誰にでも、どんな種類の音楽を聴く人にも、このユニットは奨められる。いわゆるユニバーサルな傾向をもつシステムとして完成度も高い。
JBL 2110
岩崎千明
ステレオサウンド 32号(1974年9月発行)
「AUDIO MY HANIECRAFT C・Wホーンシステムの制作と試聴記(下)」より
このJBL♯2110に対しては、僕自身も期待の程度がもっともも高かったわけ。原型のオリジナルユニットD208のプロ用としても、また38cmのD130の直系の20cmユニットという点からも。
JBLには、ここで作ったバックロードホーンとほぼ同じような構造をもつプロフェッショナルシステムとして、容積において約4倍近い♯4520というシステムがあり、それに38cmゆにっとをつけたじょうたいとあまりにも似ているので、このシステムには大きな期待をかけたわけだ。
このユニットのもっている傾向というのは、200Hzを中心としてサウンドのバランスの上で明らかにレベルが高い点だ。この辺は、声のファンダメンタルにあたり、声とか楽器のファンダメンタルが非常にアピールされる結果を促し、それ以下の低域エネルギーで、ホーンが効いてくるのでホーンロードによる力強い低音をささえている。
200Hzから800Hzぐらいまでの中低域から低域にかけての音は、いかなる音楽においても最も重要な帯域として、いわゆる豊かさの基となる。その充実感が非常によく出て、どんな曲を聴いても、いかにも音楽が鳴っているなという実感がある。ただ、このユニットは、原形の開発時期が非常に古く、オリジナルはJBLユニットの中でもD130と並ぶ歴史的なユニットだけに、高域に関しては必ずしもレンジが充分とはいえない。
聴いてみると、高域はおそらく3kHzあたりから落ちているし7kHzまでやっと出てる程度で、それ以上はかなり急激に落ちているようだ。したがって現代の再生音楽の水準を満足させんがためには、どうしても高域用のユニットを追加せざるを得ないといってもよい。
トゥイーターをどう選ぶべきかは、この場合幾通りもの考え方ができ、残された楽しみも豊富といえよう。このシステムのまでの完成度は、70点、あるいはそれ以下といいたいかも知れぬ。といっても、こうした音域バランスだけで判断するのは実に危険だ。このシステムの中低域の音の質の良さは、今回集まったユニットの中でも特に群を抜いている。だから70点というのは、そういった良さを無視した上での話であって、その中低域の良さを高く買えば満点にもなり得る魅力を持っている。しかし、2115に較べて誰にでも推めるというわけにはいくまい。楽器の音をなるべつ間近に再生したい方々の期待には充分満足させてくれるのは事実なのだが。
トゥイーターを追加して中音域から高音を補う場合、そのトゥイーターにどういうものを選ぶか、そのクロスオーバーをどの辺にもたせるか、具体的にはいろいろな方法がある。しかし、それによって完成されたシステムは、市販のあらゆるシステムの中でもめったにあるまい。無論ブックシェルフタイプでは到底得られっこないだろう。
今後へのグレードアップという余力を残して、さらに現在の段階においても充分な魅力を持っているという点で、非常にマニア向きな、自作をいとわずに自分の手でシステムを作ろうとする人にとっては大変興味深い上、後々までの楽しみも大きく秘めたるシステムといえる。今回集められたユニットの中で、一番ユニットの本領を発揮した。

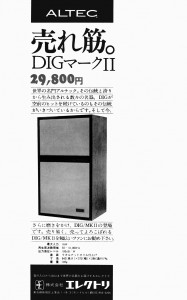


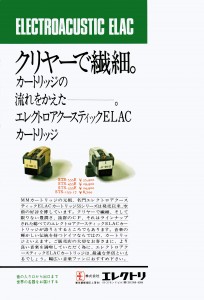
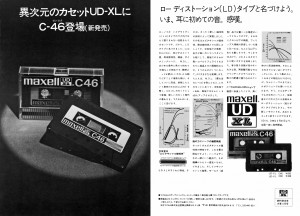
最近のコメント