シーメンスのスピーカーシステムSachsenの広告(輸入元:關本)
(モダン・ジャズ読本 ’82掲載)
Monthly Archives: 12月 1972
シーメンス Sachsen
パイオニア SA-910
菅野沖彦
スイングジャーナル 1月号(1972年12月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
SA910はパイオニアの最新アンプとして登場したもので、いかにも同社らしい巧みな製品づくりの冴えが感じられるプリ・メイン・アンプである。パイオニアがSAシリーズのアンプをだして、もうずいぶん長い年月を経たが、その間、着実に時代の流れに応じて電気回路の改善、機能の充実、デザインの洗練といった歩みを見せ、このSA910に、それらが集約されたといってもよいだろう。パイオニアというメーカー、まことに好調の波に乗ったメーカーで、国内はもとより海外の市場においても高く評価されているが、それは同社の製品づくりの巧みさと、強力な営業政策のバランスの賜で、よきにつけ、あしきにつけ、オーディオ・マニアや市場の機微に精通したプロ精神が心憎いほどに感じられる。
SA910は、その性能、価格の両面からみて、当然、高級アンプであり、まず、見事な外観の仕上げに目をうばわれる。フロント・フェイスの金属パネルは一見単純なさりげなさであるが、その精緻な加工と仕上げは美しく、エッジのフレイム加工に立体的なイメージが活きて高級感を盛り上げている。ツマミ類やコントロール・レバー類のデザイン、感触も好ましく、確度と適当な味わいがバランスし、アンプいじりの喜びを感じることができる。回路を見ると、最新アンプにふさわしい充実したもので、特に、イコライザー、トーン・コントロール、パワー・ステージという全段にわたって二電源方式、差動回路を採用し、高い安定度を得ている。ピュア・コンプリメンタリー、全段直結というのは現在の日本のメーカーが猫も杓子も採用しているパワー・アンプの回路パターンだが、このアンプでも、差動増巾二段、二ヶ所の定電流負荷回路を採用し、実効出力で、60W+60W(8Ω)のパワーを20Hz〜20KHzにわたって確保、その時の高調波歪率と混変調歪率は0・1%というデータを得ている。イコライザー・アンプを中心としたプリ・アンプにも入念な設計がうかがわれ、余裕のあるダイナミック・レンジと、偏差の少いプレイバック・カーブ、低い歪率と、よく練られた素子の定数決定により、高いクォリティの音質が保証されている。
操作パネルを眺めてみると、いかにもパイオニアらしいマニア気質を知り尽した、いじる楽しみとその必然性がよく考えられた配慮がわかる。特に目につくのは、ユニークなツイン・トーン・コントロール、レベル・セット・ツマミ、三系統のスピーカー出力端子とそのうちの一系統に出力レベル調整がついていることだ。
ツイン・トーン・コントロールは、それぞれ異ったトーン・コントロールを単独あるいは組み合わせて使い、広い適応性と、多様なカーブを作り出すことが出来るもの。よく理解して使わないと難しい面もあるが、このアンプを使おうというほどのマニアにとってはむしろ強力な武器ともなるだろう。
レベル・セット・ツマミは、予じめ−15db、−30dbのプリ・セットをすることによって、ボリュームを微妙に動かす必要もなく小音量時の使用が楽に出来るもの。この他に、別に−20dbのミューティングもついているという少々オーバーな手のこみようである。
スピーカー三系統のうち、一系統に出力レベル調整がついているのはなかなか便利。能率の異るスピーカーの併用には威力を発揮する便利なアクセサリーである。
この他、サブソニック・フィルター、30Hz以下カットのフィルターも適切で使いよいし、プリ・メイン・アンプとして要求されるコントロールは完備している。少々複雑過ぎる観もなくはないか、まさにマニア・ライクな代物だ。細かいことだが、どうも気になったのはトーン・デフィート・レバーの表示で、レバーにONという表示があって、トーンをキャンセルしないポジションにトーン・デフィートという表示があるのがおかしい。よく考えるとどっちがどうなのかわからなくなる。国際商品として、この表示は問題があるのではないだろうか?
音質は力のある、それでいて、透明で柔かなニュアンスをよく再現してくれるもので、60W+60Wの出力は決して大パワーとはいえない現状だが(スピーカーが低能率時代だから)あらゆるスピーカーをこなす最低条件は満たす力を持っていると思う。
良い音とは、良いスピーカーとは?(4)
瀬川冬樹
ステレオサウンド 25号(1972年12月発行)
スピーカーから出る音には、いかなる名文、百万言を尽しても結局、その音を聴かなくては理解できない、また一度でも聴けばそれですべてが氷解するような、そういう性質の音がある。百見一聞に如かず、とは誰がもじったのか、よくも言ったものだと思う。
がしかし、ただ単に聴けば済むといった、そんな底の浅いものではない。
オーディオ・メーカーの主催するレコード・コンサートが、近頃また盛んである。マニアの集いとか対話とかシンポジウムとか、いろいろな名目がついているにしても、つまりは自社の新製品の音を聴いてもらおう、という意図にほかならない。わたくし自身もまたその種の催しに、よく引き出されるが、それで困るのは、小さなホールとか会議室とか講堂などの場所で、おおぜいの人たちを相手にして、ほとんとうに良い音とまではゆかぬまでも、せめて、わたくしの意図するに近い音で鳴らすことが殆ど不可能であるという点である。
*
レコード・コンサートという形式がいつごろ生まれたのかは知らないが、LPレコード以降に話を限れば、昭和26年に雑誌『ディスク』(現在は廃刊)が主催した《ディスク・LPコンサート》がそのはしりといえようか。この年は国産のLPレコードが日本コロムビアから発売された年でもあるが、まだレパートリーも狭かったし、それにも増して盤質も録音も粗悪で、公開の場で鳴らすには貧弱すぎた。だからコンサートはすべて輸入盤に頼っていた。外貨の割当が制限されていた時代、しかも当時の一枚三千円から四千円近い価格は現在の感覚でいえば十倍ぐらいになるだろうか。誰もが入手できるというわけにはゆかず、したがってディスクのコンサートも、誌上で批評の対象になるレコードを実際に読者に聴かせたいという意図から出たのだろうと思う。いまではバロックの通俗名曲の代表になってしまったヴィヴァルディの「四季」を、ミュンヒンガーのロンドン盤で本邦初演したのが、このディスクの第二回のコンサート(読売ホール、昭和26年暮)であった。
これを皮切りに、その後、ブリヂストン美術館の主催(松下秀雄氏=現在のオーディオテクニカ社長)による土曜コンサートや、日本楽器・銀座店によるヤマハLPコンサートが続々と名乗りを上げた。これらのコンサートは、輸入新譜の紹介の場であると同時に、それを再生する最新のオーディオ機器とその技術の発表の場でもあった。富田嘉和氏、岡山好直氏、高城重躬氏らが、それぞれに装置を競い合った時代である。
やがて音楽喫茶ブームが来る。そこでは、上記のコンサートで使われるような、個人では所有できない最高の再生装置が常設され、毎日のプログラムのほかにリクェストに応じ、レコード・ファンのたまり場のような形で全国的に広まっていった。そうしたコンサートや音楽喫茶については、『レコード芸術』誌の3・4・5月号に小史の形ですでにくわしく書いたが、LPの再生装置が単に珍しかったり高価なだけでなく、高度の技術がともなわなくては、それを作ることもまして使いこなしてゆくことも難しかったこの時代に、コンサートと喫茶店の果した役割は大きい。
LP装置も普及して個人で楽に所有できるようになってくると、コンサートの形態はやがてレコード会社が新譜紹介の場を兼ねたコンサート・キャラバンというふうに変ってゆく。しかし、すぐにFMの時代が来る。ステレオ放送がはじまり、FMが誰でも聴けるようになると、新譜を聴きにわざわざ遠い会場に集まる人は減ってしまう。コンサートという形が意味をなさなくなる。
レコードの新譜はそうして放送でも聴けるようになるが、再生装置の音質は放送では聴けない。カートリッジの聴きくらべという番組は組めても、アンプやスピーカーの聴きくらべは放送電波には乗るわけがない。そこが、オーディオ・メーカーや販売店でコンサート開催する理由になっている。会場にはいろいろなスピーカーやアンプが置かれ、スイッチで切り換えたり接ぎかえたりして音を聴きくらべる。その場に居合わせた人たちは、確かに自分耳で音を比較したという安心感で帰途につくかもしれない。しかしわたしくは、そういう場所で聴きくらべた音、あるいはまた販売店やショールームの店頭で聴きくらべた音が、そパーツの音だと想うのは誤りだと言いたい。一歩譲っても、そういう場所で聴きくらべた音は、自宅で、最良の状態にセットしたときの音は殆ど別ものだと言いたい。それぐらいのことは、ほんの少しオーディオで道楽した人たちの常識かもしれないが、単に部屋の広さが違うとか音響特性が違うとか、部屋が変れば音が変るなどというよく知られた話をわさわざしたいのではなく、実はもう少し先のことを言いたいのである。
*
ラックスのオーディオ・サルーンという催しが、一部の愛好家のあいだで知られている。毎土曜日の午後と、それに毎月一回夜間に開催されるこのサルーンのメーカー色が全然無く、ラックスの悪口を平気で言え、またその悪口を平気で聞き入れてもらえる気安さがあるのでわたくしも楽しくつきあっているが、ここ二年あまり、ほとんど毎月一回ずつ担当している集まりで、いままで、自分のほんとうに気に入った音を鳴らした記憶が無い。もよう推しのほとんどはアルテックのA5で鳴らすのだが、そしてわたくしの担当のときはスピーカーのバランスをいじり配置を変えトーンコントロールを大幅に調整して、係のT氏に言わせればふだんのA5とは似ても似つかない音に変えてしまうのだそうだが、そこまで調整してみても所詮アルテックはアルテック、わたしの出したい音とは別の音でしか、鳴ってくれない。しかもここで鳴らすことのできる音は、ほかの多くの、おもに地方で開催されるオーディオの集いで聴いて頂くことのできる音よりは、それでもまだ別格といいたいくらい良い方、なのである。しかし本質的に自分の鳴らしたい音とは違う音を、せっかく集まってくださる愛好家に聴いて頂くというのは、なんともつらく、もどかしく、歯がゆいものなのだ。
で、ついに意を決して、9月のある夜の集いに、自宅のJBL375と、パワーアンプ二台(SE400S、460)と、特注マルチアンプ用チャンネル・フィルターを持ち出して、オールJBLによるマルチ・ドライブを試みることにした。ちょうどその日、ラックスの試聴室に、知友I氏のJBL520と460、それにオリムパスがあったためでもある。つまりオリムパスのウーファーだけ流用して、その上に375(537-500ホーン)と075を乗せ、JBLの三台のパワーアンプで3チャンネルのマルチ・アンプを構成しようという意図だ。自宅でもこれに似た試みはほぼ一年前からやっているものの、トゥイーターだけはほかのアンプだから、オールJBLというのはこれが最初で、また、ふだんの自宅でのクロスオーバーやレベルセットに対して、広いリスニングルームではどう対処したらよいか、それを実験したいし、音はどういうふうに変るのか、それを知りたいという興味もあった。
JBLが最近になって新たにプロフェッショナル・シリーズという一群の製品を発表したことはすでに知られているが、そのカタログの Acoustic Lenses Family の中で、比較的近距離(30フィート≒9メートル以内)でのサーヴィスに用いるタイプを限定している点に興味をそそられる。
……Where the length of throw does not exceed 30 feet.(30フィートを越える距離までは放射できません)
model 2305(一般用の 1217-1290 に相当する。有名な LE175DLH 専用のホーン/レンズ)、および #2391(同じくHL91ホーン。オリムパスS7RやC50SMスタジオモニター等に採用されているLE85用のスラント・プレート・ホーン/レンズ)に、とくに上記の註がついている。
もう20年近い昔のこと、池田圭氏から、ウェスターンのホーンのカタログの中に、それをならすリスニングルームの容積の指定があることを教えられたことがあったが、寡聞にして、ホーンのカタログにこうした使用条件を明確にしている例をほかに知らない。同じJBLでも、一般市販品のカタログにこの註がないのは、家庭用として使うかぎり、9メートル以上も離れて聴かれることは無いとかんがえているのだろうか。それにしても、537-500はすでに製造中止で、プロ用のカタログにも復活していないから、上記のどちらの設計に入るのかわからない。1217-1290と同系列の設計だとすれば同じく30フィート以内用とも思えるし、しかし同じ375用の──ほんらいはハーツフィールド用として設計された、そして現在も作られているセ線ン537-509ホーン/レンズ(プロ用の型番は♯2390)は、上記の指定がないところをみると、537-500の方も遠距離用かもしれないという気もしてくる。いずれ確かめてみたい。
もうひとつの興味ある記述は、いまもふれた537-500ホーンが、一般用カタログでは500Hzクロスオーバー用とされているのに対し、プロ用では800Hz以上と指定され、しかもそこまで使うには18インチ角のバッフルにホーンをマウントせよと書いてある。もっとも、一般用のカタログでも、500Hzをクロスオーバーとしているのではなく、……JBL System crossing over at 500 cps. と含みのある表現で、JBLの指定ネットワークで分割した場合に、結果としてアコースティックな分岐点が500Hzになるというニュアンスに受けとれるが。そしてもうひとつのHL91ホーンに至っては、オリムパスでは500Hzのネットワークがついているのに、プロ用の♯2391では、800Hzからでも使えるが1200Hzの方が推奨できる、などと書いてある。
むろんこれは家庭用より大きなパワーで鳴らされることを前提にしているにはちがいないが、だからといって、一般用を無理なクロスオーバーで使うというのも気分のよくない話だ。
そこで白状すれば、わが家の375(537-500ホーン)は、ほぼ一年あまり前から、マルチ・アンプ・ドライブでのヒアリングの結果からクロスオーバーを700Hzに上げて、いちおう満足していた。500Hzではどうしてもホーン臭さを除ききれず、しかし700Hzより上げたのではウーファーの方が追従しきれないという、まあ妥協の結果ではあったが。
ところでラックスのサルーンでの話に戻る。ふだん鳴らしている8畳にくらべると、広い試聴室だけにパワーも大きく入る。すると375が700Hz(12dBオクターブ)ではまだ苦しいことがわかり、クロスオーバーを1kHzまで上げた。しかしこうすると、ウーファー(LE15A)の中音域がどうしても物足りない。といってクロスオーバーを下げてホーン臭い音を少しでも感じるよりはまあましだ。075とのクロスオーバーは8kHz。これでどうやら、ホーン臭さの無い、耳を圧迫しない、やわらかくさわやかで繊細な、しかし底力のある迫力で鳴らすことに、一応は成功したと思う。まあ70点ぐらいは行ったつもりである。
むろんこれは自宅で鳴っている音ともまた違う。けれど、わたくしがJBLの鳴らし方と指定とした音には近い鳴り方だし、言うまでもなくこれまでアルテックA5をなだめすかして鳴らした音とはバランスのとりかたから全然ちがう。ここ2年あまりのこの集まりの中で、いちばん楽しい夜だった。
と、ここからやっと、ほんとうに言いたいことに話題を移すことができそうだ。
このサルーンは人数も制限していて、ほとんどが常連。まあ気ごころしれた仲間うちのような人たちばかりが集まってきて、「例のあれ」で話が通じるような雰囲気ができ上っている。そうした人たちと二年顔を合わせていれば、わたくしの好みの音も、意図している音も、話の上で理解して頂いているつもりで、少なくともそう信じていた。ところが当夜JBLを鳴らした後で、常連のひとりの愛好家に、なるほどこの音を聴いてはじめてあなたの言いたいこと、出したい音がほんとうにわかった、と言われて、そこで改めて、その音を鳴らさないかぎり、いくら言葉を費やしても、結局話は通じないのだという事実に内心愕然としたのである。説明するときの言葉の足りなさ、口下手はこの際言ってもはじまらない。たとえばトゥイーター・レベルの3dBの変化、それにともなうトーン・コントロールの微調整、そして音量の設定、それらを、そのときのレコード、その場の雰囲気に合わせて微細に調整してゆくプロセスは、結局、その場で自分がコントロールし、その結果を聴いて頂けないかぎり、絶対に理解されない性質のものなのではないかという疑問が、それからあと、ずっと尾を引いて、しかもその後全国の各地で、その場で用意された装置で持参したレコードを鳴らしてみたときの、自分の解説と実際にその場で鳴る音との違和感との差は、ますます大きく感じられるのである。自分の部屋のいつも坐る場所でさえ、まだ理想の半分の音も出ていないのに、公開の場で鳴る音では、毎日自宅で聴くその音に似た音さえ出せないといういら立たしさ、いったいどうしたらいいのだろうか。音は結局聴かなくてはわからないし、しかしまた、どんな音でも聴かないよりはましなどとはとうてい思えない。むしろ鳴らない方がましだと思う音の方が多すぎる。
*
結局自分の部屋で鳴らしてみなくてはわからない。けれど、JBL375を、わたくしは鳴らしてみて購(もと)めたのではなかった。むろんその前に短い期間ではあったが175(LE175DLH)を鳴らして一応はたしかめている。しかし375を鳴らしてから購めたわけではない。
ずっと昔、モノーラル時代には175の音を聴いている。たとえばヤマハのコンサート。あるいはまた、いまは無くなってしまった有楽町フードセンターのフジヤ・ミュージック・サロン。ここは当時、鈴木章治とリズムエース、藤家虹二クインテット、白木秀雄クインテットなどが、毎日ナマを聴かせていた。その演奏の合い間に、レコードやテープを鳴らす装置がJBLのスピーカーで、トゥイーターに、まだグレイ塗装の、JBLではなく Jim, Lansing と書いた〝LE〟のつかない175DLHが鳴っていた。しかしその音はどういうわけか──おそらくアンプかどこかが歪んでいたのだろうと思うが、およそ175本来の片鱗もない、ひどく歪みっぽい、じゃりじゃりした音で鳴っていた。片鱗も無いなどとは今だからそう言えるので、ちょうどその頃は、高価な品物が買えないひがみもあって、アメリカ製のスピーカーにはロクなものが無いなどというラジオ雑誌の記事を鵜呑みにしていたのだから、そういうひどい音を聴いたところでかえって国産愛用の念が強まればこそ、歪んだ音ぐらいでは少しも驚きはしない。ではヤマハのコンサートではどうだったのかといえば、そこではまさか歪んだ音など出してはいなかったが、外国製品は悪いと頭から信じて聴けば、良い音も悪く聴こえるものだし、良い音と信じて聴けば、鳴っていない音さえも鳴って聴こえる。
ただの比喩ではない。実際にあった話だ。当時、外国製スピーカーは悪いという伝説を撒きちらしていたオーディオ・マニアのグループが、これこそは最高と信じていた国産のホーン・トゥイーターがあった。そのトゥイーターを、あるとき、レコード愛好家のS氏邸に持ちたんだのだそうだ。そうだ、というはそこにはわたくしは居合わせず後から伝え聞いた話なので、だからこの話には誇張があるのかもしれないが、ともかく、S氏のスピーカー・システムのトゥイーターをそのホーンに接ぎかえて、レコードをかけた。マニアのグループは期せずして素晴らしいと叫んだそうだ。本もののトゥイーターをつけると、ほら、こんなにハイが美しくなるんですよ。ハイを伸ばすと、高音がキンキンするというのは迷信です。本当に歪みなくよく伸びた高音は、こういうふうにおとなしいのです……。エンジニアがしたり顔で解説したそうだ。この説明はしかし全く正しい。
ところでS氏は黙って聴いておられたが、やおらつかつかとスピーカー・システムのところに歩みより、トゥイーターに耳をつけて音を聴くことしばし。
「君、このスピーカー、鳴っとらんぞ」
一同がどういう顔をしたのか、接続をし直して鳴った音をそれからどう説明したのか、そのあとの話は知らない。
けれど、実はこの話をただの揶揄でここに書いたのではない。むしろ逆だ。信じて聴く耳は、鳴らない音さえ聴きとることを、この実話はみごとに物語っている。確かに一同の耳にはそのとき素晴らしい理想の音が鳴り響いていたに違いあるまい。この話は滑稽であるだけに、かえって悲しいほど美しくわたくしには思われる。わたくしにだってそれに似た体験が無いわけではない。

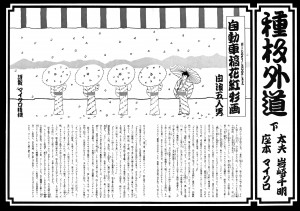
最近のコメント