アイワのカセットデッキTP1100、カシーバーTPR2001の広告
(スイングジャーナル 1971年11月号掲載)
Monthly Archives: 10月 1971
アイワ TP-1100, TPR-2001
JBL SG520, SE400S, SE460
岩崎千明
スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)
「supreme equipment 世界の名器を探る」より
71年の看板商品だったアクエリアス・シリーズが評判の割に1型、4型を除き、宇宙的デザインの主要高級品2、3が本国で思わしくないとかの噂。世界のJBLも近頃はその威光にかげりが見えたとか、ささやかれている。
これを吹き飛ばすかのようにプロフェショナル・シリーズが日本にもお目見えして、またまた話題を呼びそうだ。米本国のプロの分野で大手を振って幅をきかせているアルテックと並び、JBLが最近勢いを急進しているという。
今やJBLはスピーカーだけでなくアンプを中心として音響設備に大々的に乗り出しているのである。
JBLがアンプを作り出したのは、自社のスピーカーももっとも理想的に鳴らすという、はっきりした目的を持っている。当り前だがメーカーとしてこれほどはっきりした姿勢を、製品に持たせたことはそれまでにはなかった。JBLが「バラゴン」というステレオの3ウェイのホーン・ロード・システムを発売したときと同時に「エナージァイザ」という変った呼び方で発表したパワー・アンプが、パラゴンのドライブ用だ。スピーカー・システムの後側には、専用の格納スペースさえ設けられている。
このアンプにつけられる名称通り、スピーカーの音響エネルギーの供給用という目的が、はっきりと出ているし、それがJBLの姿勢そのものなのである。この「エナージァイザ」にはパラゴン用とするときの低音上昇のための専用イコライザー・ボードが内蔵されていた。
このエナージァイザはSE400として独立したステレオ用パワー・アンプの形で発売されたが、それと同時に発売されたのがSG520プリ・アンプでグラフィック・コントロ−ラーという名称をつけられた。スライド型のコントロールと、プッシュ・ボタンの切換という当時まったく新鮮なデザインに対して名づけられた。ステレオ・ブームの始まろうとする61年のことである。その翌年には早くもSG520は米国内西海岸のグッド・デザイン製品に選ばれ、品質、デザインとも、ずばぬけた高性能を認められたのは当然であった。
この当時は真空管アンプで圧到的に他を圧していたハーマン・カードン社のサイテイション・シリーズがトランジスタ・ライズされた製品を発表し、今はなきアコーステック・ラボラトリのアコースティック・アンプが好評のもとにスタートした。しかし、現在、そのいずれもが数年前に姿を消し、ハーマン・カードン社もこのトランジスタ・アンプの失敗が原因で大きく後退を余儀なくされマイナーに引下ってしまった。トランジスタ・ライズに早くからふみ切って成功したのはJBLアンプだけなのである。これは実に偉大な技術的成果であり、メーカーの姿勢の正しさをも示すといえるであろう。
かつて初期のSE400を実測してみたことがあった。ステレオ用として同時にフルパワーな出したとき、それはあらゆる周波数で60/60ワットを示した。規格の上ではなんと40/40ワットのアンプがである。現在はSE460としてさらに大きくパワーアップされている。
この直後、私はSG520と、SE400を組み合せて手元におき、毎日のように愛用し、リスニング・ルームのメインとして活躍しているのはいうまでもない。
永年使用してみてはっきり知らされたことは、61年に発表したSG520は10年を経た今日といえとも、これに匹敵する美しく華麗なステレオ・サウンドを持ったトランジスタ型のアンプを知らない。10年たった今においてまさに世界の名器といわれも大きな理由であろう。メーカーのすぢ金をこれほどはっきりと感じさせるアンプはめったにないであろうし、それは10年に渡って何ら変ってはいないのである。
サンスイ AU-888, TU-888
レンコ L-75
オタリ MX-5000
菅野沖彦
スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
テープレコーダー・メーカーとしての小谷電機(オタリ)の名前は一般には耳新しいかもしれない。事実そんなに古い会社ではないが、それでも創立以来7年目を迎える。そして、この会社の製品は、デュプリケーター、マスター・レコーダーの分野ではプロの間で既に有名で、特にデュプリケーターのシェアは圧倒的。一部、外国製品をのぞいて、ほとんどのミュージック・テープ・メーカーでは同社のものを使っている。8トラック・カートリッジのブームに乗って急激に成長したメーカーである。プリントの送り出しマスターとして必要なマルチ・トラック・テレコも手がけ、それらの技術をそのまま生かせるスタジオ用のテレコも製造している。したがって、その名は直接知らなくても、プログラム・ソースを通して、多くの人がオタリ製品の音を聴いていることになる。社長自身がエンジニアで、若く、はつらつとした体質をもったメーカーなのである。
ところが、この専門メーカーとしての技術を一般のコンシュマー・プロダクツに生かした製品が、今回御紹介するMX5000という4トラック・オープン・リール・デッキである。この製品の前に、MX7000という2トラック・38cm/sをメイン・フューチュアーとしたデッキが発売されているが、これは一般用というより、むしろ、セミプロ級の機器であった。MX5000がオタリの初めての一般オーディオ・マニアとの接触点とみてよいだろう。
いきなり苦言を呈するのは、いささか気がひけないでもないが、同社の製品はその堅実で充実した内容にも拘わらず、なんともセンスの悪いデザインであって、プロ機として工場やラボの中でならともかく、アマチュアの音楽的雰囲気豊かな部屋へとけこむにはなんとも見栄えのしないのが残念である。この感覚でほ、巌しいマニアの目には耐えられないといわざるを得ない。技術が丸裸で飛び出したというのが誇張のないところであって、素材や、加工にお金がかかっていながら、それらを生かし切っていない。よく見れば、手造りらしい好ましい雰囲気や、まじめな製作態度がよくわかるのだが……、これから同社か第一線メーカーとして飛躍するのに直面しなければならない問題といえるだろう。
このような苦言は、私があえて言及するまでもなく、それぞれのユーザーの目に明白に見えることだが、あえて、このことに触れたのは、その内容のよさのゆえである。つまりなんとか、この点だけを改めれば、第一級の製品と思えるからこそである。
MX5000は3モーター、4ヘッドの高級4トラ・デッキで、きわめてオーソドックスな設計思想による製品だ。サウンド・オン・サウンド、エコー回路、オートリバース(再生のみ)といったアクセサリー機能を備えてはいるが、その基本的な性格は、プロ用の3モーター、3ヘッド・デッキにあって、これをグレードを落さずにコンシュマー製品にしたものと思える。トランスポートはヒステリシス・シンクロナス・モーターでキャプスタンをベルト駆動、サプライ、テイク・アップにはそれぞれ余裕のあるインダクション・モーターを使っている。走行系のレイアウトもアンペックス式のごくありきたりのもので、それだけに信頼度が高い。操作ボタンはよく考えられた碁盤型のプッシュ式でリレー・コントロールである。スクエアーなプッシュ・ボタンを採用しているので、押すポジションによって動作がやや不確実になるのが惜しまれるが、レイアウトのアイデアは高く評価したい。エレクトロニックスは、3段直結ICを使用し、現時点でのテープに広く適用するように半固定のバイアス・アジャストをそなえている。スイッチによる大ざっばな切換えではなく、オシレーターを使ってのバイアス・アジャストとした点にもこの製品が、ハイ・レベルのユーザーを狙ったものであることが知れるだろう。実際に使用してみて、その使いよさ、堅実性はプロ機そのものといってよく、録再オーバーオールでの特性ははよく確保され、ソースとモニターの切換試聴でも、かなり優れた性能を知ることができた。高域でのトーン・クォリティーはきわめてナチュラルなのが好ましく、表面的な音造りなどという姑息は感じられなかった。実質的に大変価値の高いテープ・デッキだと思う。
パイオニア E-1000M, E-3000M
ソニー ULM2, ULM3, ULM4, ULM6
ラックス SQ507X
岩崎千明
スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
ここに紹介するラックスの新型アンプSQ507Xは、この71年秋発表される製品の中でもっとも魅力に富み、その期待に十分応え得る品質を秘めたSJ選定の名に恥じぬアンプである。
ラックスは、同社のベストセラーであるSQ38FDアンプにみられる通り、今日で市場にあるただひとつの管球式を現在に到るも市販、製品化しているきわめて「保守的」な色彩を濃く持ったメーカーである。日進月歩、技術のピッチの著しい。ステレオ・メーカーとしてトランジスタ・アンプが幅をきかせる今日、今だにSQ38FDを商品としているのがこのメーカーのよい面にも悪い面にも出ているのだ。
良い面は、いわずとしれて、高級マニアの欲する技術を温存していることにあり、「音楽のわかる」ことを誇るステレオ・メーカーである。悪い面はこのメーカーの作るトランジスタ・アンプが他社ほどにふるわない原因を作っているともいえるし、名作SQ38FDがラックスの作ってきた今までの数多いトランジスタ・アンプの影を薄くしてしまっているという事実だ。
このSQ38FDのイメージをぶちやぶらずには、アンプ・メーカーとしてのラックスの地位を将来に確保することすらおばつかないのではあるまいか、という危惧はラックスのアンプの高品質を知るものにとって、おそらく共通の懸念であり、またこれからのアンプに対する期待でもあったに違いない。
ラックスが発売したSQ507Xは、まさにSQ38FDの水準に達し、それを追い越したといい得る「最初」の製品である。
このアンプの音に接したとき、このアンプの中味がすでに発売されているSQ505Xとほとんど変ることがなく、ただパワー・ステージを強力な石に換えて出力をアップしただけと聞かされ、それを疑ったほどである。つまり、それほどにSQ505Xにくらべ、音色の向上が明瞭なのである。
深みと、うるおいのある音から、SQ505Xのと同じ回路方式とはどうしても思えないぐらいだ。あえていえば、これはJBLのアンプに近い音であるともいえるし、SQ38F特有の美しい音を受け継いでいるともいえる。
ジャズ・サウンドのとりこになっている私にすれば、今までふれてきたラックスのトランジスタ・アンプの音は、やはりアタックにもの足りなさと歯がゆさをいつも味わうのだが、このSQ507Xに対してはそれが全然なかった。アルトやテナーのソロの迫力、ピアノのアタックのガッチリした響き、どちらもSQ507Xは見事にたたきだした。シンバルの輝きも、ベースの厚いうねりも、楽々と再生してくれた。この深みはかってSQ38FDで得た力強いベースに匹敵し、トランペットの輝きはSQ38FDさえ凌駕していた。このしっとりとして、しかも華麗ともいえるうるおいを他に求めればトランジスタ・アンプではJBLのそれしかないのである。
この艶ややかにして素直なサウンドは、ラックス特有のシンプルな構成のトーン・コントロール回路と全段直結の融合による所産であるに違いない。さらに加えるならば構成ステージをやたら増すことなく、全体にムダを廃しゼイ肉を落し切った構成にあるのであろう。
しかも、このアンプの11kgという重量は電源回路のゆとりあるレギュレーションを意味し、見えない所まで徹底したメーカー技術陣の充分なる配慮をうかがわせる。
ラックスが今秋発象したSQ505X、503Xなどの全段直結アンプ群の最高級品としての誇りと品質とを担って登場したSQ507X、おそらくこのメーカーの今後の発展の強力なる索引力となるに違いない。
ソニー SLH
オルトフォン STA202J, シュバイツアー Recored Cleaner, Recored Service, etc…
オーディオテクニカ AT-1009, AT-6005
ビクター MCA-V9
オットー DCA-150X
ビクター TD-450, CCR-661, CHR-260
富士フィルム FG, FM
ティアック A-6010GSL, A-7010GSL, A-7030GSL, A-2300, A-2520, A-2420, A-2500, A-2100
ソニー STR-6000
ソニー TC-6040, TC-6364, TC-8040, TC-9040, TC-9520, TC-9540
ソニー TAE-8450 + TAN-8550
菅野沖彦
スイングジャーナル 11月号(1974年10月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
今年のオーディオ界の大きな論題の一つとして特筆すべきものといえば、FETパワー・アンプの実用化ということであろう。すでに、この新しい素子、V-FETについては多くの機会に紹介されている。従来のトランジスタとは異なった動作特性をもつV-FETが、かなりの高出力アンプの出力段に使えるようになって、その音質がいろいろうわさされているようだ。たしかに、この新しい素子によるアンプの音は、独自の音質をもっていて、従来のトランジスタ・アンプとはちがう。しかし、率直にいって、私には、その音のどれだけの部分が、V-FETそのものによるものなのかはわからない。アンプの音質や音色を左右するファクターはあまりに多く、ただ単純にFETアンプの音はこうだというような断定をする勇気はないのである。ただ、いえることは、私が今まで聞いて来た多数のトランジスタ・アンプ群とはちがった音の質感(タッチとクォリティ)をもっていて、大きく音質のカテゴリー別の地図を描くことが、可能だという程度である。この新製品を紹介するに当っては、先入観をもたずに、実際の音に接してみる努力をしたつもりだが、やはり新鮮な魅力を持った音というのが第一印象であった。
TAE8450プリ・アンプと、TAN8550パワー・アンプは、当然ペアーで使われることを考えてデザインされたものだとは思うけれど、それぞれ、セパレート・アンプとして独立した機能と価値をもった製品である プリ・アンプのTAE8450は実に多機能なコントローラーで、一見したところ、その操作部分の複雑多岐なことに驚ろかされる。いずれもあって便利なものばかりだが、よほど馴れないと、一つ一つ見ながらでないと操作出来ない。無意識にコントロールするようになるには大変な熟練がいりそうだ。オプティカル・ピーク・プログラム・メーター(PPN)と称されるライト・ビームのピーク・メーターは中でも本器の大きな特長であろう。これはパワー・アンプ8550のほうにもついているから、二台一緒に使うと壮観である。このメーターはプログラムのピーク値を指示できるだけではなく、その値をホールドして示してもくれるという素晴らしいもの。またスイッチでVUに切換えても使える。各種コントロール機能についてふれているスペースはないが、全て確実な動作と効果のあるものが完備している。それよりも、このプリ・アンプの音質の純度の高さは高く評価できるもので、特性的には全く不満がないといってよい。音像の解像度、セパレーション、プレゼンスなど全て満足すべき高い品位をもつ。ただ、パネルのハードなイメージのためかも知れないが、座右において使いこもうという魅力には一つ欠けるというのが正直な感想だ。このことはパワー・アンプの8550についてもいえると思う。100W×2の余裕ある大出力で、ゲインも高いにも拘わらず残留ノイズの少さ、ローレベルからのリニアリティのよさ、暖みのある音の肌ざわりもあって、きわめて高度な水準にあるパワー・アンプだと思う。しかし、もう一つ音の生命感、力感というものが物足りない。素晴らしいなあと感心するのだが、もう一つ、ふるいつきたくなるような魅力に欠けるのである。こういうことは純技術的な立場からすれば理解できないかもしれないが、根拠のないことと片づけられるかもしれない。しかし、現実に多くのアンプの中に魅力の要素の有無がはっきりある以上、使い手としては、魅力を待ったものに惹かれるのは致し方あるまい。しかも、それが、私が録音し得たと思っている魅力のファクターをよく出してくれるものと、そうでないものとがあるという現実の前には、考え込まざるを得ないのである。微視的な見方をすると、このパワー・アンプ、中高域(400Hz以上)はウォームで豊かだ。私見としては、低域の力強さの点でもう一つといったところ。全体に今一つベールをはいだ冴えが欲しい。しかし、これはもの凄く高い次元での欲張った話であって、この二つのアンプが世界的水準で最高のものであり、その設計のバックグラウンドから製品の仕上りにまで、オーディオ・マニアの気質分析と技術の高さが横溢している。



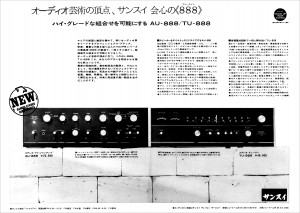








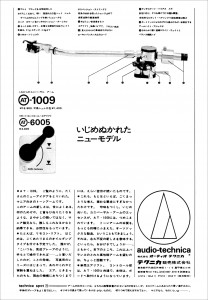





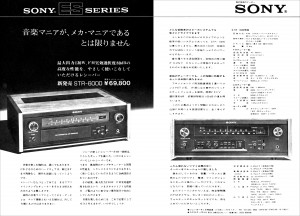

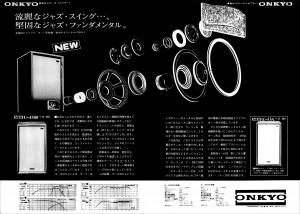
最近のコメント