ヤマハのスピーカーシステムNS690III、カセットテープMUSIC、MUSIC ex、STUDIO ex、METALの広告
(別冊FM fan 33号掲載)
Category Archives: スピーカーシステム - Page 18
エレクトロボイス Interface:AIV
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
これもまたアメリカのスピーカーであるが、エレクトロボイスは、アメリカのミッド・イーストを代表するメーカーである。このスピーカーのだす音を、ほんの1分もきけば、そのことは、誰にでもわかるはずである。ひとことでいうと、都会の音──とでもいうことになるであろうか。辛口の音である。ウェストコーストを出身地とするスピーカーの、あのあかるく解放感にみちみちた音とは、ひとあじもふたあじもちがう音である。同じアメリカのスピーカーでも出身地がちがうのであるから、JBLやアルテックをきいたレコードとはちがうレコード、つまりビリー・ジョエルやトーキング・ヘッズのレコードを、かけてみた。
ビリー・ジョエルやトーキング・ヘッズのレコードをきいてみて、なるほどと納得のいくことが多々あった。トーキング・ヘッズの音楽のうちの棘というべきか、鋭くとがったサウンドを、このエレクトロボイスのスピーカーは、もののみごとに示した。もし、時代の影といえるようなものがあるとすれば、そのうちひとつがトーキング・ヘッズの『リメイン・イン・ライト』できける音楽のうちにあるのかもしれない。そういうことを感じさせる、このエレクトロボイスのきこえか方であったということになる。
ビリー・ジョエルの『ニューヨーク52番街』は、音楽の質からいっても、性格からいっても、トーキング・ヘッズのレコードできけるものとずいぶんちがうが、きこえた音から、結果的にいえば、似たところがあるといえなくもない。つまり、リズムの示し方の、切れの鋭さである。いや、もう少し正確にいえば、リズムの切れが鋭く示されているというより、リズムの切れが鋭く示されているように感じられるということのようである。
そのように感じられるのは、おそらく、このスピーカーの音が、ウェストコースト出身のスピーカーのそれに較べて、いくぶん暗いからである。
しかし、音が暗いといっても、このスピーカーの示す音には湿り気は感じられない。音は充分な力に支えられて、しゃきっとしている。ひびきの輪郭がくっきり示されるは、そのためである。
ハーブ・アルバートの『マジック・マン』のきこえ方などは、まことに印象的であった。アルバートによるトランペットの音がいつになくパワフルに感じられた。トランペットの音の直進する性格も充分に示されていたし、リズムの切れもよかった。音場感的にもひろがりがあってこのましかった。ただ、ひびきが、からりと晴れあがった空のようとはいいがたく、いくぶんかげりぎみであった。そういうことがあるので、ウェストコースト出身のスピーカーできいたときの印象と、すくなからずちがったものになった。
こうやって考えてくると、このスピーカーの魅力を最大限ひきだしたのは、どうやら、トーキング・ヘッズのレコードといえそうである。そこで示された鋭さと影は、まことに見事なものであった。
BOSE 301 Music Monitor
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
このスピーカーはいい。価格を考えたら大変にお買得である。
むろん、スケール感がほしいとか、腰のすわった低音をききたいとか、あれこれむずかしい注文をだしても、このランクのスピーカーに対応できるはずもないが、きかせるべき音を一応それらしく、あかるい音で、すっきりきかせる。小冠者、なかなかどうしてようやるわい──といった感じである。きいていて、いかにもさわやかで、気分がいい。
このボーズ301MUSIC MONITORのきかせる音は、ひとことでいえば軽量級サウンドである。それにしても、吹けばとぶような音ではない。しんにしっかりしたところがあるので、音楽の骨組みをあいまいにしない。そこがこのスピーカーのいいところである。なかなかどうしてようやるい──と思えるのは、そういういいところがあるからである。
ハーブ・アルバートのレコードのB面冒頭には、しゃれたアレンジによる「ベサメ・ムーチョ」がおさめられているが、それなどをきいても、いくぶん小ぶりな表現ながら、細部を鮮明に示して、あざやかである。このアルバートによる「ベサメ・ムーチョ」は、深いひびきのきざむリズムにのってはこばれるが、あたりまえのことながら、本当に深いひびきは、このスピーカーではきけない。それをきこうとしたら、やはりどうしても大型のフロアースピーカーのお世話にならなければならない。しかし、このボースの301MUSIC MONITORは、その深いひびきの感じを、一応、それらしく示す。
音場的なひろがりの面でも、このスピーカーは、あなどりがたい。ハーブ・アルバートのレコードが、せまくるしくあつくるしくきこえたら、きいていてやりきれなくなるが、その点で、このスピーカーの示す音場とひびきの質は、このましい。あくまでもさわやかであり、すっきりしている。このスピーカーもまた、ウェストコースト・サウンドの特徴をそなえているといっていいように思う。
マーティ・バリンのレコードもよかった。うたわれた言葉はシャープにたちあがる。ただ、難をいえばリズムをきざむソリッドな音に力が不足している。そういうこのスピーカーのいくぶんよりよわいところが、ランディ・マイズナーのレコードではより強く感じられるとしても、決して湿っぽくなったり、ぐずついたりしないひびきのこのましさがあるので、致命的な弱点とはいいきれない。
アルバートのレコードにしても、バリンのレコードにしても、マイズナーのレコードにしても、大滝詠一のレコードにしても、音がべとついたり、ぼてっとしたりしたら、それぞれのレコードできける音楽の本質的な部分がそこなわれ、その音楽の最大のチャーミング・ポイントをたのしめないことになる。すくなくともそういうことは、このボーズの301MUSIC MONITORではない。
もし環境の面で許されるなら、パワーを少し入れてやると、ひびきの力感に対しての反応もよりこのましくなるであろうし、このフレッシュな音をきかせるスピーカーは、魅力充分といえそうである。
アルテック Model 6
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
JBLのL112をきいた後でこのスピーカーをきいて、そうか、そうであったな、これもまたウェストコースト出身のスピーカーであったなと思わないではいられなかった。それほど、JBLのL112とこのアルテックのMODEL6とでは、ちがう。したがって、そういことがあるので、出身地別でスピーカーに安易にレッテルをはることはつつしまなければならない。ことはまことに微妙である。よほど用心してかかる必要がある。さもないと、とんでもない誤解をしてしまいかねない。
しかし、このアルテックのMODEL6もまた、まきれもなく、アメリカのウェストコースト出身のスピーカーの特性をそなえている。それがなにかといえば、ひびきのおおらかさである。ひびきのおおらかさはJBLのL112でも充分に感じられたものであるが、それとこれとのいずれでよりきわだっているかというと、このMODEL6においてである。ただ、すぎたるはおよばざるがごとし──ともいう。このスピーカーの音は、たしかにおおらかではあるが、おおらかにすぎたといえなくもない。
たとえば、マーティ・バリンのレコードで、例の「ハート悲しく」をきくと、JBLのL112できいたときより、陽気な歌に感じられる。ひびきが、おおらかで、率直な分だけ、この歌の影の部分が薄くなったというべきであろうか。バリンの声には独自のかすれがあるが、それを充分に感じとれるとはいいがたい。その辺にこのスピーカーの多少の問題がある。
しかし、JBLのL112とこアルテックのMODEL6では、価格の面でわずかとはいいがたい差があるから、同列において四の五のいったら、アルテックのMODEL6に対してフェアでない。判断する場合には、その価格の面での差を割引いて考える必要があるものの、スピーカーの音の性格として、鋭角的なひびきより丸みのあるひびきの表現にひいでているということはいえるにちがいない。
たとえば、ランディ・マイズナーの『ワン・モア・ソング』をかけたときのサウンドなどは、ききてをのせる。中域の音が充実しているからであろう。そのストレートなサウンドは、爽快である。ただ、これは、このランディ・マイズナーのレコードでも、マーティ・バリンのレコードでも、そして大滝詠一のレコードでもいえることであるが、総じて、声より楽器の音の方がきわだちぎみで、声、ないしはうたわれている言葉は、ともすると楽器のひびきの中にうめられる傾向がある。
ハーブ・アルバートのレコードもわるくない。アルバートによって吹かれたトランペットの音が、その特徴をきわだてているとはいいがたいが、音楽の力感をよく伝える。そのようなことから、このスピーカーの音のもちあじを、こだわりのない率直さということもできるであろう。
音楽の力強さをすとんと示すが、ひびきの微妙なところにこだわる人は、そこにものたりなさを感じるのかもしれない。しかし、このスピーカーのきかせる音には、俗にウェストコースト・サウンドといわれる独調のひとつである解放感があることはまちがいない。
JBL L112
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
JBLはアメリカ・ウェストコーストを代表するメーカーである。なるほど、この音像をいささかもあいまいにならずくっきり示す示し方、それに力感のあるサウンド、それでいてあくまでさわやかであることなどは、これぞウェストコースト・サウンドといいたくなるようなものである。ひびきのきめのこまかさがもう少しあればと思わなくもないが、しかし、それがかならずしも弱点とはいいがたいところに、このスピーカーの魅力があると考えるべきであろう。
ランディ・マイズナーの『ワン・モア・ソング』などでは、リズムのきざみに、いわくいいがたい、本場ものの独自の説得力とでもいうべきものが感じられる。高域は、さらに一歩進めば、刺激的な音になるのであろうが、その手前にふみとどまって、すっきりした、ふっきれたサウンドをうみだしている。こういうレコードは、こういうスピーカーでききたいなと思わせる、ここでのきこえ方であった。
マーティ・バリンの『恋人たち』も、とてもすてきにきこえた。そのレコードのうちの、テレビのコマーシャルでつかわれているA面の冒頭に入っている「ハート悲しく」をきいたのであるが、子音をたてた音のとり方や、歌の、粋で、ちょっときどった、それでいて孤独の影のうちにある気配を、もののみごとに示して、なるほど、このレコードは、こういう音できくべきなんだなと思わせた。このスピーカーの音は、あくまですっきりさわやかであるから、多少音像が大きめになっても、ぼてっとしない。
マーティ・バリンの場合と似たようなことのいえるのが、大滝詠一の『ロング・バケーション』であった。このスピーカーにおける音のキャラクターの面での大らかさが、ここではさいわいしていたとみるべきであろう。スピーカーからでてくる音は、湿度が低く、からりと乾いているから、抒情的な歌もじめじめしない。
ただ、大滝詠一の『ロング・バケーション』できけるような性格の音楽なら、このJBLのスピーカーの音にも申し分なくフィットするが、日本の歌でも、たとえば演歌のようなものではどうなのであろうと考えなくもなかった。このスピーカーの音がふっきれているだけに、もしかするとあっけらかんとしたものになってしまうのかもしれない。
ハーブ・アルバートの『マジック・マン』のレコードは、すべてのスピーカーできいてみたが、ここでのきこえ方は、それらのうちのベストのひとつであった。こういう性格の音楽とサウンドでは、このスピーカーは、そのもちあじのもっともこのましい面をあきらかにする。アルバートの吹くトランペットの音は、まことに特徴があって、誰がきいても、あっ、これはアルバートとわかるようなものであるが、その音の特徴が、このスピーカーでは、いとも鮮明に示された。
それに、トランペットの音の直進する感じも、ここではよくききとれ、ききてに一種の快感を与えた。音楽の走りっぷりのよさを実感させる音であり、きいていて、なんともいえずいい気分であった。
このスピーカーの音は、ひとことでいえば解放的で、すべての音が大空めざして消えていくといった気配であった。さわやかさは、なににもかえがたい魅力といってもいいであろう。
KEF Model 303
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
これはいいスピーカーである。スペンドールのBCIIもすぐれたスピーカーであったが、やはりこのスピーカーと較べると、いくぶん大人っぽいところがあった。このKEFの303の方が、いまの音楽、いまのサウンドをきくには、あっている。ひびきがひときわフレッシュである。ただ、あらためていうまでもないと思うが、スケールの大きいな音楽を恰幅よく示すタイプのスピーカーではない。それに、こもまたイギリス出身のスピーカーであるから、ひびきは暗めである。スペンドールのBCIIよりはいくぶんあかるいようであるが、あのアメリカのウェストコースト出身のスピーカーに較べれば、やはり暗いといわざるをえない部分がある。その分だけひびきのきめがこまかいとしても、聴感上は暗いというべきであろう。
デイヴ・エドモンズの『トワンギン』で特徴的な、高い方でのいくぶんざらついた音への対応のしかたは、きいて、なるほどと思うものであった。きれいにみがきあげられたとはいいがたい音の、汚れた音であるがゆえの生命力とでもいうべきものを、なまなましく示した。これはイギリス出身のスピーカーに共通していえることでもあるが、このKEFの303でも、声がヴィヴィッドに示されたのが印象的であった。
そのために、アメリカのウェストコースト出身のレコードであるマーティ・バリンのレコードを、ここでまたきいてみたいと思った。きいてみたら、なかなかいい感じであった。バリンのかすれた声をうまく示した。しかも、バリンの歌に、ウェストコースト出身のスピーカーできいたときには感じとりにくかった大人っぽい雰囲気があることがわかった。いくぶんかげりのあるひびきの中に、バリンのスリムな声がすっきり定位して、なかなかいい感じであった。
スライ&ロビーの『タクシー』もよかった。シャカシャカした音とソリッドな音の対比を充分につける能力をそなえたスピーカーであるから、このレコードできける音楽の特徴を示すことにおこたりはなかった。このスピーカーの音は、たとえ多少のかげりがあるとしても、重くぼてっとはしていないので、このレコード『タクシー』におさめられているようなサウンドにもうまく対応できるということのようである。
ハーブ・アルバートのレコードも、好結果をおさめた。むろん、「ベサメ・ムーチョ」でリズムをきざむ深いひびきの提示には、無理があった。しかし、それとても、一応それらしく示した。したがって、音楽をはこんでいくリズムのきざみは、ききてに感じとれるわけで、音楽としてきいている分には、ことさら不満をおぼえなかった。つまり、そのことから、このKEFの303というスピーカーが、その音楽的まとまりをこのましく示すスピーカーということがいえるにちがいない。
大滝詠一のレコードでも、音がききての側に迫ってくる力は感じられなかったもの、すっきりした音場感を示し、大滝の声の特徴もよくあきらかにしていた。音のだし方にいくぶんひかえめなところがあるとしても、上品な音の、つかいやすいスピーカーのようである。
「世界一周スピーカー・サウンドの旅」
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
ウェストコースト的とか、イギリス的とか、はたまた日本的とか、ともかく的という言葉をつかって十把ひとからげにしてああでもないこうでもないと、わかった風なことをいいたててみても、本当ところはなにひとつはっきりしない。
実は、この的という言葉は、なかなかどうしてくせもので、あつかいがむずかしい。よほどうまくつかわないと、意味があいまいになってしまう。なんだこの文章は、なにをいいたいのかよくわからない──と思ったら、よくよくその文章をながめてみるといい。きっとその文章には、的、ないしはそれに類した言葉が、あちこちでつかわれているにちがいない。
そういうあいまいなところが的という言葉にはあるので、つかう方としてはつかいやすいし、安直につかってしまいがちである。たとえば、なるほどこの音はドイツ的だ──といった感じで、つかってしまいがちである。そのようにいわれた方としては、半面では、なるほどドイツ的なのか──と思い、残る半面では、実際のところ、ドイツ的とはどういう音なのであろう──と思うことになる。つまり、ひとことでいえば、わかったようでいてわからない。
それぞれのスピーカーには生れ故郷がある。アメリカのウェストコーストで生れたスピーカーもあれば、イギリスで生れたスピーカーもある。したがって当然(といっていいのかどうかはわからないが)、ともかく、生れ故郷のちがいが音のちがいに、なんらかのかたちで、影響している。いかなる理由でそういうことになるのかは、よくわからない。いろいろまことしやかな理由で説明してくれる人もいなくはないが、これまでに説明されて納得できたことは一度もない。
産地がちがえば、ミカンの味もちがう。これはあたりまえである。しかし、なんでスピーカーの音がちがうのであろう。スピーカーはミカンでないから、土地や気候のちがいがそのまま音に反映するとは考えられない。にもかかわらず、ウェストコーストのメーカーでつくられたスピーカーでは、誰がきいてもすぐにわかるようなちがいがある。
そのちがいは、否定しようのない事実である。ここでは、さしあたって、ちがうという事実だけを問題にする。なぜ、いかなる理由でちがうのかは、ここでは考えないことにする。さもないと、ことは混乱するばかりである。はっきりさせたいのは、どのようにちがうかである。
それぞれのレコードにも生れ故郷がある。ドイツで録音されたレコードもあれば、ニューヨークで録音されたレコードもある。このレコードについても、スピーカーと似たようなことがいえる。このことについては、多少なりともひろい範囲でレコードをきいている人なら、すでに確認ずみのはずである。さわやかだね、この音、やっぱりウェストコーストのサウンドだね──といったようなことを口にする人は多い。ここでは、そういうレコードの音とスピーカーの音を、ぶつけてみようと思う。ウェストコーストで録音したレコードをウェストコーストのメーカーでつくられたスピーカーできき、その後、故郷をちがえるレコードをそのスピーカーできいてみて、どのように反応するのかをききとどけてみようというわけである。
理想をいえば、ウェストコーストで録音されたレコードをいかにもウェストコーストで録音されたレコードらしく、イギリスで録音されたレコードはいかにもイギリスで録音されたレコードらしくきかせるスピーカーが、このましい。しかし、それはやはり理想でしかなく、多くのスピーカーは、なんらかのかたちで、そのスピーカーのお国訛りを、ちらっときかせてしまう。愛矯といえばいえなくもないが、つかう方からすれば、その辺を無視するわけにはいかない。いかなるもちあじを魅力とするスピーカーなのかをしかとみとどけてつかえば、それだけそのスピーカーを積極的につかえるはずである。
世間ではしばしば、クラシック向きスピーカーとか、ロック向きスピーカーといったような区分がおこなわれ、それはそれなりに多少の意味がなくもないが、ここでは、生れ故郷をちがえるスピーカーがどのようにちがう音をきかせるのか、その辺にポイントをおいて、きいてみた。
さしあたってここでは、さまざまなスピーカーに対して、「あなたは、どの国の出身のレコードの再生がお得意なのででしょうか?」と、たずねてみたことになる。スピーカーの答えは、さて、いかなるものであったか──。
ヤマハ NS-1000M, ビクター Zero-5 Fine
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
スピーカーで音の世界めぐりをしてきて、最後に日本のスピーカーを2機種きいた。そこでまず感じたのは、ともかくこれは大人の音だということであった。充分に熟した音であり、かたよりがないということである。立派だと思った。どの国出身のレコードでも、つつがなく対応した。ヤマハのNS1000MとビクターのZER05FINEでは、価格の差があるので、そのクォリティについては一概にはいえないとしても、おのれの個性をおさえて、それぞれの方法でさまざまな音楽に歩みよろうとしている姿勢が感じられた。大人の音を感じたのは、おそらく、そのためである。
とりわけ、ヤマハのNS1000Mは、立派であった。それぞれに性格のちがう音楽のうちの力を、しっかりと示した。ただ、たとえば、マーティ・バリンの歌の、粋でしゃれた感じをこのましく示したかというと、かならずしもそうはいえなかった。さまざまな面で、はきり、くっきり示しはしたが、独特のひびきのあじをきわだたせたとはいいがたかった。したがって、このマーティ・バリンだけを例にとれば、JBLのL112とか、あるいはボーズの301MUSIC MONITORの方がこのましかったということになる。ビクターのZER05FINEについても、同じようなことがいえる。
こうやって考えてくると、ヤマハのNS1000Mにしろ、ビクターのZER05FINEにしろ、日本出身のレコードでそのもちあじを特に発揮したわけではないから、外国のスピーカーたちとちがって、お国訛りがないということになる。お国訛りというのは、いってみれば一種の癖であるから、ない方がこのましいと、基本的にはいえる。ただ、場合によっては、そういうスピーカーの癖が、レコードの癖と一致して、えもいわれぬ魅力となることもなくはない。シーメンスのBADENのきかせたニナ・ハーゲンやクラフトワークのレコードの音がそうであり、エリプソンの1303Xがきかせたヴェロニク・サンソンのレコードの音がそうである。
癖があるのがいいのかどうか、とても一概にはいいきれない。同じ価格帯で比較したら、日本のスピーカーの多くは、平均点で、外国産のスピーカーを大きくひきはなすにちがいない。さしずめ、日本のスピーカーは3割バッターといたところである。そこへいくと、外国のスピーカーの多くは、ねらったところにきたらホームランにする長距離打者といるであろう。
ただ、この場合、ききてであるかぼくが日本人であるために、日本のスピーカーのお国訛りが感じとれないとういこともあるかもしれないので、はっきりしたことはいいにくいところがあるが、日本のスピーカーは、ドイツのシーメンスのBADENをドイツ的というような意味で日本的とはいいにくいように思うが、どうであろうか。
くりかえして書くが、、ヤマハとビクターのスピーカーは、大滝詠一やブレッド&バターのレコードもこのましくきかせたが、それと同じようにハーブ・アルバートやマーティ・バリンのレコードもこのましくきかせた。その意味で安心してつかえるスピーカーではあるが、きらりとひかる個性にいくぶん欠けるといえなくもないようである。
B&O Beovox S80
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
青い音とでもいうべきであろうか、すっきりした、透明度の高い音である。ほかの国のスピーカーからは感じとれない、独自の、しかし耳に心地よい音である。
レコードは、いくぶんこじつけめくが、アバの『スーパー・トゥルーパー』とパット・メセニーの『アメリカン・ドリーム』をきいてみた。そしてここでもやはり、なるほどと納得する結果になった。アバの歌は、いずれも、巧みなサウンド設計に支えられていると思うが、そのことがよくわかるきこえ方をした。それに、アバの歌では、歌い手たちの声がいくぶん楽器的にあつかわれていて、声そのものが。情感を背負うことはあまりないことも、ここでは幸いしていたようである。
たとえばヴェロニク・サンソンの唱などをきくと、エリプソンの1303Xできいた場合とまるでちがって、肌ざわりのつめたいものになる。その辺にこのスピーカーの特徴があるといえよう。ハーブ・アルバートのトランペットの音は、本来のあじわいとはすくなからずちがうが、あたかも涼風が頬をなでていったように感じられ、これはこれでわるくないと思わせた。
パット・メセニーのレコードでは、キーボードによる低い音が過度にふくらむことなく、このましかった。サウンドのフィーリングが音楽のフィーリングとぴったりあっていたようである。
エリプソン 1303X
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
ひとことでいえば、瀟洒なスピーカーということになるであろう。スリムなボディから、いかにもフロア型スピーカーならではの、たっぷりしたひびきがきこえてきた。音は、しなやかであり、ふっくらしていて、ソフトであった。
ここでは、ヴェロニク・サンソンのレコードと、ミッシェル・ポルナレフのレコードをきいてみたが、とりわけヴェロニク・サンソンのレコードのきこえ方が、すこぶる見事であった。インストルメンタルによるバックがもう少し鮮明であってもいいのではないかと思ったりしたが、声のなまなましさは、なんともはや驚くべきものがあった。
ハーブ・アルバートのレコードなどでも、音楽の切れあじの鋭さの提示ということでは多少の不満が残ったとしても、ひびきに独特のあかるさがあるで、音楽の性格をききてに感じとらせることができた。
しかし、このフランス出身のスピーカーは、ハードな音楽はあまりきかないで、きくのは女声ヴォーカルが多いというような人には、うってつけかもしれない。このスピーカーの音は、力でききてに迫る音ではなく、そこはかとない雰囲気でききてににじりよるような音である。ただ、にじりよられても、音の湿度は高くなく、ひびきとしてあかるいので、嫌味にはならない。
シーメンス Baden, ヴィソニック David 5000
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
シーメンスのBADENとヴィソニックのDAVID5000では、大きさも、それに価格も極端にちがうので、とても一緒くたに考えられないが、でも、ふたつとも、まぎれもなくドイツ出身のスピーカーであることが、一聴してわかる。その意味で、まことに特徴的である。ドイツのスピーカーをきくのであるからと、クラフトワークの『コンピューター・ワールド』とニナ・ハーゲンの『ウンバハーゲン』を中心に、ここではきいた。
シーメンスのBADENできいたニナ・ハーゲンは、圧倒的というべきであろうか、なんともすさまじいものであった。ききてに迫る音のエネルギーの噴出には、きいていてたじろがざるをえなかった。このレコードは、これまでにもいろいろなスピーカーできいているが、それらと、ここでシーメンスのスピーカーできいたものとは、決定的にちがっていた。リズムのうちだす音の強さは、さて、なににたとえるべきであろう。鋼鉄のごとき強さとでもいうべきであろうか。
クラフトワークのレコードできけた音についても、同じようなことがいえる。そうか、このグループはドイツのグループであったのだなと、あらためて思った。そういう音のきこえ方であった。音場的にかなりのひろがりは感じられたが、そのひろがった間をぎっしり強い音がつまっている感じであった。このスピーカーの音の力の示し方は、独自であるが、すばらしいと思った。
ところが、たとえば、ハーブ・アルバートのレコードなどをきくと、たしかに音の輪郭をくっきりあいまいにせずに示すあたりはすばらしいのであるが、このレコードできけるはずの本来の軽快さやさわやかさからは、遠くへだたったものになっていた。どことなくPA的になっているとでもいうべきであろうか、微妙なニュアンスの感じとりにくいはがゆさをおぼえた。
シーメンスのBADENというスピーカーの音の特徴は、あぶなげのない、そしてあいまいさのない、いうべきことをはっきりいいきったところにある。きいていて、すごいと思うし、それなり説得力もある。しかし、すべての音楽を、そしてすべてサウンドを、自分の方にひきつける強引さが、ときにうっとおしく感じられることもなくはないであろう。そういうことを含めて、たしかにドイツのスピーカーであると思わせる音をきかせたということになる。
小さなDAVID5000についても、似たようなことがいえる。コマーシャルを真似て、DAVID5000は小さなドイツです──などといってみたくなる。小さな身体にエネルギーがみちみちているといった感じである。よくもこの小さな身体からこれだけダイナミックな音をだすものであると感心した。クラフトワークのレコードなどでも、音楽的特徴は、一応つつがなくききてに示した。なかなかたいしたものである。
このDAVID5000の泣きどころは、声のようである。声が、概して、がさつきぎみであった。しかし、その一方で、ソリッドな音を、くずれをみせずに示しているのであるから、あまりないものねだり的なことはいいたくない気持である。
いずれにしろ、シーメンスとヴィソニックで、ドイツの人が好むにちがいない音の力を堪能した。
ロジャース PM110SII
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
重い音への対応ということでは、このロジャースのPM110SIIは、これまでのイギリス出身のふたつのスピーカー、スペンドールのBCIIとKEFの303と、かなりちがう。このスピーカーの大きさからは考えられないような低い、そして重い音がでるのには、感心させられた。しかも、ここで示される低音には、ぼけた感じがない。それがこのましい。
たとえば、デイヴ・エドモンズの『トワンギン』できける音楽の、敢えていえばロックとしての迫力とでもいうべきものは、実に見事に示した。そのかぎりにおいて、これは、これまでのイギリス出身の2機種にまさる。この表情の変化なども、大変になまなましく示した。ただ、問題がひとつある。表現の重心が中高域より中低域にかかりすぎているためと考えるべきか、いずれにせよ、シャカシャカいう音よりドンドンいう音の方が拡大されがちなことである。
きいてみたレコードの中で、特にきわだって結果のおもわしくなかったのが大滝詠一の『ロング・バケーション』であった。音像が拡大されがちなことと関係して、声そのもののなめらかさはあきらかになっているとしても、声は楽器の音にうめこまれがちで、きいていて重くるしさが感じられる。そいうきこえ方というのは、この音楽のめざす方向とうらはらのものといえよう。
似たようなことのいえるのが、ハーブ・アルバートの『マジック・マン』であった。ここでのきこえ方は、お世辞にも颯爽としているとは表現しがたいものであった。たしかに、低音のきこえ方などには独自ものがあり、アルバートのトランペットの特徴ある音色を巧みに示していたが、音楽がさわやかに走る気配を感じとらせにくいものであった。
本来なら、スライ&ロビーの『タクシー』あたりが、もう少し軽くきこえてほしいところであったが、音楽としてもったりしたものになってしまった。そのようなことから、このスピーカーは、いまのサウンド、あるいはいまの音楽、とりわけここできいたようなレコードにおさめられている音楽にはあわないスピーカーといえるのかもしれない。ご存じの方も多いと思うが、ロジャースのスピーカーは、総じて、クラシック音楽を中心にきく人の間に支持者が多い。たしかに、この腰のすわった、それでいてきめこまかいところもあるスピーカーの音が効果的なレコードもあることはわかるが、すくなくとも今回きいたようなレコードでは、ロジャースのスピーカーのよさがいきなかったといってよさそうである。
スピーカーの音としていくぶん暗めであるのは、イギリス出身のスピーカーに共通していえるわけで、このロジャースのPM110SIIについてもそことはあてはまるが、それに加えて、このスピーカーでは、もうひとつ音ばなれがすっきりしないために、全体としてさわやかさの不足したものとなったようである。
いまの音楽は、ウェストコースト出身のレコードできかれる音楽にしろ、イギリス出身のレコードできかれる音楽にしろ、一種の軽みを共通してそなえていると思われるが、その点での反応でいささかものたりなさを感じさせた。
スペンドール BCII
黒田恭一
サウンドボーイ 10月号(1981年9月発行)
特集・「世界一周スピーカー・サウンドの旅」より
このスペンドールのBCIIというスピーカーは、しばしばクラシック向きといわれる。たしかに、このスピーカーのもちあじであるきめこまかさは、繊細さを求めるクラシック音楽をこのましくきくのに、うってつけである。それに、SS編集部の良識派のMくんがいみじくもいったことであるが、おそらくこのスピーカーをつくった人たちは、ここで試聴につかったようなレコード、たとえばデイヴ・エドモンズの『トワンギン』のようなレコードは、きいたことがないにちがいない。しかし、デイヴ・エドモンズの『トワンギン』の中には、1968年にロンドンで録音された曲が収録されている。そうなれば、今回の意図からして、ここできいてみることになる。
それで、結果はどうであったかということになるのだが、納得できる音をきくことができた。なるほどと思えた。デイヴ・エドモンズの音楽をパブ・ロックといっていいのかどうかはわからないが、この音楽の、あかるくはれやかになりようのない性格を、なかなか巧みに示した。ひびきのスケールがきわだって大きいとはいいがたいが、それなりの音楽の力感といえるようなものは提示したというべきであろう。
これはイギリス出身のスピーカーに共通していえることであるが、サウンドは、いくぶんうつむきかげんで、多少暗い。その多少の暗さが音に陰影をつけることにもなっているようである。
このスペンドールのBCIIを、たしかにイギリス出身のスピーカーであると思ったのは、イギリスで録音された、つまりイギリス出身のレコードをきいたときでなく、むしろアメリカのウェストコースト出身のレコード、たとえばハーブ・アルバートのレコードなどをきいたときであった。アルバートのトランペットの音は、かげりの中にあった。エレクトロボイスのスピーカーできいたときほどの違和感はなかった。その辺がイギリスのスピーカーの興味深いところである。レコードヘの歩みより方が巧妙である。
それぞれのレコードがきかせる音楽の「らしさ」への対応がうまいということになるであろう。
スライ&ロビーの『タクシー』のようなレコードにしても、乾ききらないどことなく湿りけを残したひびきを、ききてに感じさせるような音をきかせる。ひびきは、再三書いているように暗く、多少の湿気もあるのであるが、ついに重くひきずったようにならない。つまり、ある種の軽みの表現にもすぐれたところがあるということである。
そために、このスピーカーは、いまの時代のサウンド、あるいは今様な音楽にも、無理なく対応しているとみるべきであろう。このイギリス出身のスピーカーは、なかなかどうしてヤング・アット・ハートである。一応ものわかりもよく、それなりの実力をもあり、気分的に若いとすれば、つかう方からすると、気をつかわないでつかえるということで、それはむろんスピーカーとしては美徳である。
このスピーカーには、もうひとつ、このましいところがある。おそらく、ひびきのきめのこまかさに関係してのことと考えるべきであろうが、言葉のたちあがりが鮮明である。歌を中心にきく人にはうってつけのスピーカーといえるのではないか。
ダイヤトーン DS-503
井上卓也
ステレオサウンド 60号(1981年9月発行)
「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より
コーン型ウーファーの振動板材料に早くからハニカム構造振動板を採用したダイヤトーンの技術は、これを発展させアラミドハニカム振動板とダイアフラムとボイスコイルボビンを一体成型をする新技術によるボロンのドーム型ユニットを組み合わせた大型4ウェイブックシェルフ型システムDS505を昨年登場させ、デジタルオーディオ時代に対応するスピーカーシステムのありかたを提示し、反響を呼んだ。今回は、この設計方針に基づく第2弾製品として、3ウェイ構成のブックシェルフ型システムDS503が発売された。
システムとしての特長は、従来からブックシェルフ型の高級機種には完全密閉型エンクロージュアを採用する伝統があり、これがダイヤトーンの特長であったわけだが、本機では初めてバスレフ型が採用されている点が目立つ。エンクロージュアは、包留柄接ぎ方式を採用し、ポート部分にはアルミパイプダクトを採用しているのが特長。
ユニット構成は、新スキン材採用の32cmウーファーをベースに、ダイヤトーン・ユニファイド・ダイアフラムと名付けられた一体成型型直接駆動振動板採用で、新設計の65mmボロンドーム型スコーカーと同構造の23mmボロンドーム型トゥイーターの組合せである。ダイヤトーンDUDユニットの他の特長としては、ハードドーム型で一般的な手法である振動板の内側に制動材などによるダンピング処理がなく、そのうえ振動板前面のイコライザーもない設計があげられる。この利点は、アンプ関係の裸特性を向上してNFB量を少なくする設計と共通点がある。前面に障害物がなく、フリーダンプの振動板によるダイナミックで活き活きとした再生能力は、DUDユニットの隠された特長であり、魅力である。
ネットワークはスピーカーシステムの成否を握る重要なポイントだが、本機では圧着方式配線と2分割型新固定方法の採用で、単純な従来の固定方法とは一線を画した成果を得ている。
DS503は、床から30cm程度の台に乗せて最良のバランスとなる。低域は豊かで紙独特のノイズがなくクリアーである。中域のエネルギー感はたっぶりとあり、インパクトの強烈な再生能力は凄い。音の表情は505よりフレキシブルで親しみやすいが、併用装置による変化はかなり大きい。
「でも、〝インターナショナル〟といっていい音はあると思う」
瀬川冬樹
ステレオサウンド 60号(1981年9月発行)
特集・「サウンド・オブ・アメリカ 憧れのスーパー・アメリカン・サウンドを聴く」より
全試聴が終らないうちに不本意ながら入院ということになってしまいまして、聴けないシステムが何機種か出て、最後の総括の部分のみなさんのお話に加われなかったために、お三方のご意見をいちおう読ませていただいたうえで、私個人の感じたことを談話でしゃべらせていただきたいと思います。
まず、今回のテーマの〈アメリカン・サウンド〉ということについて、二、三、申しあげておきたいんですけれども、私自身がここ数年来、スピーカーの音の分類をするためには、第一に、その音の生れた風土・地理、第二にその音を生んだ時代、あるいは世代、第三に技術的な進歩、という、まあ大きくわけて三つの座標軸でとらえるようにしている。
そういう意味では、西ドイツや日本のような小さな国がひとつの地域としてとらえられるにしても、アメリカという国はあまりにもひろい。お三方がそれぞれのかたちで指摘しておられるように、アメリカという国を,ごくおおまかに分けたとしても、東海岸があり、西海岸があり、そしてシカゴを中心とした中部といったような三つの地域にわけて考えなくては片手落ちになるわけで、〈アメリカン・サウンド〉と一括して論じることにはやや無理があるんではないかという気がまずいたします。
次の第二の点として、これは岡先生が発言しておられるように、アメリカのスピーカーの発達の歴史をたどっていきますと、アルテックに代表されるトーキー・サウンドから発生した音と、もうひとつはパナロープを例にあげておられたような家庭用の電気蓄音機から発生した音という、まあごく大ざっぱなわけかたであるにしても、ふたつのちがいがあるこのこと自体も、一括して論じるというわけにはなかなかいきにくい、ひとつの要因ではないか、と思います。
第三点として、とくに時代、あるいは世代のちがいとなると、これもお三方がそれぞれに指摘しておられるように今回試聴し得たスピーカーのなかでも、アルテックのA4を古いほうとして、新しいほうでは、たとえばインフィニティに代表されるところまで、アルテックの原型から考えれば、半世紀ぐらいも時代がはなれているわけで、その点でもなかなか〈アメリカン・サウンド〉という一言で一括しにくい部分がある、というように私は考えました。
以上の点を前提としたうえで、しかし、私自身が個人的に考えている〈アメリカン・サウンド〉というイメージ、あるいは〈アメリカン・サウンド〉という言葉を聞いたときに、とっさに思い浮かぶこと、をもうすこし具体的に述べてみます。菅野さんが発言しておられたと思うんですけれども、やはりアメリカのよき時代ですね。たとえば第2次大戦以前の30年代、それも30年代後半から、それと第2次大戦の終った50年代、のふたつの繁栄した、ゆたかであった時代に代表される、そういうものをやはり〈アメリカン・サウンド〉というふうに受けとめてみたい、という気がするわけです。
それを具体的に言いますと、たとえば、アメリカの自動車でいえばキャディラックのような大型の、大排気量の、車にのったときの乗り心地のよさのような、ぜいたくに根ざした快さ、、快適さ、いかにもお金がかかっているという、そういうところが、まず第一に、第二に、同じようなことですけれども、音のリッチネストいいますか、音がこよなく豊かである。第三にははなやかさ、一種独特のきらめいた、はなやかなサウンド。第四に音の明るさ──どこまでも、くったくなく、朗々と鳴る気持のよさ、だいたい、そんなような音を私個人は、どうしても思い浮かべてしまう。
そして、それを具体的な音、スピーカーにあてはめてみると、やはり、古い世代のアルテックに代表されるものではないか、という気はいたします。
もうひとつ私は前期の理由によって、試聴には加われませんでしたけれども、ほかで何度か聴いた音で言えば、エレクトロボイスの音ですね。これも上手に鳴らしたときの音というのは、以上、申しあげたような各要素が、やはり聴きとれるんではないか、という気がします。
またJBLのパラゴンであっても、そして今は製造中止になってしまったハーツフィールドであっても、やはり、お金を充分にかけた、そこからくる、ゆたかで、明るく、はなやかである、という音をやはり持っていると思うので、そういうのは、やはり〈アメリカン・サウンド〉だろう、とはっきり言ってよろしいかと思います。
さて、次の問題にうつるまえの簡単な補足をつけ加えておきますと、以上のようなスピーカーは本質的な意味でのワイドレンジではないのではないか。たとえば、いまあげた、ハーツフィールド、パラゴン、パトリシアン、これらは、それぞれの時代では、たしかに、アメリカのスピーカーのなかでのワイドレンジの製品であったにちがいないけれども、しかし、同時代に、これは今回の話題ではないけれども、たとえばイギリスがモニタースピーカーなどで追求していた、ほんとうの意味でのワイドレンジとは、ずいぶん質のちがっている、耳にきこえる感じというのは、いわゆる「ワイドレンジ、ワイドレンジした」音ではなくて、たとえば、プログラムソースのアラなどが耳につきにくいというような音、あるいは、それに関連して、ノイズや歪みを極力おさえて、まろやかに、つまり、さきほどの話によれば、ぜんたくな、快適さといいますか、そういうものをやはり信条としていた、というふうに思います。それが私の考える〈アメリカン・サウンド〉です。
さて、私がJBLの4345の試聴のところで、やや不用意に〝インターナショナル・サウンド〟という言葉を使ってしまったために、あとで総論の部分を読ませていただきますと、お三方の誤解をややまねいたような気がいたしますので、そのことについて、補足をさせていただきたいと思います。
たとえば、JBLでも、今しがた例にあげたパラゴンにせよ、それから、それとは、また、まったく方向のちがう4676システム、といったような音になりますと、これは、やはり、私はアメリカならではの音、アメリカ以外の国では決して生れることのないサウンドだと思います。
そして、私が〝インターナショナル・サウンド〟という言葉を使った、その使いかたがやや不用意だったために、誤解をまねいたようです。この場合、言葉の意味にあまりこだわってもらっては困るわけです。常日頃、私がスピーカーを論じる場合に、一貫して主張し続けてきたことですけれども、世界的な音の流れとして、たとえば10年という時間をさかのぼってみますと、当時はまだ明らかにイギリスの、たとえば、やや線の細い、繊細な音、ドイツのコリッとした音、アメリカの華麗な音、といったようなわけかたが、はっきりできた。それに対して、近年の、ことにそれは技術的な進歩によってスピーカーの特性の解析の技術がたいへんすすんだこと、そして、もうひとつは、プログラムソースを作る側、もっとさかのぼって言えば、音楽を演奏する側、などの感覚的な変化、楽器の変化なども含めて言えることですけれども、音楽的に正しく再生するには、指向特性を含めての、真の意味でのワイドレンジであり、歪あを極力すくなく、トランジェントをよく、そして、位相特性までも含めた平坦な特性、物理的な意味で、理想に近い特性を各国のメーカーとも目指しはじめた。
目指しはじめたことによって、各国から数多く作り出されるスピーカーのなかで、そうした条件をみたすことに、からくも成功したスピーカーの音というものが、だんだん、ひとつの地域の独特のサウンドではなくて、国際的に、あるいは、みなさんのお話のなかの最後に〝コスモポリタン〟という言葉が出ていましたが、このほうが適当か、という気もいたしますけれども、そうしたように、特定の地域の、あるいは特定のジェネレーションのカラー、特定の技術によるカラーといったものが、だんだんうすめられてきて、音のバランスとか音の鳴りかたが、たいへんよく似てきているということを申しあげたいわけです。それを特に私が、JBLの4345のところで申しあげたのは、今回、試聴に用意されたそれぞれのスピーカー、および今回は種々の理由によって用意できなかったアメリカのスピーカーを全部ふくめたうえで、やっぱりJBLの4345というのは、とびぬけて、物理特性を理想に近づけることに成功した、数少ない例のひとつだということを言いたかったために、〝インターナショナル・サウンド〟などというような、言葉を使ってしまったわけです。
で、ありながら、菅野さんや、ほかのかたのご指摘にありますように、私が、それだから、JBLが無国籍のスピーカーだと言おうとしているのでは決してなくて、あくまでも、これはJBL製であり、アメリカの西海岸製のスピーカーであり、そのことは、百も承知のうえで、アメリカが作り得た、〝コスモポリタンな〟あるいは〝インターナショナルな〟音、ということを言いたかっただけの話なのです。アメリカのそれ以外のスピーカーというのは、たとえばアルテックのA4に代表される、アメリカの古き良き時代のトーキー・サウンド、あるいは、インフィニティに代表されるようなアメリカの古い伝統を全く断ち切ったところから生れてきた、まったく耳あたらしいサウンドといったようなものが、オーバーに言えば、無数にあるわけです。そういう点で私は、JBLの4345をのぞいたそれぞれのスピーカーというのは、やっぱり、アメリカの国のそれぞれの地域、世代、技術、そしてそれらをふくめた音を求める傾向、といったものが、はっきりと現われていると思う。それか今回試聴に参加して、たいへん興味ぶかく感じたことです。
多少個人の発言につっかかような言いかたになるんだけど、菅野さんが「あいつは自分の考えている音の世界があって、それを〝インターナショナル・サウンド〟だと思っている、ということは不遜である」と、いうようなたいへん、きつい発言をなさっている。
まあ、菅野氏とは個人的に仲がいいから、あえて、すこし売られたケンカを買わせていただくけれども、私は決して自分の考えている音が即〝インターナショナル〟だとは思っていません。
ですから、決して、もちろん私自身の音の世界というものは確固として持っているけれども、それをインターナショナルなどと思うどころか、それはもう、私の鳴らしかた、私の音の世界だというふうにわり切っているわけです。それと、客観的といいますか、要するにその主観的な要素が入らない物理特性のすぐれた音、そういったものを〝インターナショナル〟ないし〝コスモポリタン〟と言っていいのだろうと思うので、傲慢と言われたことについては、私は、とんでもない、と一言抗議させていただきたい、と思います。
タンノイ GRF Memory
菅野沖彦
ステレオサウンド 60号(1981年9月発行)
「現代に甦るタンノイ・スピリット〝GRF MEMORY〟登場」より
現代に甦るタンノイ・スピリット〝GRF MEMORY〟登場
イギリスのタンノイ社から新製品が届いた。新しいモデルの名は、〝ガイ・R・ファウンテン・メモリー〟と呼ばれ、いかにも伝統に輝くタンノイ社の製品にふさわしい風格と緻密なつくりを見せている。ガイ・R・ファウンテンとは、いうまでもなく、タンノイ社の創設者の名前で、オートグラフという同社のトップモデルやGRFシリーズを通して、タンノイファンには親しみ深い人である。そして、今は亡きこのファウンテン氏を偲ぶモデル名がこの製品につけられているわけだが、これが単にネイミングに止まらず、製品の総合的なつくりに、その雰囲気が溢れていることは誰の眼にも明らかであろう。
クラシックなたたずまいを見せる〝ガイ・R・ファウンテン・メモリー〟とはどんなスピーカーシステムか? 三つ折り頁の「ビッグサウンド」のグラフィックと共に、立体的に、その全貌をお伝えしようというのが、今号の〝タンノイ研究〟のテーマである。
内容積220ℓのエンクロージュアは、高さが1メートル10センチ、幅が80センチ、奥行きは48センチという大型フロアーシステムで、バスレフレックス方式を採用している。このサイズは、受注生産のオートグラフ・レプリカを除けば、現在のタンノイのシステムの中で最も大きく、GRFモデルを一廻り小さくしたディメンションである。ただし内容積だけに限れば、スーパーレッドモニターやクラシックモニターの230ℓより10ℓ小さくなっている。
内蔵ユニットは、クラシックモニターに使われているK3838のスペシャル・ヴァージョンで、38センチ口径のデュアル・コンセントリック(同軸型2ウェイ)であるが、ネットワークは新設計のものだという。いうならば、最新のタンノイのテクノロジーを、伝統的な雰囲気とつくりをもった意匠で包んだもので、タンノイ社の力を十二分に発揮した入念の作品といえそうだし、その重厚な姿態と緻密で周到な細部のつくりには、今時のスピーカーらしからぬ風格を感じさせるものがある。あえて、今時のスピーカーらしからぬと書いたけれど、これは重要な問題であり、このシステムの価値の重さを語るのに触れぬわけにはいかない要素だと考える。
大型フロアーシステムの数は決して少なくないけれど、新しい製品に一様に感じられる淋しさは、そのデザインとつくりに、往年のそれらの製品に見られたような家具としての美しさや風格が感じられなくがなったことである。高級機である以上、音に、非常に大きな影響力をもつエンクロージュアに、音響的、あるいは剛性などの点では充分な考慮がなされているとはいえ、それを超える工芸的な美を感じさせてくれる新しい製品が少ないことは万人の認めるところではないだろうか。高度な音楽芸術鑑賞のための道具である高級スピーカーシステムに、家具調度としての高い仕上げと風格を要求することは決して本質からはずれたことではなく、むしろ当然な要求だと私は思っている。それにもかかわらず、現代の合理的な産業システムは、これらの要求を満たす能力を失いつつあり、できたとしても、いたずらにコストアップを理由に、本気になって工芸的仕事に取組もうとはしなくなってしまった。もちろん、これは、オーディオ機器に関してだけの話ではなく、私たちの身の廻りのすべてにいえることだろう。現代人の美意識は一体どうなってしまったのだろうとうたがわざるを得ないのである。新しいものは味気がないなどの一言で、あきらめてよいはずはない。
余談だが、私は、日本が世界に誇る、あの新幹線の駅を見るたびに、なんともやりきれない気特にさせられる。あのペラペラの倉庫のような建造物には美も文化も全く感じられない。コストを抑えて、必要な機能と安全性を考慮すれば、ああならざるを得ないというようなことは承知であるが、あれほど大きな建造物は、周囲の景色を大きく色付けるに充分な存在で、大げさにいえば、その国の文化を象徴せざるを得ない重要な建造物であるはずだ。もし、あれをニューデザインだというのなら、なにをかいわんやである。金属とガラスでできた現代のバラックではないか。どう見ても仮設駅含程度にしか私の眼には映らない。
古い建物が機能的に不備で、安全性にも欠けていることはよくわかる。しかし、少なくとも、美と風格の点では比較にならないほど立派なものが沢山あった。東京駅の丸の内側の駅舎と、八重洲口側駅舎を比べても、それは歴然としている。オランダのアムステルダム駅をモデルとしたといわれる、あの古い駅舎も、国鉄が大赤字をかかえていなければ、とっくに建て直されていたことだろう……。ヨーロッパの古い教会や駅も同じ運命にあるけれど、100年後、200年後の人々への遺産として、今のような建造物を残して平然としていられるのだろうか。20世紀後半に、当時の人間達は、それまでの文化を受け継がず、全て破壊し堕落させたと後世の歴史に書かれることだろう。そして、それと引き換えに、人類を危機に陥れる機械文明を手に入れたことが、果して、どれほど評価してもらえるだろうか? 〝古きを尋ねて、新しきを識る〟などという格言は、今の世の中には通用しないのであろうか。
古いものがよいといっているのではない。新しいものの全てが悪いというつもりもない。歴史は連綿と繋げなければいけないといいたいのである。知的な革命は決して破壊であってはいけないのである。それが誤ちであることは、中国の文化大革命が証明している。国家社会の下部構造としての政治経済が、上部構造の文化文明を脅かしては、本末転倒である。
少々、話しが横道にそれでしまったが、現代社会への不安は、オーディオ機器のあり方にも読みとれるものだということをいいたかったのである。高級スピーカーシステムに話しを戻そう。
現在、手に入れることのできる(お金があればの話しだが)大型高級システムの中で、こうした不満を感じないですむものがどれほどあるだろうか? 好き嫌いは別としても、その数はしれたものだ。そして、それらのほとんどは旧製品のロングランとして作り続けられているもので、中には、要望によって限定再生産(たいていの場合、質は大きく低下している)されたものである。これらの中でのベスト・ワンを挙げろといわれれば、私は躊躇なく、JBLのパラゴンをとる。あのパラゴンの独創性、美しい姿、立派な風格は、多くのスピーカーシステムの傑作の中でも水際立っている。あれは、新しさも古さも超越したデザインと見事な作りであり、驚くべきことに、どんな環現においても、環境負けすることがない。クラシックなインテリアの中でも、モダーンな部屋にあってもだ。大抵の場合、我々の部屋の方が負けてしまう。負けるどころか、置くスペースが確保できない場合が多い。スペースがあれば、これを置くだけで、部屋の中は立派に見える。部屋がかえってみすぼらしく見える場合もないではないが、オーディオが好きならば、そうはならない。逆に、金がかかっていても、趣味の悪い装飾調度品が多い場合に、とんちんかんになる場合が多いだろう。むしろ、他に何にもないほうがよいくらいだ。
他に、これに匹敵するものといえば、かつての見事な蓄音器たちを除けば、同じJBLのハーツフィールド、昔のエレクトロボイスのパトリシアン・オリジナル、パトリシアン600、タンノイのオートグラフ、GRF、現在買えるものなら、パトリシアン800の再生産モデル、ヴァイタヴォックスCN191コーナーホーン、クリプシュホーンK-B-WOぐらいまでが、どうやら許容できるものといったところだろう。
モダーンデザインなら、JBLの各システムをはじめ、むしろ国産につくりのよいものがあるが、この辺になると風格といった領域にはほど遠い。私が現在夢中になっているマッキントッシュのXRT20などは、大変よくできたエンクロージュアだが、なんとも夢のない雰囲気で、家具としての美しさは薬にしたくともないといえる。機能本位のさっばりしたところが、うまく部屋に合えば消極的で厭味がないといった程度である。
こんなわけで、大金を投じて買った高級スピーカーシステムにふさわしい、所有の充足感とでもいった気分を満してくれるものは今後、ますます少なくなりそうな気配である。こうした背景の中で登場した今回の〝ガイ・R・ファウンテン・メモリー〟は、たしかに目を引く存在感のあるシステムだと思う。かといって、芸術的な工芸品と呼ぶには、いささか、プロポーション、仕上げ感覚に注文をつけたい点もあるし、やや不自然ともいえる意識の出過ぎに、わざとらしさも感じられる。本物はもっと、巧まざる自然の姿勢から生まれなければいけないとは思うのだが、それにしても、現時点でこれだけのものを作り上げたタンイの情熱と力には敬意を表したい。
SRMシリーズやバッキンガムがスタジオモニターとして作られたのに対し、このGRFメモリーは純粋にホームユースの高級システムとして作られたものであることは明白である。しかし、モニターとはいいながら、SRMやバッキンガムのエンクロージュアのつくりも、間違いなく現代第一級のレベルにあることを認めるし、このGRFメモリーには現代版としては、特級の折紙をつけざるを得ない。これだけ手のこんだエンクロージュアは、条件つきとはいえ、その美しさと風格を含めれば、少なくとも80年代の新製品では他にはないものだから。
では、このGRFメモリーについて、少し詳しく述べることにしよう。横幅も充分にある縦型プロポーションのシステムの仕上げはオイルフィニッシュのウォルナットであり、背面などの構造材には25ミリ厚の硬質パーティクルボードが使われている。トップボードがひさしのように張り出しているのが大きな特長といえるが、私の個人的なバランス感覚では、やや出っ張り過ぎのように感じてならない。機械加工かもしれないが、エッジの随所はテーパー状に仕上げられた手のこみようで、細部の接合は留めに決めているところなどは、感心させられる。
後面からバッフル前面にかけて、左右対称にしぼりこまれた梯形は、オートグラフ、GRFシステムのフロント・イメージと共通のものだ。したがって、バッフル面は、全横幅よりかなり狭くなっていて、このシステムの形状に立体感をもたせている。ディフラクションを避けるために左右を後方斜めに切り落とした恰好だ。この斜めにそがれた部分にバスレフのポートが設けられているが、表面はバッフル面と同一のサラングリルで被われている。
フロントグリルは鍵つきのロックで固定されている。オーナーには、ゴールドに輝く鍵が渡されるわけだが、これをリリースして、サランのグリルをはずすと、そこにはまた美しい光景が展開する。38センチ口径の堂々たるユニットのコーン紙にはガイ・R・ファウンテンのオートグラフ(自署)が金色にプリントされ、ユニットの取付けられたバッフル面はコルクで貼りつめられているのである。見た目にも大変美しいしユニークであるが、コルクの音響材としての効果も無視できないのではなかろうか。このバッフル前面、左右の斜面は共に美しくフレーミングされていて高い精度の木工技術がうかがわれる。また、フロントグリルには、あのガイ・R・ファウンテンのオートグラフがエングレイヴされたバッジが、それも木製の台座を介して取付けられているという手のかかり具合である。内部は、バッフルボードと背板が井桁状の角材で補強され、高い剛性を誇っている。
隅々まで周到に仕上げられたこのシステムには、タンノイ社の情熱と執念のようなものさえ感じさせられるし、あの経済的に決して好況とはいえない英国で、よく、これだけのものを作ったものだと感心させられるのである。確定的な価格は、本稿執筆の時点では発表されてはいないが、60方円前後だということだ。もしそうならば、これは決して高い買物ではないだろう。仮に、この大きさと、この手の込んだ細工のサイドボードを買えば、そのぐらいの値段はする。否、輸入品となれば、この値段では買えまい。そう、そう、忘れていたが、ネットワークによるロールオフとエナジーのコントロールのツマミまでが、ムクの木の削り出しだった。とにかく徹底的なのである。関係者の熱意には脱帽である。
ところで、そろそろ、肝心の音ついて記さねばならないが、今回も従来のこのタンノイ研究シリーズと同じように、具体的に数種のアンプを使っての試聴を行った。以下、ドキュメントという形でリポートさせていただくことにしよう。
8月中旬、一組のサンプルが本誌の試聴室にセットされたということで試聴に出かけた。写真を見せられただけのGRFメモリーである。どんな音が、あの優雅な姿態から流れ出ることかと、いささか興奮気味であった。
タンノイのほとんどのシステムを聴いている私にとって、この新製品に寄せる期待は大きいものがあった。すべて、デュアル・コンセントリックのユニットを使いながら、システム毎に微妙にちがう表情の豊かなタンノイの鳴り方は、全製品に一貫して聴かれる、あの充実のサウンド故に、まことに興味深いものがある。オートグラフ、GRF、 コーナーヨーク、 レクタンギュラーヨーク、IIILZ、アーデン、バークレイ……、そして、バッキンガムモニター、スーパーレッドモニター、クラシックモニター、SRM15X、12X、12B、10Bと、ずい分沢山のタンノイたちを聴いた。そのいずれもが紛れもないタンノイでありながら、それぞれの響きをもって鳴った。鳴っている場所でも、がらがら鳴り方が変った。アンプやカートリッジによっても豹変した。それだけではない。私はもっと不思議な体験もしている。話しが艮くなって申し訳ないが、これは是非、お話ししておきたいことだから、この機会に書くことにする。
あれは、今年の5月14日のことであった。束京のオーディオ販売店Dの主催するタンノイ・オートグラフの試聴と講演での出来事である。話しを正確にするため、ダイナミックオーディオの主催する第4回マラソン試聴会でのことだといい変えよう。会場は、赤坂のホテル・ニュー・ジャパンであった。私の受け持ったオートグラフの講演と試聴会は、夕方5時からだったが、その直別まで他の催しがあって、セッティングには全く立会えなかった。
開演5分所に会場の席についたときには、大きな宴会場の正面にオートグラフが据えられ、プレーヤー、アンプ類(私の指定のもの)も既に結線されていた。熱心なファンも50名ぐらい、もう備についていた。スタート直前、係の一人が、「こんな会場なもので、どうも、いい音は出ませんが……、ええ、かなり厳しいようで……」と、口ごもりながら私に耳打ちしてくれた。どう厳しいのか判然としなかったけれど、決して良い意味にとれなかった。こういう催しの常である。そのスピーカーの能力の60%から70%発揮されれば最高といってよいだろう。しかし、この感じだと50%にもいかないなと私は直感した。そりゃ、当り前だ。コーナータイプのオートグラフは、部屋の壁面をホーンの延長として使うように設計されている。ところが、その場のオートグラフときたら、コーナーはおろか、左右、後方に数メートルの距離のある状態。しかも宴会場は薄手のペニアの間じきりで、どこを見ても、いかにもボコン、ポコンといった感じであるから、とてもとても、まともな音など期待するほうが無理というものだろう。実は、この会場で、前年にもタンノイの講演をしたのだが、その時鳴らしたのは、スーパーレッドモニターだった。これはオートグラフとちがって、よりコンベンショナルなバスレフ・エンクロージュアだから、まだなんとかなったものだったが、今度は最悪だ。
こういう催しで、精一杯話した後で出した音が、話しとは似ても似つかぬ音だった時には、穴があったら入りたくなるほどつらいものなのである。何をいっても言い訳にしかならないだろうから、じっとこらえて、苦々しく音を聴いている他はない。寿命が縮む思いである。レコードは余裕をもって選んではあるが大幅にカバーするわけにはいかない。私は覚悟を決めてし講演を始めた。いっそのこと2時間しゃべり続けてしまおうかとさえ思ったほどだ。さあ、もうこうなったら念じるより他はない。あのカートリッジで、あのアンプで、本当ならあの音がするはずなのに……と、もう、半ベソの有様。心で泣いても顔では何とやら、つとめて冷静に、快活に、ずるずると40分ほど話し続けた。もう駄目だ。そろそろ鳴らさなければ……。前列の熱心なファンの表情も、そろそろ音に飢えてきた様子。「伝統に輝くオートグラフの音は……」という私の言葉に、生ツバをゴクンとのんでいるではないか。隣りの青年は、早く鳴らせといわんばかりにノビをして、眼鏡越しに私の顔をチラリ! 絶体絶命である。オートグラフよ頼む! 鳴ってくれ! お前のあの音を出してくれ! カートリッジにも、アンプにも、私は同じ願いをこめてレコードをターンテーブルに載せたのであった。リハーサルがないから、音量からしてボリュウムの位置では見当がつかない。日頃のカンを働かせ決めた。古い録音からスタート。ピエール・モントゥ一指拝ウィーン・フィルのハイドンの交響曲「時計」である。
おおっー、いい。いいではないか。しなやかな弦。ウィーン・フィルらしい艶。豊かな中~低音の響き。これなら、ひかえ目にいっても70点。次に小編成で、ヤニグロとソリスティ・ディ・ザグレブの演奏。これもなかなかの鳴りっぶり。気をよくした私の話しも、一段と熟っぼく滑らかに進みだす。お客の眼も輝きだした。盛んにうなづいてくれる人もいる。時たま首をかしげる奴もいたけれど(気になるもんですよ、そういう人)……、そして遂にラストナンバー。比較的新しい録音の一枚として、ミケランジェリのピアノ、ジュリーニの指揮するウィーン・シンフォニーの演奏でベートーヴェンのピアノ協奉曲第1番をかけた。堂々たるオーケストラのソノリティ、輝かしいピアノが圧倒的な盛り上りを演じたのだった。
私も、ファンの人達も、スピーカーと一体となって熟っぽく燃えているのがよくわかった。終るやいなや、数人のファンから歓声が上った。「よかった!」と大声で叫んだ人もいた。その場の人々が全員、満足し、感動したことは、確かな実感として私に伝わった。口々に礼をいって去っていくファンの人たちの表情にもそれがあった。そして、係のスタッフたちが、まるで孤につままれたような表情で「先生、何をしたのですか?」と私に聞くのだった。「信じられないなあ……。直前まで様にならないひどい音だったのに……」。そして、ファンからも同じ言葉が述べられた。また、この催しの前の催しを担当していた他メーカーの人の驚きようはもっと凄かった。「アンプが暖まったなんていうもんじゃないですよ、あの変りようは! 装置をそっくり入れ替えたようだった」というのである。
理由は、私にも判らない。しかし、このような劇的なハプニングとまでいかなくても、これに類した体験はいくらでもある。
実をいうと、ガイ・R・ファウンテン・メモリーに関しても、これに近い体験をさせられたのであった。
本誌の試聴室でのガイ・R・ファウンテン・メモリーとの初対面は、不幸にして、決して素晴らしいものではなかった。
試聴には、エクスクルーシヴのP3プレーヤーシステム、カートリッジはオルトフォンのMC20/II、コントロールアンプはマッキントッシュのC29、パワーアンプは同MC2500という組合せで、まず音を出した。聴き馴染んだハイドンのシンフォニー「軍隊」(ネヴィル・マリナ一指揮)の第1楽章の序奏を聴いただけで「驚愕」とまでいかずとも、愕然とした。鋭く硬く、とげとげしい弦の音。ステレオフォニックに、ふくよかに拡がるはずの空間のプレゼンスは、2チャンネルに二分され、音が左右のスピーカーの位置にへばりついたままではないか? こんなはずはない。だいたい本誌の試聴室は、きかに製品テスト用の試聴にふさわしく、すべてのスピーカーが楽しく聴けるというよりは、アバタもエクボもさらけ出す傾向にあるのだが、それにしてもひどい。タンノイ研究のシリーズだって、第1回は別として(ティアックの試聴室)、その後はずっと、ここで聴いてきたのである。SRMもクラシックモニターも、アーデンも、かなり楽しく聴けたのである。
なんとかならないものかと、まずカートリッジを交換してみた。ゴールドバグのブライヤーをつけた。このカートリッジのしなやかな高域と豊かな中低域によって、かなり聴きよい音にはなったものの、とても、期待にそうものではない。アンプを変えた。前回までのこのシリーズの実験の結果、タンノイのスピーカーとのベスト・マッチングとして私が推薦したコントロールアンプのウエスギU・BROS1とパワーアンプのオースチンTVA1を試みた。さらに一段と向上はしたが、まだ、私のタンノイのイメージからは、ほど遠い。そこでパワーアンプもコントロールアンプと同じく上杉研究所のU・BROS3を2台、パラレル接統にして使ってみた。この方が、また一段と音がまとまってきたが、それでも決してかつてSRMやクラシックモニターから得られた音の水準には至らなかった。
私のコンディションのせいかと、自らを疑ってもみたが、立会いの編集部のM君もS君も同じょうに浮かぬ顔つきである。これは困ったことになったと一同呆然。置き方やレベルコントロールもさわってみたが効果なし。バランスだけではなく、音の質感が悪いのである。歪みっぽくさえあるのだ。なんだかんだと数時間を費したけれど、うまくいかないので、日を変えようということになったのである。そこで翌週、再度挑戦ということで当日は終了ということにした。
さて、週は変り、再度挑戦である。今度は場所をティアックの試聴室に移した。用意した機材は、プレーヤーはローディのTTU1000にフィデリティリサーチFR64fxトーンアーム。カートリッジはゴールドバグ・ブライヤー、トランスはアントレーET100、コントロールアンプはマッキントッシュのC29とウエスギU・BROS1、パワーアンプはマッキントッシュのMC2255、ウエスギU・BROS3、マイケルリン&オースチンのTVA1というラインナップである。
結果は、まさに、ドラマティックな変貌であった。到底、部屋と多少の機材の変更からは想像のつかない変りようだったのりだ。
前回の条件に近づけるため、まず、トランジスターアンプで試聴した。マッキントッシュC29とMC2255である。ハイドンの「軍隊」交響曲のイントロダクションが流れた途端、それは先週聴いた同じスピーカーとは全く違った響きであった。弦のしなやかさ、空間のプレゼンスが、このレコードの鳴るべき音で鳴ったのである。アレグロの第1主題におけるヴァイオリンが、かつての粗さが出ず、すっきりとした響きの中に芯の通ったリアルなものであった。木管の輝きと柔軟さも、適度な距離感をもって聴こえるのだった。
これは確かにタンノイの音だ。それも、かなり上質の豊かな響きである。フィッシャー=ディスカウがバレンポイムの伴奏で新録音したシューベルトの〝冬の旅〟も、ピアノのきりっと締った響きといい、バリトンのまろやかな声といい、まず申し分のないものと感じた。続いて、ジャズをかけてみたが、これがまた大変よく弾む。タンノイの旧製品のように低音が重くないし、SRMシリーズに共通の張りのある明快さと力強さを兼ね備えている。初めの試聴時にはパワーアンプがMC2500であったが、この違いは、そんなものではない。第一、MC2500とMC2255は、パワーこそ500Wと250Wの差があるが、音質的にはきわめて近いものであることは確認ずみなのだ。プレーヤーはエクスクルーシヴのP3から、ローディのTU1000+FR64fxの組合せに変っているが、たしかにこの組合せは、たいへん滑らかで透明な音であることは、私の自宅で使って強く印象づけられている。しかし、それにしても、この音の変化の大きさには驚かされる。ゴールドバグのブライヤーは初試聴の時にも使ったことは既に述べたとおり。このガイ・R・ファウンテン・メモリーにはたいへんよくマッチするカートリッジで、その柔軟で豊潤な音が生きてくるようだ。パイプの材料として有名なブライヤーの根を削り出してボディを作ったこのカートリッジのもつ手工芸の味わいは、GRFメモリー・システムの持味ともぴったりで、趣味性豊かなオーディオ・ライフを感じさせてくれる。
これで、GRFメモリーの真価は充分発揮されたように感じたが、さらに次の5種類の組合せで試聴してみた。
①U・BROS1+TVA1
②U・BROS1+U・BROS3×2
③C29+U・BROS3×2
④C29+TVA1
⑤U・BROS1+MC2255
用意したアンプの相互組合せをやってみたわけで、これらのアンプは、タンノイにベスト・マッチと思われるものばかりである。プレーヤーはTU1000+FR64fx+ゴールドバグ・ブライヤーが成功したので、これを今回のリファレンスとした。結果として整理すると、次の3種の組合せにしぼってよいだろう。
①マッキントッシュC29+MC2255
②ウエスギU・BROS1+オースチンTVA1
③ウエスギU・BROS1+U・BROS3×2
つまり、試聴した計6種の組合せで、この3種以外は、参考までに試聴したわけで、もし、飛び抜けた組合せが発見されればと思ったわけだが、そうはいかなかった。というより、あえて、トランジスターと管球式のハイブリッドを試みる必然性はなく、バランス上、同種の組合せのほうが完成度が高かったというべきだと思う。
既に、この研究シリーズで、タンノイを鳴らすゴールデン・カップリングとして、②のU・BROS1+TVA1を推薦してきたが、今回はこれに、パワーアンプも上杉研究所のU・BROS3を、それも2台用意し、各々をパラレル接続にしてモノで使う組合せを加えた。こうすることにより、U・BROS3の控え目なパワー50Wを90Wに上げられるし、音質的にも、やや淡白であったものが、ぐんと力と艶がのってくるように感じられたのである。オースチンのTVA1の熱っぽい音とはちがうが、品のよさ、滑らかさ、透明感といったこのアンプの特質は格別の魅力のあるものだ。ぜいたくな使い方だが、2台をパラレル接続で使うと力の点での弱点をカバーできて、ある意味では従来のゴールデン・カップリングを凌ぐといってよい。エモーショナルにはオースチンのTVA1がもつ充実のサウンドに軍配が上るが、メンタルには、U・BROS3のほうが端正で透明なのだ。この二種の組合せには甲乙つけ難いのが正直なところである。情熱的な音を嗜好されるならTVA1を、洗練度の高さを求められるならU・BROS3になるだろう。
これら二種の管球アンプの組合せは、たしかに、トランジスターアンプのマッキントッシュの組合せとは音の質感や発音性に違いがある。しかし、これも、どちらが勝っているとはいい難いのである。緻密な情報量ではマッキントッシュのほうが優れているように感じられるが、音の流動感と立体感では一味、管球アンプの組合せに魅力がある。ハードなジャズやロック、フュージョンまで鳴らすことを考えると、マッキントッシュの組合せのほうが力を発揮すると思うが、ポピュラー・ヴォーカル、あるいは、スイング・ジャズぐらいまでなら、そして、クラシックからセンスのよいソフトなポピュラーという範囲でなら、U・BROS1+U・BROS3×2の品位の高い音の魅力が生きるはずである。いずれにしても、この3種の組合せは、タンノイの新しい魅力的なシステム、ガイ・R・ファウンテン・メモリーの可能性を100パーセント発揮させてくれることだろう。
故ガイ・R・ファウンテン氏と創立時代より共に仕事をしてきたロナルド・H・ラッカム氏が、ファウンテン氏のメモリー(追憶)というモデル名のこの製品に情熱を燃やしたことが今回の試聴でよく判った。紛れもないタンノイ・サウンドが保持されながら、新しい録音に対応できる、よりヴァーサタイルな性格をもつことは、同時に参考試聴したオートグラフとの比較で明らかであった。クラシックモニターとの差も勿論あったが、概して共通のキャラクターといってよさそうだ。それよりも、部屋や、そこへのセッティング、使い手との関係による音の変化のほうがよほど大きいので、あまり機械自体の特質を重箱の隅をつつくような見方は控えたい。しかし、この新しく古い丹精なエンクロージュアと対面して音楽を聴けば、モダンなデザインのSRMシリーズ(クラシックモニターも共通のデザインだ)とは趣きも雰囲気も違った音が聴こえて当然だろう。視覚によって、音の印象が変化しないような鈍感な人間は、もともとオーディオの世界とは縁なき衆生ではなかろうか。
アルテック Model 6041
JBL L150A
BOSE 901 SeriesIV
ウエストレーク・オーディオ TM-3 Monitor
シーメンス Sachsen
テクニクス SB-6
エレクトロボイス Sentry100
井上卓也
ステレオサウンド 59号(1981年6月発行)
「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より
このシステムは、エレクトロボイス社が放送局及びスタジオモニターシステムとして小型、高能率それに周波数特性が軸上で3dBダウンのポイントが低域で45Hz、高域で18kHzを目標に開発した新製品。
ユニット構成は、20cm口径ウーファーとスーパードーム型と名付けられたトゥイーターの2ウェイ型で、クロスオーバー周波数は2kHzにとられている。ユニット関係では、放送局用コンソールのあまりハイパワーでないパワーアンプでも、例えばロックンロールのディスクジョッキーが要求するパワーを得るために高能率が要求され、300〜2000Hzで91dBが得られているが、この値は米国では高能率の部類に入るようすである。また、テープデッキの早送り、巻戻し時のキューイングでトゥイーターを破損しないように、ドーム型トゥイーターの許容入力は、通常のタイプの約5倍の25Wに耐える設計である。
システムとしての許容入力は、長時間の使用では30W、10ミリセコンドの短時間なら300Wと発表されている。インピーダンスは6Ωとあるから、全般に能率を上げるためにインピーダンスをかなり下げる設計が広く採用されている昨今では、むしろ平均的な値といえよう。ちなみに、5万円以下の国内製品ブックシェルフ型では公称インピーダンスが8Ωで、実際の最低インピーダンスが4Ω以下というシステムも存在している。最低インピーダンスを知らぬユーザーが8Ωと信じて比較試聴をすれば、このようなシステムは見掛け上で高能率と思いやすいことに注意すべきである。
このセントリー100で注目したいのは、場所的にモニタースピーカーを任意の位置にセットし難い放送局などのスタジオ使用状態に合わせるために、別売のSRB7ラックマウント兼ウォールマウントキットがある。これを使えば、19サイズのラックに前面から取付け可能だということだ。
エンクロージュアも業務用を考慮して外装はマットブラックのビニール仕上げだ。
セントリー100の豊かでやや制動の効いた低域をベースに、少し薄い中域、スムーズな高域という典型的2ウェイバランスの音だ。音色は低域が重く粘りがあり、高域は適度に明るい。モニターとしては穏やかな音で長時間の試聴でも疲れないタイプ。
タンノイ Autograph
菅野沖彦
ステレオサウンド 59号(1981年6月発行)
特集・「’81最新2403機種から選ぶ価格帯別ベストバイ・コンポーネント518選」より
デュアル・コンセントリックK3808ユニットは別名スーパーレッドモニターと呼ばれる38cm口径の同軸型2ウェイである。これを、複雑な折り曲げホーンの大型エンクロージュアに収めたもので、オリジナルは、タンノイの創設者、G・R・ファウンテン氏のサイン(オートグラフ)を刻印してモデル名とした名器。これを日本の優れた木工技術で復元したものが、現在のオートグラフ。高次元の楽器的魅力に溢れた風格あるサウンド。
マッキントッシュ XRT20
菅野沖彦
ステレオサウンド 59号(1981年6月発行)
特集・「’81最新2403機種から選ぶ価格帯別ベストバイ・コンポーネント518選」より
24個のトゥイーター・アレイをもつ、3ウェイ27ユニット構成というユニークなシステム。緻密な計算と周到な測定技術によって開発された抜群の指向特性によるステレオフォニックな音場再現、驚異的なリニアリティによるDレンジの大きなハイパワードライブ、広帯域の平坦な周波数特性など、物理特性でも最高水準のものだが、その音の品位の高さ、自然な楽器の質感や色彩感の再生は群を抜く、実に高貴な音だ。




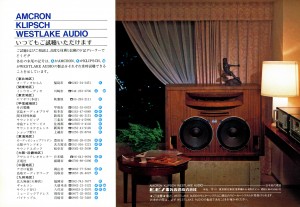

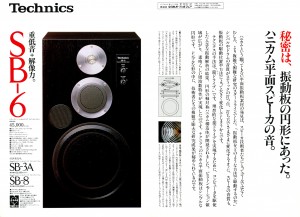
最近のコメント