オットーのスピーカーシステムSX-P2の広告
(モダン・ジャズ読本 ’80掲載)
オットー SX-P2
アキュフェーズ C-240, P-400
ヤマハ NS-590, NS-890
QUAD 44
井上卓也
ステレオサウンド別冊「AUDIO FAIR EXPRESS ’79」
「注目の’80年型コンポーネント355機種紹介」より
QUAD405パワーアンプのペアとなるコントロールアンプ。待望久しい新製品の登場である。外観から受ける印象では、管球式の22、ソリッドステート化された33のイメージを受け継いだ、クォードらしい伝統の感じられるデザインである。
内部のコンストラクションは、その外観から予想するよりははるかに現代的な、それもプロ用機器的なプラグイン方式のモジュールアンプを採用していることに特長がある。基本的なモジュールの組合せは、フォノ、チューナー、AUX、2系統のテープの入力系をもつが、任意のモジュールアンプの組合せが可能であり、近く、MCカートリッジ用フォノモジュールも発売される。なお、このモジュールには交換用のプッシュボタンが付属している。
機能面は伝統的な高域バリアブルフィルターに加えて、ティルトコントロールとバスコントロールを組み合わせたトーンコントロール、フォノとテープモジュールのゲインと負荷抵抗の切替え、フォノ入力とプリアウトにピンプラグがDIN端子と併用するなど、一段と使いやすくなり、リファインされ、コントロールアンプにふさわしい魅力をもっている。
オーディオテクニカ AT150E/G
Lo-D HS-230, HS-430, HS-630
ハーベス Monitor HL
井上卓也
ステレオサウンド別冊「AUDIO FAIR EXPRESS ’79」
「注目の’80年型コンポーネント355機種紹介」より
BBCモニター、LS5/1、LS3/5Aなどの設計者として著名なハーウッドが設立したハーベス社の最初の製品である。
20cmウーファーは、ハーウッド自身が開発した新材料ポリプロピレンコーン使用が特長で、ダンプ材なしで優れた特性が得られる。ソフトドーム型トゥイーターは、仏オーダックス製で、空芯コイル採用のネットワークで2kHzでクロスオーバーされ、能率の差はタップ型のオートトランスにより±0・5dB以内に調整され、工場で固定してある。
このシステムは、スムーズに伸びたレスポンスをもち、すばらしく反応が早いクリアーな音に特長がある。音像定位は明快で、十分に奥行きのある音場感は特筆に値する。
ビクター Zero-7, Zero-5
ソニー AHF, BHF, CHF
オンキョー Integra T-419, Integra T-417, Integra T-410 DG, Integra T-406
コンラッド・ジョンソン Power Amplifier
井上卓也
ステレオサウンド別冊「AUDIO FAIR EXPRESS ’79」
「注目の’80年型コンポーネント355機種紹介」より
コンラッド・ジョンソンのコントロールアンプは、シンプルなデザインにふさわしい、シンプルな回路構成によって、ナチュラルな管球アンプの新しい魅力的な音を聴かせて話題になったが、これとペアとなるパワーアンプである。
パワー管は、米国のKT88ともいえる6550Aのウルトラリニア接続のAB級で、バイアス調整回路はLED表示である。増幅段は、電源部に定電圧電源を採用し、安定度を向上している。なお出力端子はツインバナナプラグで差込み方向を変えて、インピーダンス切替えを行う。
安定感のある豊かな低域をベースとした、力強く、豪快な音は、やはり米国のアンプならではのキャラクターだ。
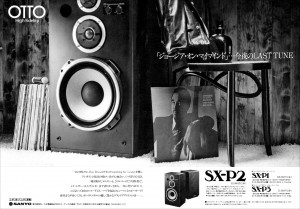

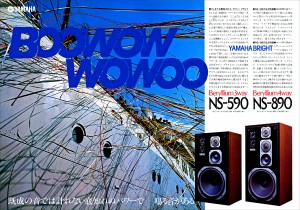





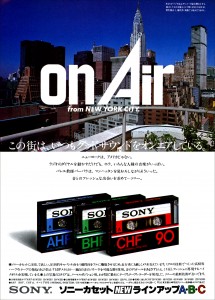








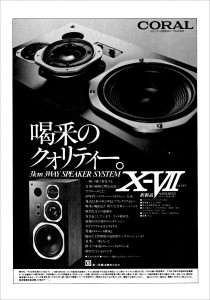


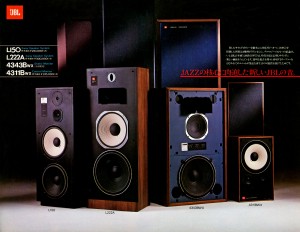
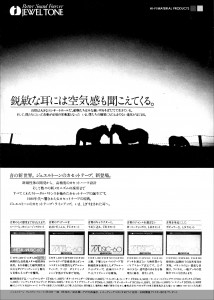
最近のコメント