マイクロのアナログプレーヤーMR422の広告
(スイングジャーナル 1973年10月号掲載)
Monthly Archives: 9月 1973
マイクロ MR-422
オンキョー Integra A-722
岩崎千明
スイングジャーナル 10月号(1973年9月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
発表時点より、少し時間を経た新製品、オンキョーA722が、今月のSJ選定品として選ばれた。
少々遅れての登場には理由がないわけではない。
つまり、今月のSJ試聴室には2台のA722がある。1台は、当初のもので、もう1台はその後運び込まれた新製品だ。この2台の中身は、実はほんの少しだが違いがある。
結論をいうならば、この2台は外観も、規格も、仕様の一切は変らないのだが、その音に少しの差がある。それも、低音から中低音にかけての音のふくらみという点で、ほんの少々だが新しい方が豊かなのだ。
それはSJ試聴室のマッキントッシュMC2300の響きにも似た豊かさといえよう。このわずかながらの音の向上が、今月の選定品として登場するきっかけにもなったわけだ。
というのは、A722は新製品として誕生した時に、選定品たり得るべきかどうかで検討を加えられたが、ピアノの左手の響きなどに不満を残すとして、紙一重の差で選考にもれ保留されたのであった。
その後、この音質上の問題点があるステレオ雑誌において痛烈な形で指摘されるところとなった。
オンキョーのアンプは、従来それと同価格の他社製品にくらべ、きめのこまかい設計技術とそれによって得られる質の高い再生に、コスト・パーフォーマンスが優れているというのが定評であった。それは市版アンプの中でも一段と好ましいサウンドを前提としていわれてきたのであるが、そのサウンドというのは、トランジスター・アンプらしからぬナチエラルな響きに対する評価をいう。
初期のA722においては、オンキョーアンプの特長で
もあるクリアーな響きが、紙一重に強くでたためか、硬質といわざるを得ない冷やかさにつながる響きとなってしまっていたようだ。その点が特に低い音量レベルで再生したときに、より以上強くでてしまうのは確かだ。出力60ワット、60ワットという高出力アンプであるA722をメーカーの想定する平均使用レベルよりもおさえた再生状態では、上記のことがいえる。
A722を当初より手元において使っていた私自身、A722のロー・カットをオンのうえ、トーンコントロールは低音を400Hzクロスオーバーで4dBステップの上昇の位置で使っていたことを申し添えておこう。
ところで、こうした再生サウンドのあり方は、メーカー・サイドでもいち早く気付くところとなり、ここではっきりとした形の改良が加えられた。
今月、加わったA722はこうしたメーカーの手による新型なのである。
当初から、大出力アンプA722に対して、8万円を割る価格に高いコスト・パーフォーマンスを認めていた私も、A722の中低域の引締った響きに、豊かさをより欲しいと感じていたが、その期待を実現してくれた。
トーンコントロールの低域上昇によっても、中低域の豊かさはとうてい解決できるものではない。トーンコントロールで有効なのは、低音においてであり、決して中低域ではないからだ。
もっとも、響きが豊かになったからといって決して中低域が上昇しているわけではない、アンプ回路設計のひとつの定石である負帰還回路のテクニックに音色上の考慮を加えたということである。性能、仕様とも技術的な表示内容が変らないのはそのためだ。
なにか長々と改良点にこだわり、多くを費してしまったようだが、それは下記の点を除いてA722がいかなる捉え方をしても、きわめて優れたアンプになりえたからだ。
もうひとつの不満点というのは、そのデザインにある。8万円近いA722が5万円台のA755と、一見したところ大差ない印象しかユーザーに与えないという点だ。確かにコストパーフォーマンスという点で、並いる高級アンプの市販品群の中にあって、ひときわ高いオンキョーのアンプには違いないが、そうした良さを備えているだけにより以上高級アンプとしてのプラス・アルファのフィーリングが欲しいと思うのは私だけではあるまい。
だがこれを求めるには、やはり価格的な上昇を余儀なくされる結果に終るかも知れない。
商品としての限界とマニアの希望とは、いつも両立しないのだが、この点アンプ作りのうまいオンキョーの「高級アンプA722」の悩みでもあろう。
この悩みを内含しつつも、A722はリー・ワイリーの20年ぶりの新アルバム「バックホーム・アゲイン」をひときわ生々しく、ゆったりと、きめこまやかにSJ試聴室に展開してくれたのであった。
ヤマハ NS-690
菅野沖彦
スイングジャーナル 10月号(1973年9月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
ヤマハがコンポーネントに本腰を入れてから開発したスピーカーは、どれもがヤマハらしい、ソフト・ウェアーとハード・ウェアーのバランスのよさを感じさせるものが多い。このバランスがもっとも強く要求されるスピーカーの世界で、同社が優れた製品を生みだしているのは同社のそうした体質の反映と受け取ることができるだろう。
かつて好評を得たNS650を頂点とする三機種のシリーズ、つまり、NS630、NS620に続いて、そのアッパー・クラスのシリ−ズとして開発されたのが、NS670、NS690という新しい製品である。前のシリーズとはユニットから全く新しい設計によるものであって、今回の2機種は、いずれも、高域、中域にソフト・ドームのユニットをもつ3ウェイ・システムである。エンクロージュアーは完全密閉のブックシェルフ型であって当然、アコースティック、エア・サスペンジョン・タイプのハイ・コンプライアンス・ウーファーをベースとしている。
今月号の選定新製品として取上げることになったNS690は、もうすでに市販されていると思うから、読者の中には持っておられる方もあるかも知れないが、ごく控え目にいっても、国産スピーカー・システムの最高水準をいくものであり、世界的水準で見ても、充分このタイプとクラスの外国製スピーカーに比肩し得るものだと思うのである。
世界的にブックシェルフが全盛で、しかもソフト・ドームが脚光を浴びているという傾向はご承知の通りであるが、このNS690も、よくいえば、そうしたスピーカー技術の脈流に乗ったもので最新のテクノロジーの産物であるといえる。しかし、悪くいえば、オリジナリティにおいては特に見るべきものはない。ヤマハはかつて、きわめてオリジナリティに溢れた平板スピーカーなるものを出してオーディオ界に賑やかな話題を提供したメーカーであり、独自の音響変換理論をアッピールし、しかも、これをNS、つまりナチュラル・サウンドとうたって、同社の音の主張を強く打出したメーカーであることは記憶に新しい。その考え方には私も共感したのだが、残念ながら、その思想は充分な成果として製品に現われたとはいえなかった。しかし、欧米の筋の通った一流メーカーというものは、自分の主張を頑固なまでに一貫し、これに固執して自社のオリジナリティーというものを長い時間をかけて育て上げていくと、いう姿勢があるのだが、この点で、ヤマハがあっさりと世界的な技術傾向に妥協したことは、精神面において私の不満とするところではある。だからといって平板を続けるべきだというのではないが……。もっとも、これはヤマハに限らず、全ての日本のメーカーの姿勢であって、輸入文化と輸入技術の王国、日本の体質が、そのまま反映していることであって、同じ、日本人の一人としては残念なことなのであるがしかたがあるまい。無理矢理なオリジナリティに固執して、横車を押すことの愚かさをもつには日本人は利巧すぎるのである。したがって、このN690も、これを公平に判断するには日本の製品という概念をすてて、よりコスモポリタンとしての見方をもってしなければならないだろう。そしてまた、世界的な見地に立って見るということは、専門技術的に細部を見ることと同時に、より重要なことは、結果としての音を純粋に感覚的に評価することになるのである。
このスピーカーの基本的な音としての帯域バランス、歪の少ない透明度、指向性の優れていることによるプレゼンスの豊かさと音像の立体的感触のよさなどは、まさに、世界の一流品としてのそれであると同時に、その緻密なデリカシーと、一種柔軟な質感は、日本的よささえ感じられるという点で、音にオリジナリティが感じられる。これは大変なことであって、多くの日本製スピ−カーが到達することのできない音の質感と、それとマッチした音楽の優しさという面での細やかな心のひだの再現を実現させた努力は高く評価できるものだ。反面、音楽のもつ力感、鋼鉄や石のような強靭さとエネルギッシュで油っこいパッショネイトな情感という面で物足りなさの出ることも否めないのである。私の推量に過ぎないが、これは中、高域にソフト・ドームを使ったシステムの全てがもつ傾向であるようで、これが今流行のヨーロッパ・トーンとやらであるのかもしれないが……?
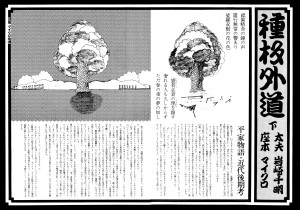

最近のコメント