井上卓也
ステレオサウンド 53号(1979年12月発行)
「SOUND QUARTERLY 話題の国内・海外新製品を聴く」より
トーンアームにエレクトロニクスの技術を初めて導入し、バランス、針圧などの全てを電子的にコントロールする電子制御トーンアーム(バイオトレーサー)を搭載したプレーヤーシステム、PS−B80は、ソニーの技術水準の高さを世界に示す優れた製品であるが、この優れた再生能力を実用価格帯の製品に実現したものが、このPS−X75である。
トーンアームは、垂直と水平方向に、独立した速度センサーとリニアモーターを備え、速度型フィードバックにより低域共振を従来より約3dB以上抑え、低域共振による混変調歪と低域のクロストークを改善している。また、バランス調整は手動であるが、光学式レコードサイズ選択、盤面上の部分送りを含むアーム操作を含めたオート機構、針圧調整、自動インサイドフォース調整などは完全に電子制御化され、フロントパネルで任意にコントロールできる。
プレーヤーベースは、独自のSBMC複合成形材と特殊ゲル状粘弾性体インシュレーター使用。モーターはクォーツロック高トルク型リニアBSLモーターの、マグネディスク回転数検出型で、電磁ブレーキが付属する。トーンアーム軸受はロングスパン構造、高さ調整付。亜鉛ダイキャスト合金製の強固なアームベース付で、内線材はリッツ線使用。滑らかで自然なバランスが音の特長。
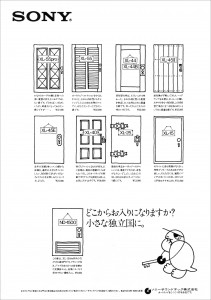
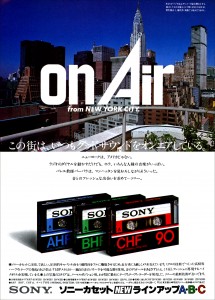



最近のコメント