dbxのエンハンサー117、119の広告(輸入元:エレクトリ)
(オーディオアクセサリー 1号掲載)
Category Archives: アンプ関係 - Page 74
dbx 117, 119
マランツ Model 3600, Model 250M
マークレビンソン LNP-2
瀬川冬樹
月刊PLAYBOY 7月号(1975年6月発行)
「私は音の《美食家(グルマン)》だ」より
アメリカには、超弩級のマニアがいる。マーク・レヴィンソンもそのひとり。まだまだ納得がいかないといいながら、世界最高のプリアンプをつくった。
黒ヒョウを思わせるパネル前面に並ぶ無数のツマミは、ただひたすら、カートリッジがひろった音を、忠実無比にスピーカーに送りこむ。このプリアンプあってこそ、カートリッジもスピーカーも、その真価を発揮するといえる。ビューティフルなメカが、ハッピーなサウンドを生む好例だ。アメリカ、マーク・レヴィンソンLNP2(プリアンプ)108万円。
セクエラ Model 1
瀬川冬樹
月刊PLAYBOY 7月号(1975年6月発行)
「私は音の《美食家(グルマン)》だ」より
世界のオーディオ界を、アッといわせたかつての名チューナー、マランツMODEL10Bを作った技術陣がセクエラという別会社をつくって製作した最新のチューナーである。現代エレクトロニクスの粋を集めて作ったこのセクエラ・MODEL1は、128万円。もちろん、周波数帯域は、日本のそれに、本国アメリカで修整されている。オシログラフのさまざまな波形が、聴く楽しみと同時に見る楽しみをもつけくわえている。
Lo-D HA-1100
岩崎千明
スイングジャーナル 7月号(1975年6月発行)
「SJ選定新製品試聴記」より
Lo−Dアンプが全製品イメージ・アップして、一挙に新シリーズに改められた。
歪0・006%と、かつてない驚異的な低歪率特性で、名実とも、Lo−Dのトレード・マークはますますその輝きを増すことになったわけだ。音声出力に対して歪成分はなんと6/10万という信じられない値である。
今ではすっかりスピーカー・メーカーとして体質を変えてしまったが、英国にリークというアンプ・メーカーの老舗がある。モノーラル最終期の50年代後半までは、英国を代表する高級アンプのメーカーとして今日のQuadよりもはるかに高高いイメージをもった高級志向の実力メーカーであったこのリークの名が、一躍世界の檜舞台へ踊り出て脚光を浴びるきっかけになったのが、歪0・1%のアンプで、その低歪をそのまま商品名としたポイントワン・アンプであった。
10数年の歳月がたった今日、0・006%と2ケタも低い歪特性が達成されたのが、Lo−Dブランドであるのは決して偶然ではあるまい。例えばLo−Dの名をもっとも早く定着させたブックシェルフ・システムHS500は、歪0・5%という。これがデビューした当時にしては驚くべき低歪特性であったことは有名だ。その後昨年発表した大型スピーカー・システムHS1500は歪率0・1%を実現している。
カセットにおいても、その常識をぶち破る低歪、ワウ・フラッター特性を、カートリッジにおいても……というようにLo−Dブランドの目指すものが、単にブランドとしての名だけでなくて、まぎれなく実のある低歪を確立しているのは、まさに瞠目べき成果であろう。そして、今日の新シリーズ・アンプの0・006%!
新シリーズ・アンプに達する以前からも日立のアンプの高品質ぶりは、内側では早くからささやかれていた事実だ。ベテラン・ライターやエディター達はその擾れた再生能力については一目も二目もおいていたともいっても過言ではない。ただ、そのおとなしい再生ぶりとデザインとが、アピールをごく控え目におさえてしまっていた。新シリーズになって、それではデザイン・チェンジによって強烈なイメージを得たかというと、必らずしもそういう派手な形にはなっているわけではない。しかし、ごくおとなしい、つまり大人の雰囲気の中に外見からも格段の豪華さが加わったことだけは確かだ。パネルの右側に配された大型のコントロールつまみ。これひとつだけで、日立のアンプはまったくそのイメージを一新してしまったのだ。もっとも大きく変ったのは、外観ではなくて、0・006%歪の示すように、その内容面の質的向上である。もともと、日立のアンプの優秀性は、その電子技術の所産としての高性能ぶりにあったのだし、今日それは格段の高性能化への再開発を受けし、アンプとしてきわめて高いポテンシャルを獲得したのである。
日立のアンプの大きな特長、オリジナル技術がこの高性能化の土台となっているが、それは例えば、ごく基本的なパワー・アンプについていえば、インバーテッド・ダーリントン・プッシュプル回路であろう。インバーテッド・ダーリントン・プッシュプル回路を採用しているアンプとしては、米国のマランツ社のアンプがトランジスタ化と同時に今日に至るまで、高級品がすべてインバーテッド・ダーリントン回路である。。他社製品が多くコレクタ接地回路のパワーステージであるのに対してのインバーテッド・ダーリントン回路はエミッタ接地のPP回路だ。これによって、パワー段の増幅度が大きくなるので、パワー・アンプは増幅度が高く、回路構成は簡略化されるので低歪のためのNFは安定化されるし、基本的に低歪であるが、そのためにはドライバー段の設計はきわめてむつかしいといわれ、マランツのアンプが日本メーカーコピーされることがないのもその辺が理由であった。日立の場合はすでにキャリアの永い「定電流駆動ドライバー段」の技術の延長上にこうしたインバーテッド・ダーリントンPP回路が成果を結んだとみてよかろう。
パワー段のみに眼を向けるだけですでに紙面が尽きてしまったが、あらゆる点にLow Distortionへのアプローチとしてのオリジナル技術があふれる日立アンプは、他社にみられないすばらしい再生ぶりを発揮してくれる。品の良い力強さ、透明感あふれるサウンドが何よりこのアンプの高品質を物語るのである。
マークレビンソン LNP-2
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
きめ細かなゲイン調整と、トーンコントロール、それにピーク指示のできる精密音量レベル計など、JC2より音質はやや甘いが機能的にずっと充実している。しかし高価だ。
マッキントッシュ MC2105
菅野沖彦
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
出力トランスをもった同社のパワーアンプはインピーダンスに無関係に定格出力が得られ、かつ耐久性が保証される。重厚な音、美しいデザインと仕上げは満足感を与えられる。
ソニー TAN-8550
菅野沖彦
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
V−FETアンプとして登場した話題の製品。ピーク・メーターつきのデザインで、中域の充実感、質感に優れたアンプだ。音楽のもつニュアンスが濃やかで、しかも暖い。
SAE Mark IIICM
菅野沖彦
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
片チャンネル200Wを越えるパワーアンプとなると、アメリカ製にキャリアがある。この製品はその中でも特筆してよい音のよいアンプ。あくまで明解で力強い。
パイオニア Exclusive C3
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
海外の高級品と比べてもひどく高価で、単純に価格、性能比を考えれば割高には違いないが、長期に亘ってモニターした結果、音質、操作性とも相当に優秀だと思った。
パイオニア SC-3000
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
いまとなっては回路構成やその他に少々古めかしさが感じられるが、内容や仕上げのよさを考えると、いまやこの価格では単体の高級プリアンプとしては格安の印象を受ける。
マークレビンソン JC-2
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
ひとつひとつの音が実にかっきりと鮮明で、入ってきたあらゆる信号を細大漏らさず忠実に増幅しているという印象。SNも優秀。ばかげて高価だがほかにこういう音質はない。
ラックス CL30
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
先にキットで発売されたので、単に同じものと誤解する人が多いらしいが、パーツの一部をはじめとしていろいろ改良されて別のものになっている。CL35/IIIよりも質的に優秀。
QUAD 33
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
性能もデザインも実にユニークで洒落ていてこういう製品が存在することがうれしくなる。とうぜん、パワーアンプの♯303、チューナーのFM3と組み合わせるべきである。
プリアンプ/パワーアンプのベストバイを選ぶにあたって
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
セパレートタイプはどうしても割高につくのだから、デザインや操作性や大きさを含めた置きやすさや、機能の豊富さあるいは独自性、そして最も重要な音質の良さ、などのどれかの項目で、プリメイン一体型ではできない何か、がなくては困る。ところがプリメイン型の性能がエスカレートしてきたために、一体型で達成できない項目が減ってしまい、セパレートであることの意味あいが薄れはじめている。この辺でそろそろ、メーカーにはセパレートの意義を洗い直して発想の転換を試みるよう望みたいところだ。
ヤマハ CR-600
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
プリメインの600よりもずっとソフトな音が意外なくらいで、一般的なリスナーを対象とした商品という現れか。その点がかえってハイレベルのファンにも受けそうな魅力だ。
サンスイ 771
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
かなり金がかかっていることを外観から知るが、豪華なのはレシーバーの客層を考えれば当然といえる。やや割高だが、中をのぞけばそれが信頼性を支えていることをも知れる。
ニッコー R-5000
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
輸出に精を出していたキャリアが抜群のコストパフォーマンスを引き出して、豪華な風格と、内容の豊富さとをうまく製品に満たした点、国産レシーバーのひとつの傑作。
パイオニア SX-434
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
市販レシーバー中のスーパーベストセラーというべき実績にのって、デザインを改めて豪華になったのも商品としての魅力を減らさぬメーカーの偉大なる努力の賜だ。
L&G R-3400L
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
日本ばなれしたデザインは、あるいは今日ではちょっと早すぎるかも。海外製品と並べてもなおこの個性は秀逸だ。若者の個室の一隅にあれば、そのセンスの良さの象徴となる。
パイオニア SX-737
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
レシーバーをステレオの入門用としてのコンポと考えるならば、価格の割に豊富で高い内容はまさにお買徳品。つまり初心者にも納得できる良さ、バランスのとれた製品だ。
ヤマハ CR-400
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
FMの感度に、もう一歩と望むのはこの価格からは無理というもの。市販レシーバー中級群のデザインと使い良さは時代を越えた永久的な魅力といえる。誰にも薦められる良さ。
トリオ KA-9006
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
7006の音質をベースに、パワーの増加とそれにともなう中~低音域のいっそうの充実感で、耳当りのいい穏やかな音色ながらバランスの良い音質を響かせる。
ヤマハ CR-1000
岩崎千明
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
サブ用として居間などにぜひ一台は欲しくなるのが音楽の分る高級マニアだろう。つまりこのアンプの質は外観の斬新さ以上にオーソドックスな絶対的良さを秘めているのだ。
ラックス L-507
瀬川冬樹
ステレオサウンド 35号(1975年6月発行)
特集・「’75ベストバイ・コンポーネント」より
SQ505、507以来、永い期間をかけて暖めてきたという、ロングセラーの実績を評価したい。但しパネルの色調は、507Xの明るい金色の方が品位が高かった。
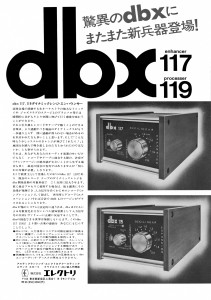
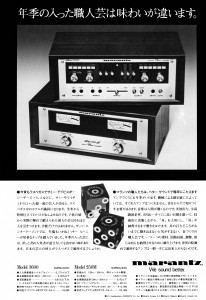
最近のコメント